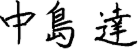CEOメッセージ

時代の転換期に立つ
2025年4月2日、世界最大の経済大国である米国が相互関税を発表し、世界に激震が走りました。第二次世界大戦後に米国が主導し構築してきた自由貿易体制を揺るがす事態に、市場は大きく混乱しました。その後、猶予措置が講じられ、一旦市場は落ち着きをみせていますが、先行きの不透明感は全く払拭されていません。今後の展開次第では、グローバル経済の減速につながるおそれもあると考えられます。
当面は、米国政府が打ち出す施策と各国の反応、政府首脳の発言等の一挙手一投足に注目が集まる混沌とした状況が続くと見込まれますが、日々の出来事に一喜一憂したり、右往左往したりせず、今起きていることの本質を見極めることが大切だと考えています。
“我々SMBCグループは、
この時代の大転換とそれに伴う経営環境の
変化に直面する難しい局面において、
重要な社会インフラとしての役割を
果たしながら、
持続的な成長を
実現していかなければなりません。”
私は、米国の相互関税に代表されるさまざまな措置について、次の政権に移行すれば元に戻るといった一過性のイベントではなく、ファンダメンタルな変化のあらわれとみています。米国の現政権は、国際秩序の前提であった新自由主義がもたらした格差や分断、貿易収支の不均衡等の「結果」として誕生したものであり、自国第一主義や保護主義、大国間の競争・対立といったトレンドは、政権交代等によって容易に変わるものではありません。また、こうした国際的な政治・経済体制の変化に、ロシア・ウクライナや中東地域でみられる地政学リスクの高まり、AIをはじめとするテクノロジーの加速度的な進化、脱炭素に向けたエネルギー源のシフトが折り重なった結果、世界は、これまでの常識や前提が大きく変わる、歴史的な大転換期を迎えたと考えています。
この時代の大転換は、当然のことながら、金融機関の経営環境にも影響を及ぼします。
ヒト・モノ・カネが自由に移動するグレート・グローバリゼーションの揺り戻しは、世界的に経済効率を低下させ、インフレ率を上昇させる方向に作用するでしょう。2010年代までの低インフレ・低金利の時代は終焉を迎え、金利がつき、上昇する世界が常態化するとみられます。また、米国は、ドルの基軸通貨としての位置付けを守り、強いドル政策を進める意向を示していますが、国際的な不均衡の是正に向けてドル安を志向する可能性も払拭できず、ボラティリティの高い状況が続く見通しです。加えて、今後は、世界各国における半導体をはじめとする生産設備の増強、グローバル・サプライチェーンの見直し、AIを支えるデータセンターの建設、クリーンエネルギーへのトランジション等に向けて、膨大な資金需要が見込まれます。金利が上昇する一方、資金需要が高まる環境において、金融機関が安定的な資金供給機能を発揮するためには、その原資となる預金がますます重要になるでしょう。
我々SMBCグループは、この時代の大転換とそれに伴う経営環境の変化に直面する難しい局面において、重要な社会インフラとしての役割を果たしながら、持続的な成長を実現していかなければなりません。
混沌の中で成長を創る
混沌とした時代の大転換期の中、SMBCグループとして、どのようにしてお客さまや社会とともに成長し、企業価値を高めていくのかが、来年度から始まる次期中期経営計画のメインテーマです。次期中期経営計画については、今まさに策定に向けた議論を進めているところであり、来年度の初めには具体的な戦略や施策をお示ししたいと考えています。一方で、グループCEOに就任して以来、現中期経営計画を土台とした戦略の方向性について経営陣で継続的にディスカッションを重ねてきました。その中で、中長期的な成長戦略の大まかな輪郭とともに、現段階での課題認識と戦略の方向性が見えてきました。
まず、我々にとって最も重要なマーケットは日本です。日本経済は、これまでの官民を挙げた取組が奏功し、長年苦しんできたデフレから脱却して、再成長に向けて動き始めました。本邦企業の経営者は自信を深めて成長投資に前向きになり、家計においても「貯蓄から資産形成へ」のシフトが鮮明になっています。国際秩序が揺らぎ混沌とする中でも、ようやく生まれたこの日本の再成長に向けたモメンタムを維持・加速していくことが極めて重要です。我々は、金融機関として、成長に向けた投資や関税措置への対応等を検討するお客さまに寄り添い、取れるリスクをしっかりと取って、ファイナンス面から支援していかなければなりません。マザーマーケットである日本は、我々にとって成長の源泉であり、世界で戦っていくための土台でもあります。どのような難局においてもお客さまを支えていけるよう、預金をベースとした盤石な事業基盤を構築していくことが重要です。
また、大国間の競争が激化し、地政学的な混乱が生じる中、わが国にとって地理的に近く、基本的価値観を共有している東南アジア・南アジア諸国との連携強化はますます重要になっています。とりわけインドは、全方位外交と政治の安定性、経済の成長性等から世界の注目を集めています。我々は、長年アジアにおいて現地法人や支店のネットワークを通じて、日系企業や地場の大企業、グローバル企業向けのホールセールビジネスを展開してきました。加えて、近年は中小企業を含むリテールビジネスへの進出を目指して、現地金融機関への出資・買収を行ってきましたが、今はまさに我々が築いたフランチャイズが活きてくる時です。現地に根差した預金をベースとするビジネスを展開し、豊富な人口を抱え、若い活力に溢れるアジア諸国の成長を後押しするとともに、その果実をフルスケールで取り込んでいきたいと考えています。それと同時に、出資・買収先のパートナー金融機関のサービスを高度化し、本邦企業を中心とするグローバル企業の現地への進出やサプライチェーンの見直しをサポートしていくことも重要になります。
さらに、膨大な資金需要に対して資金供給を行う観点から、銀行による伝統的な間接金融に加えて資本市場の役割も重要になってきます。米国では、規模が大きく裾野が広い資本市場が資金供給面で銀行を補完しており、近年は、ファンド等のノンバンクが投融資を行う、プライベートエクイティやプライベートクレジットが拡大しています。こうした銀行の資金提供機能を補完する動きは、世界に広がっていくでしょう。わが国においても、コーポレートガバナンス改革等の資産運用立国の実現に向けた動きの中で、資本市場の機能・役割が拡充されていくと見込まれます。お客さまのニーズに合った多様な調達手段を提供し、安定した資金供給機能を果たしていく。そのためにも我々は、資本市場におけるグローバルなケイパビリティを獲得し、存在感を高めていく必要があります。かねてより海外証券業務は我々の弱点であり、競合の後塵を拝してきましたが、逆に言えば、今後の伸びしろが大きいということです。
このような課題認識の下、SMBCグループは、今後、以下の3つの領域で、成長を追求していきたいと考えています。すなわち、「日本の再成長をリードする」「アジアのマルチフランチャイズ戦略対象国において、パートナーとともにダイナミックな成長を取り込む」、そして「世界の資本市場において存在感を発揮する」ということです。
また、これらの領域における成長を支える基盤として、AIをはじめとするテクノロジーの進化を取り込むためのIT投資と、我々の競争力の源泉である人材を育成するための人的資本投資を一段と強化しつつ、気候変動対応を含む社会的価値の創造に向けた取組を進めていく必要があると考えています。
冷静に、機敏に、
したたかに前進する
“混沌とした状況は大きく前進する
チャンスでもあります。
腰を据えて冷静に守りを固めつつ、
機をみるに敏に、したたかに
前進することが大切です。”
ラグビー等のスポーツにおいても言えますが、混沌とした状況は大きく前進するチャンスでもあります。腰を据えて冷静に守りを固めつつ、機をみるに敏に、したたかに前進することが大切です。2025年度は、現中期経営計画の最終年度としてしっかり施策を仕上げるとともに次期中期経営計画の策定を進めますが、先ほどの戦略の方向性に沿って、できる施策は先行して取り組んでいきます。
日本の再成長をリードする
リテールビジネスにおいては、「Olive」を通じて着実に顧客基盤を広げ、金利上昇のタイミングで個人預金残高を大きく伸ばし、クレジットカードの取扱高やSBI証券と連携したクレジットカード積立も順調に増加しています。2025年5月にはコード決済最大手であるPayPayとの提携を発表しました。日本のキャッシュレス決済比率は未だ40%程度であり、両社がタッグを組んでユーザーや加盟店を増やすことで、キャッシュレス市場の拡大を牽引していきたいと考えています。資産運用ビジネスでは、銀行・証券・信託が従来以上に連携し、銀行のお客さまに各社の商品・サービスをワンストップで提供していくことで、銀行の幅広い顧客の「貯蓄から資産形成へ」の流れに貢献していきます。また、オンラインを中心に取引しつつも時にはアドバイスを受けたいという「デジタル富裕層」に対して、SBI証券と協働して、デジタルの利便性を活かしつつ、有人のコンサルティングを組み合わせた新しい資産運用サービスを提供していく予定です。
ホールセールビジネスでは、強みである中堅企業取引において、お客さまの発展に貢献したいという高い意欲を持つ営業担当者が活躍できるよう、リスクテイク拡大に向けた制度の整備等を進め、さらに強固なプレゼンスを築くことを目指します。大企業取引については、SMBCグループ発足以来、競合との業容の差を着実に縮めてきましたが、引き続き積極的にリソースを投入していきます。そして中小企業ビジネスについては、金利が上昇する環境下において、デジタルを活用した新しいビジネスモデルを構築し、攻めに転じます。このたび開始する総合金融サービス「Trunk」を通じて、効率的な顧客基盤の拡大を図り、粘着性の高い決済性預金の獲得を目指していきます。

アジアのダイナミックな成長を取り込む
海外においては、何よりもまず採算性の改善に真正面から取り組みます。10年、20年先を見据えた、さらなる成長の土台を創ることを優先し、低採算アセットの削減を継続しながら、捻出したリソースを成長領域にしっかりと投入していきます。
戦略的に投入する領域のひとつはアジアです。これまで、我々はアジアの既存の支店ネットワークにおいてクオリティの高いアセットの積み上げと収益成長を両立してきました。そして、マルチフランチャイズ戦略の下、インド、インドネシア、ベトナム、フィリピンの4ヵ国を戦略対象国として定め、現地の金融機関に出資してプラットフォームの礎を築いてきました。2025年には最後のミッシングピースであったインドの商業銀行YES BANKへの出資を決定し、必要なピースが揃いました。これまで期待収益を実現してきたとは言い難く、これを虚心坦懐に受け止め、経営陣でも議論を重ねているところです。今後は、既存投資先の収益力向上に全力を尽くし、我々の収益の柱に育てていきます。
世界の資本市場において存在感を発揮する
もうひとつの注力領域である資本市場に関しては、海外のCIB(Corporate & Investment Banking)ビジネスの強化に取り組んでいます。オーガニックでは、プライマリ・セカンダリ一体の運営体制を整備し、プライマリビジネスで着実にマーケットポジションを高めたことで、セカンダリビジネスでも相乗効果が出てきました。さらに、Jefferiesとの提携については、協働範囲を拡大して案件も順調に積み上がっており、確かな手応えを感じています。同時に私は、この関係にまだまだ発展の可能性があるとも考えています。今後も互いの強みを掛け合わせながら、グローバル連携のさらなる加速を目指します。
また、国内では、引き続き大企業の活発なコーポレートアクションが見込まれることから、三井住友銀行・SMBC日興証券の一体運営のさらなる推進や産業調査機能の強化等を通じて提案力を強化することで、お客さまのさまざまな金融ニーズにしっかり応えていきます。
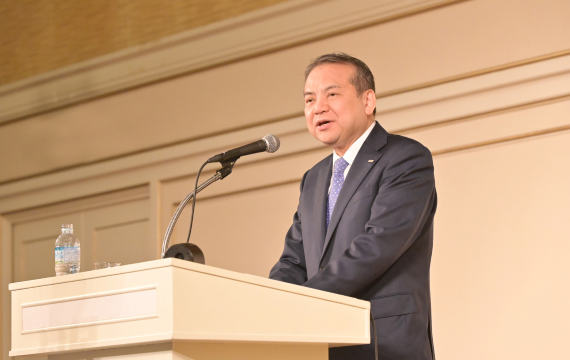
AIと人材に積極的に投資する
IT投資に関しては、特に生成AIについて、グループ全体の最優先課題として取り組む方針を明確化しており、2024年度に次期中期経営計画期間までの合計で500億円の投資枠を設定しました。AIを核として、ビジネスモデルの強化や抜本的な業務効率化、意思決定の質の向上を図りながら、それを支えるグローバルトップ人材の確保やインフラ整備を進めて競争力の源泉を作り、AI-leading Financial Institutionとしてのブランドを確立したいと考えています。
加えて、人的資本への投資も強化していきます。経営理念では「勤勉で意欲的な社員が、思う存分にその能力を発揮できる職場を作る」と謳っていますが、2026年1月に三井住友銀行で予定している人事制度改定は、まさにこの勤勉で意欲的な一人ひとりが、役割と貢献に基づいてフェアに評価され、プロフェッショナルとしてのキャリアパスを自ら設計し、自らの志向やライフステージに応じてキャリアや働き方を選択できるようにするものです。政府の後押しもあってダイバーシティも向上してきましたが、個人の職業観やライフスタイルが絶えず変化し多様化する中、今後も、一人ひとりがその人の考えに応じた働き方を選択できるような環境整備に官民挙げて取り組むことが必要です。
“SMBCグループの持つ強みを活かせる
注力領域を定めた上で、
我々らしいエッジの効いた案件を
創出するとともに、
ステークホルダーとの
連携も進めていきます。”
社会的価値を創造する
社会的価値の創造については、従業員一人ひとりが社会課題の解決に向けて行動を起こし始め、全員参加の取組の輪が広がってきました。今後も、SMBCグループの持つ強みを活かせる注力領域を定めた上で、我々らしいエッジの効いた案件を創出するとともに、ステークホルダーとの連携も進めていきます。
また、気候変動対応が喫緊の課題であることは不変ですが、外部環境が不透明化・複雑化する中、各国・地域で産業政策との結びつきがより強く意識されるようになり、欧州においても現実路線への転換の動きが見られます。我々は従前から、安定的なエネルギー供給と脱炭素化を、コストを抑えながら両立させていくことを訴えており、国や地域、セクターの固有の事情や新技術の発展、社会全体での連携等を踏まえて現実的なアプローチで取り組んでいくことが、日本経済、ひいては世界経済の発展につながると考えています。トランジションファイナンスや、新エネルギー・新技術へのリスクテイクを進めて、お客さまの脱炭素化を支援するとともに、我々自身の気候変動に関するリスク管理の高度化も図っていきます。
企業価値向上と株主還元に
向けた弛まぬ努力
当社の株価は、着実なROEの向上に加えて、金利ある世界を迎える中で、銀行ビジネスへの期待が大幅に高まったことで上昇しましたが、4月初めの混乱の中、金利上昇期待が剥落すると一時的に下落しました。混沌とした時代においてこそ、我々は手を緩めることなくROEのさらなる改善と、環境に左右されない成長期待の創出を通じたPERの向上によって企業価値を高めていけるよう、弛まぬ努力を重ねていくことが必要です。
2024年度は、国内を中心とする良好な業務環境の下、本業をしっかり伸ばしながら一時的な利益の上振れを将来への手当へ活用した上で、3期連続で最高益を更新しました。また、2025年度は、業務環境の変化を受けて当初想定していた事業計画の前提を見直し、その時点でmost likelyと考えるシナリオを前提に、現中期経営計画の最終年度にふさわしい、前年比10%以上の増益となる目標を掲げました。
さらに中長期的に目指す財務的成果については、2024年5月に公表した2025年度ROE8%という目線を2024年度に1年前倒しで達成したことを踏まえ、2025年5月、次期中期経営計画の最終年度のROEの目線を9%から10%程度に引き上げ、2030年頃には親会社株主純利益2兆円、ROE11%程度を目指すこととしました。
こうして成長した利益は、株主の皆さまにもしっかり還元していきます。現中期経営計画においては、健全性を維持した上で成長投資と株主還元にバランス良く資本配賦することを基本方針とし、CET1比率は10%程度を目線に運営しています。株主還元は配当を基本に、配当性向40%と累進的配当を維持しながら、ボトムライン成長を通じて増配の実現を目指し、自己株取得は機動的に実施します。2025年度は、利益成長に合わせて配当予想を引き上げた上で、YES BANKの出資に一定の資本を活用しつつ、5月に1,000億円の自己株式の取得枠を設定しました。不透明な環境の中、オーガニック成長のために必要な資本を見極めながら、期中も機動的に追加の自己株取得を検討していきます。また、次期中期経営計画に向けて、あるべき資本方針もしっかり検討していく考えです。
政策保有株式については、3ヵ年で2,000億円の削減計画を2024年度に前倒しで達成しました。5ヵ年で6,000億円の新たな削減計画も達成すれば、いよいよ最終局面に入ります。2024年度はギアを上げて削減を加速しており、2025年度もしっかり削減を進めていきます。
終わりに
「悲観主義者はすべての好機の中に困難を見つけるが、楽観主義者はすべての困難の中に好機を見いだす」。これは、第61代英国首相ウィンストン・チャーチルの言葉です。世界は歴史的な大転換期を迎え混沌としていますが、私も楽観主義者であり、どのような環境においても、SMBCグループは成長し、発展していけると信じています。
私のこの前向きな信念を支えるのは、世界38の国と地域で働く12万人の素晴らしい従業員たちです。我々の強みは、お客さまや社会のために尽くしたいという想いを持って、一度やると決めたら皆で力を合わせて必ずやり遂げる遂行力、エグゼキューション力にあります。私はグループCEOに就任して以来、「突き抜ける勇気。」をスローガンに、「情熱を持って、SMBCグループをより良くするために、変革に向けたアクションを起こしていこう」と従業員に伝えてきました。一人ひとりが新たな取組に挑戦し、結果にこだわって、時にスクラムを組んで助け合い、励まし合いながら、困難を乗り越えてやり遂げる。SMBCグループの従業員が一丸となれば、必ずや我々は混沌の中を突き抜け、輝かしい未来に向けてしたたかに進んでいけると確信しています。私もグループCEOとして先頭に立って、引っ張っていく覚悟です。
今後とも、より一層のご理解・ご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

三井住友フィナンシャルグループ
取締役 執行役社長 グループCEO