ATMで預金口座から気軽に現金を引き出す、積立預金や定期預金で貯蓄する、車や住宅、教育など大きな出費の際にはローンを組む――。
日本人にとって、こうしたお金にまつわる風景はすでに当たり前のものかもしれない。しかし、同じ時代を生きながらも、これらの金融サービスにアクセスできない人々が世界には数多く存在することも見逃してはいけない現実だ。
世界銀行が発行したレポート「The Global Findex Database 2021」によると、2021年時点で、世界の人口のうち14億人が銀行口座を保有しておらず、そのほとんどが新興国に集中している。アジアでは、インドで成人の約2割(2.2億人)、インドネシアでは成人の約5割(9,700万人)が口座を保有していない。
口座がなかったりうまく活用できなかったりすると貯蓄が進まず、病気やけが・災害などの予期せぬ出費や緊急事態に対応できない。また、家計が厳しい状況では融資を受けることも難しいため住宅・教育ローンが組めず、自営業者は事業拡大の機会も得られない。
このような課題の解決に向けて、誰もが必要な金融サービスにアクセスでき、それらを効果的かつ持続可能な方法で利用できる状態にするのが「金融包摂」だ。
今回は、「世界中に金融包摂を届ける」ことをミッションに掲げ、新興国を中心にマイクロファイナンスなどの金融サービスの提供を行う五常・アンド・カンパニー株式会社 代表執行役 慎 泰俊氏と、株式会社三井住友フィナンシャルグループ 執行役員 グループCSuO 髙梨 雅之が、金融包摂を巡る世界の現状や課題とそれに対する取組、両社の連携における今後の展望について対談した。
まず、マクロ視点から見た金融包摂の現状について、慎氏は世界の貧困削減や経済開発の状況をどのように捉えているのだろうか。
慎氏
2015年以降、世界的に経済開発が停滞しているとデータが示しています。理由としては、関税競争やウクライナ紛争などによるサプライチェーンの分断、権威主義政権が増え市場経済システムが弱まっていること、AIなど技術進歩を背景とした製造分野の雇用減少、世間の関心や投資が気候変動にシフトし、貧困解消や経済開発への資金供給が相対的に減少したことなどがあげられます。

絶対的貧困層※と呼ばれる人々の数は、2022年時点で約7億人と決して少なくない。これらの人々の多くは、気候変動の影響を受けやすい地域で生活しており、干ばつや洪水、気温上昇などの環境変化によって農作物の収穫や漁獲が不安定化している。その結果、栄養失調や飢餓の悪化に加え、収入の減少によって、例えば子どもが学校を辞めざるを得ないといった事態が生じている。こうした状況は、貧困の負の連鎖を一層強化し、そこから抜け出すことをますます困難にしている。
※ 国・地域の生活レベルとは無関係に、食料や衣類など生きるうえで必要最低限の生活水準が満たされていない状態。
髙梨
気候変動、人権、貧困格差、健康・福祉など、これまで個別に捉えられていた社会課題が、実は相互に関連しているという認識が強くなってきたと感じています。我々としても、貧困解消に向けて取り組むことで、他の社会課題の解決にもつながると考えています。

こうしたなか、世界の貧困を解決する方策のひとつが金融包摂だ。銀行口座を持たない個人や、金融サービスを受けにくい事業者へ金融商品・サービスを提供することで、経済活動への参加を促すことができ、生活基盤の安定や所得の向上にもつながる。では、金融包摂を実現するためには、具体的にどのような取組が必要なのだろうか。
髙梨
SMBCグループでは、インドのSMFG India Credit Company(SMICC)、インドネシアのPT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia(SMBCI)およびその子会社BTPNシャリアにおいて、低所得者や女性の方に貯金や小規模事業の立ち上げを可能にする小口融資の提供や、モバイルバンキングなどの銀行支店が不要な金融サービスの推進などを行っています。また、SMICCでは、農村の女性が日々の生計を立てるためのグループローンを始め、中小零細事業主等への無担保ローン、不動産担保ローンなどの金融商品も提供しています。さらに、SMBCIが2023年に発行したソーシャル・グリーンボンドの一部は、女性が経営する中小零細企業向けの融資に活用され、金融アクセスの拡大を加速させています。※
※ アジア事業の詳細は、コラム「アジアと共に歩む、金融包摂への道のり」参照
慎氏
新興国の低所得者層や農村部の小規模事業者にとって、無担保で利用可能なマイクロファイナンスは、新規事業の立ち上げや事業拡大に大いに役立ちます。このような融資は、経済的自立の促進や消費活動の活性化にもつながり、地域経済全体の発展に寄与するものでもあります。

また、金融包摂は金融サービスを届けるだけでは実現できない。非金融の面からもサポートすることが重要だ。
髙梨
たとえば、SMICCでは、融資先の酪農家が保有する乳牛の健康診断も行っています。搾乳量の減少は酪農事業の不安定化につながる上、我々金融機関にとっても信用コストの上昇に繋がり得るため、顧客の生活・収入や我々の事業の安定化を支える重要な取組と考えています。他にも、起業家支援プログラムや金融経済教育などを実施しています。


金融包摂の副次的な効果として、女性のエンパワーメントやジェンダー平等の推進という側面もある。実際、五常・アンド・カンパニーが提供するマイクロファイナンス利用者の9割以上が女性であり、こうした人に対してポジティブな影響を与えている。
慎氏
もともとマイクロファイナンスは、女性のエンパワーメントを目指して始まった活動でした。マイクロファイナンスを通じて女性の就労を促すことで、女性が家庭内で教育や事業投資等における決定権を持つことにつながり、結果として、家庭内で男性だけの意図に左右されない、より合理的な消費の意思決定ができるようになります。
金融包摂を加速するには、事業者間での連携の強化が不可欠だ。各々が持つ専門知識やリソースを活用することで支援の質が向上し、サービスの提供範囲も拡大できる。その一環として、SMBCグループも、五常・アンド・カンパニーとの資本面・業務面での連携を強化している。
2023年11月、SMBCグループは、五常・アンド・カンパニーと新興国での金融包摂における協業を目的に覚書を締結し、以降、五常と創業期メンバーが設立したインドのFintechファンドへも出資を行うなど連携を進めている。また、新興国の経済発展には中小零細事業主の成長が重要との考えから、2024年8月、五常グループのインド法人SATYA MicroCapital Limitedにソーシャルローンを提供した。このローンには、日本の法人や個人から集めた三井住友銀行の「ソーシャル預金」も活用される予定だ。
このソーシャルローンの実行により、両社にとって大きなインパクトも生まれているという。
慎氏
SMBCグループによるソーシャルローンの提供以来、日本の他の金融機関も追随してこの分野を加速させるなど、その影響力を強く感じています。この分野への融資は、欧米では取組が進んでいる一方、これまで日本の銀行では前例が少なかったため、業界ひいては世界全体にとっても貧困格差解消の一助となっていると思います。
髙梨
マイクロファイナンスという、これまであまり取り組んだことのない領域に融資するため、当時は社内で理解を得るにあたりさまざまなハードルがありました。貧困・格差問題に取り組むようになってから、これまで接点がなかった事業者とのつながりが増え、社内での議論もより深まるという好循環が生まれていると実感しています。

金融包摂の実現には、貧困や教育、健康、男女格差といった多様な社会課題を視野に入れ、同時に解決していくアプローチが求められる。こうした複雑な課題に取り組むには、課題解決に向けて共通の意志や知見を持つ企業間のパートナーシップや連携が不可欠となる。そして、この連携は五常・アンド・カンパニーの今後の展望においても重要だと慎氏は言う。
慎氏
現在、SMBCグループからの出向者が弊社に在籍しており、今後も連携プロジェクトを通じて新たな取組を模索していきたいと考えています。また金融教育等、非金融分野にも注力したいと思います。

個人にとって、基本的な金融サービスにアクセスできることは、自分の力で未来を切り拓くための重要な手段だ。金融包摂が進むことで、「社会から取り残されている」と感じる人や社会的な分断が減り、誰もが安心して自分らしく活躍できる社会が実現するのではないだろうか。
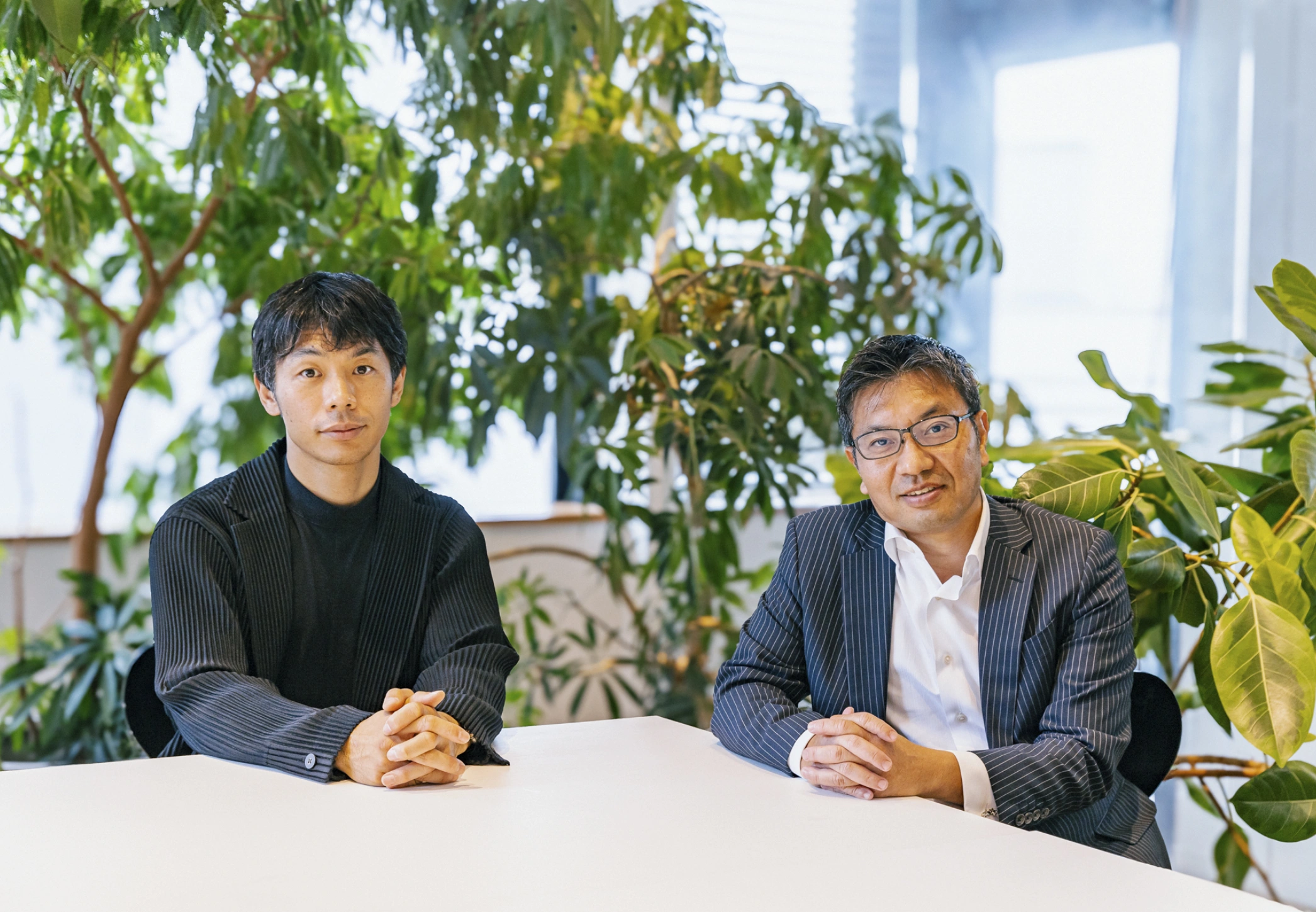
コラム
アジアと共に歩む、
金融包摂への道のり
(株)三井住友フィナンシャルグループ
常務執行役員 アジア事業戦略本部長
木許 剛
アジアの新興国では、銀行口座を持たない層や、口座を保有していても金融機関から借り入れ等のサービスを十分に受けられない層が多く、貧困・格差の改善が必要な状況にある。その一助となるよう、SMBCグループは、金融サービスへのアクセス向上に取り組んでいる。
インドネシア・インドにおける農村部などでの支援
インドネシアでは、SMBCIの子会社BTPNシャリアが、金融アクセスの乏しい農村部などで家業を営む女性を支援するマイクロファイナンス事業を主業とし、インドでも、SMICCが、農村部の顧客への貸出サービスを提供している。資金は主に、家畜の飼育、食料・衣料の製造・販売などの地域に密着したビジネスに用いられ、収入の安定化や教育を含む生活水準の向上に貢献している。
フィリピンでは金融リテラシー向上に向けた取組も
直接的な金融サービスの提供だけでなく、非金融分野での支援も重要だ。フィリピンのRizal Commercial Banking Corporation(RCBC、SMBC持分法適用会社)では、2023年から既存の顧客や学生などに対し、金融リテラシープログラムを展開している。2024年6月時点では累計6,500名が参加しており、経済的に安定した生活を築いていくための基盤の構築に寄与している。
アジアと共に成長し、より良い未来へ
アジア事業戦略本部では、『Driving Asia’s growth together. アジアを一緒に加速する。』という思いをもって、アジアの成長、アジアの人々が安心して暮らせる豊かな生活に向けて取組を進めている。SMBCグループが培ってきた全てを活かし、貧困・格差の改善、笑顔あふれる未来に少しでもつながるよう、金融サービスを通じてアジアの成長に貢献することを目指している。


