
データ利活用への関心を高めるとともに、従業員のデータ分析スキルの向上を目的として、2020年よりSMBCグループが従業員を対象に毎年開催している「D-1グランプリ」。2023年に開催された第4回 D-1グランプリには、初心者から経験豊富な熟練者まで過去最多の約560名以上が参加して大きな盛り上がりを見せました。所定の課題に対する分析の精度を競い合い、成績もリアルタイムで表示されるため、毎回参加者たちの激しいデッドヒートが繰り広げられます。
SMBCグループが取り組むデータ利活用推進施策の現状と今後の展望について、D-1グランプリの運営側と参加者側へのインタビューで明らかにします。
未経験の参加から、データ分析の沼にハマる
「D-1グランプリ」を開催している、データマネジメント部とはどのような部署なのでしょうか。D-1グランプリの概要と合わせて教えてください。
髙橋(一)データマネジメント部はSMBCグループ全体におけるデータ利活用の推進と正確かつ安全なデータ管理体制の構築、それらを支える人材の育成・確保などを担う部署です。D-1グランプリはSMBCグループの全従業員を対象にした、データ分析の精度を競うコンテストです。すでに4回実施しており、2023年の第4回 D-1グランプリではまったくの未経験者から現役バリバリのデータサイエンティストまで、過去最大となる約560名が参加しました。グループ全体でもデータ利活用への関心が高まっているので、このコンペを通じて効率よくスキルアップを果たしてもらうことが狙いです。
課題(例:国勢調査からの世帯収入予測、Jリーグの観客動員数予測)に対する回答は開催期間であれば何度でも出すことができて、そのなかの最高点を競うシステムです。挑戦すればするほど高得点を狙えるので、皆さんが夢中になることで自然とスキルアップにつながります。

データマネジメント部 戦略企画グループ長
髙橋 一誠氏
井上さんは全4回のD-1グランプリすべてに参加されていると伺いました。最初はまったくの未経験だったと。
井上はい。私がD-1グランプリに参加したのは「参加者は事前にPython(パイソン)※1のeラーニングを無料で受けられる」という点に魅力を感じたからです。これまでの人生でカラーテレビやインターネットの登場など、多くの技術革新を見てきましたが、これからのビッグデータの時代にはPythonが当たり前のスキルになると感じていました。ですので、無料のeラーニングと聞いて参加しない手はないと思ったわけですが、正直、D-1グランプリ自体に大して興味はありませんでした。ところが実際やってみたところ、見事にデータ分析の沼にハマってしまったのです。今改めて振り返ると、大規模なコンペに、大きな予算を割いて実現させたデータマネジメント部の決断はすごかったと思います。
(※1)AI開発などで用いられる、プログラミング言語の一種

井上 洋氏
参加者が時間も忘れて没頭するイベント
D-1グランプリの面白さはどこにあるのでしょうか?
井上期間内であれば何度でも回答することができ、リアルタイムで順位が変動する点です。他の参加者もニックネームで順位が表示されるので、順位を抜かれたり抜き返したり、熱くなる要素があります。参加者は順位アップするために、更なるアイデアを考えに考え抜くので、自身のスキルアップと成長につながっていくのだと思います。
髙橋(一)深夜に順位が大きく動くこともあるので、参加者の皆さんが時間も忘れて没頭している様子が分かります。過去の表彰者からは「寝る間も惜しんでのめり込みました」「1年でもっとも楽しみにしているイベントです」といったコメントをいただいています。私が運営に携わるようになったのは第2回からですが、初めて参加した表彰式の熱気は今でも忘れられません。それまでニックネームしか分からなかったライバルたちと対面できる場所ということで、皆さん仲間意識が芽生えるようです。
井上さんは第2回のD-1グランプリで見事8位に入賞されたそうですね。その知識は業務でも活かされているのでしょうか?
井上2回目の挑戦での8位はまぐれだったと思いますが、やはり結果を出すと周囲からもデジタル人材と見なされるようで、前身の部を含め過去20年以上所属していた市場営業推進部では、D-1グランプリでの入賞後にデータ利活用チームへの加入も叶い、データ分析の研修やプログラムに参加する機会が増えました。直近の第4回では経験者部門で2位になり、一般社団法人金融データ活用推進協会が主催するデータ分析コンペティション「第2回 金融データ活用チャレンジ」でも参加者1500名超の中で総合4位を取ることができました。今年度からはデータを営業に活用するという点で、先進的な取り組みを行なっている市場ソリューション部に異動しています。これにより本腰を入れて、為替やデリバティブのデータベースマーケティングにチャレンジしていきます。
「D-1グランプリがあったからこそ、今の自分がある。D-1グランプリが私の人生を変えた。」大げさではなく、本当にそう思っています。D-1グランプリを開催してくれたデータマネジメント部の皆さまと、結果を評価してくださった上司の皆さまには本当に感謝しています。

D-1グランプリで磨いたスキルをキャリアに活かす
髙橋(雄)さんは、2023年のD-1グランプリのチーム部門において1位を獲得されていますが、参加を決めた経緯を教えてください。
髙橋(雄)私は2023年の10月に三井住友カードに入社して、カードセキュリティ統括部でデータ分析に従事しています。それ以前も金融業界でExcelを始め、SQL※2やTableau※3によるデータ分析に取り組んでいましたが、どこか物足りなさを感じていました。そこで自費でPythonを学び始めたところ、その面白さに目覚めまして。データ分析のコンテストに出てみたいと考えていたところ、D-1グランプリの存在を知って参加を決めました。
(※2)データベースを操作するための言語
(※3)データの分析や可視化を可能にするツール
髙橋(雄)さんの考えるD-1グランプリの面白さを教えてください。
髙橋(雄)課題が初心者でも分かりやすい点ですね。データ分析のコンペは外部にも多数ありますが、例えば医療用の画像から腫瘍を発見するといった専門領域の課題も多く、なかなか初心者には敷居が高いのが現状です。D-1グランプリの課題は、サッカーの試合の観客動員数やアメリカの世帯収入を予測するなど、専門知識がなくても取り組める内容となっています。最初の一歩のきっかけとして課題の分かりやすさは重要だと思います。

髙橋 雄治氏
お二人のお話を聞いて、運営サイドである髙橋さんの感想を教えてください。
髙橋(一)D-1グランプリについては、大がかりなコンペを開催して盛り上がって終わり、といった形にはしたくありませんでした。ここで磨いたデータ分析のスキルを、その後のキャリアや業務での成果につなげてもらうことが目的です。井上さんのように、まったくの初心者からデータ分析のスペシャリストになる、こういった事例がどんどん増えていくことを強く期待しています。
井上さんは初回のD-1グランプリに参加するにあたって、どのくらいの期間Pythonを学んだのでしょうか?
井上だいたい1カ月ほどでしょうか。その期間はハードスケジュールで、毎日3時間くらいは勉強しましたね。
髙橋(一)ちなみに分析ツールは、Excelも利用可能で、過去にはExcelのみ利用して入賞された方もいます。ただ、Pythonを使うとしても、約1カ月間学べば、未経験者でもD-1グランプリに参加できるようになります。今では井上さんはデータマネジメント部も太鼓判を押すほど、社内有数のデータサイエンティストとして活躍しています。
D-1グランプリを通じてスキルアップはもちろん、他部署との交流が生まれることもあるのでしょうか?
髙橋(一)D-1グランプリは参加者同士のやり取りができるコミュニティ機能も備えています。開催中はニックネームでしか他の参加者を識別できませんが、表彰式では皆さん本名で表彰されるので、そこで交流が深まることもあります。

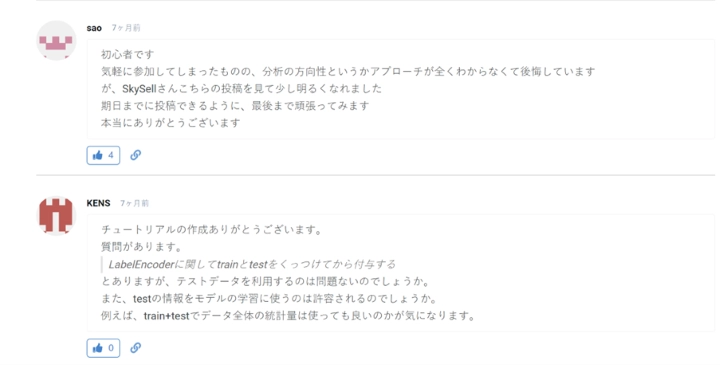
データとビジネスを繋ぎ、グループ全体のビジネスを強化
データマネジメント部の今後の展望について、D-1グランプリの展開も含めて教えてください。
髙橋(一)データマネジメント部は2016年に設立された、まだまだ新しい部署です。
今年度はグループCDAO(Chief Data and Analytics Officer)というデータに特化した役職も生まれ、取組は拡大の途上にありますが、私からすればまだまだ道半ばという認識です。グループ全体としてデータ利活用を推進していくには、一人ひとりの従業員が自分の持ち場で適切かつ、有効にデータを活用していく必要があります。データ利活用とは、何か特別な才能を持った人だけが取り組むものではありません。デジタル時代のビジネスにおいて、データ活用は必要不可欠な前提ですので、全員が理解する必要があります。
データマネジメント部としては0から1を生むステップは終えたので、次はいかにして1を10にしていくか。何か新しい目立つことを1やるだけではなく、新しい1が10に育つように、すなわちグループ全体に取組が根付くようにならないと意味がありません。
「1を10に育てる」とは、D-1グランプリ以外の施策も含めてのことでしょうか?
髙橋(一)そうですね。D-1グランプリのようなデータ分析コンペ以外にも、研修や業務支援、新規ビジネスの立ち上げなどいろいろな形があるかと思います。データ利活用に関心を持ってもらうきっかけになればと思って開催したコンペですが、現状はまだまだこうした取組が珍しいために注目されている側面があると思います。今はデータ利活用が誰しもにとって身近にはなっていないということですが、いずれは英語のように、誰もが当たり前に学ぶ域まで持っていきたいと考えています。
最後にお伝えしたいのが、データを活用できるようになるには「自分の手を動かしてみることが何より大事」ということです。井上さんも、髙橋(雄)さんも決して特別な人ではなく、日々の努力を通して、D-1グランプリで結果を残されるほどのスキルを習得されています。また、日頃の業務であまりデータ分析を行わない人であっても、自分の手を動かしてみることで、データやAIを活用して何ができるかの理解を深めることが出来ます。誰でも実際にやってみることでデータ活用できる人になるということです。また、繰り返しますが、D-1グランプリは盛り上がることだけを目的にしたコンペではありません。予算を割いて開催している以上、ビジネスとして結果を残す必要があります。データとビジネスをつないで、グループ全体のビジネス強化をさらに推し進めていきます。

PROFILE※所属および肩書きは取材当時のものです。
-

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 株式会社三井住友銀行 データマネジメント部 戦略企画グループ長
髙橋 一誠氏
2010年に三井住友銀行入行。法人営業での勤務経験を経た後、総務部にて約10年間、法務、コンプライアンス業務を経験。
2021年10月よりデータマネジメント部に異動し、データ利活用人材の育成・確保、データマネジメント戦略企画等に携わる。 -

三井住友カード株式会社 オペレーションサービス本部 カードセキュリティ統括部(東京) 部長代理
髙橋 雄治氏
2017年にSMBC日興証券に入社し、投資銀行業務に従事。その後複数のベンチャー企業で経営企画部ポジションを経て、昨年三井住友カードに入社。カードセキュリティ統括部でクレジットカードの不正抑止に携わる。
-

株式会社三井住友銀行 市場ソリューション部 シニア・マーケティング・オフィサー
井上 洋氏
2001年に三井住友銀行入行。スペシャルエキスパート職として、20年近く法人向けデリバティブ営業に従事したあと、コンプライアンスオフィサーを経て、今年度より市場ソリューション部に異動。データベースマーケティングを担当。
その他の記事を読む
-
 その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト
その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト -
 最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント
最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント
アンケートご協力のお願い
この記事を読んだ感想で、
最も当てはまるものを1つお選びください。
アンケートにご協力いただき
ありがとうございました。
引き続き、DX-linkをお楽しみください。
