急変する自動車業界に対応。SMAS(住友三井オートサービス)社長が語る、次世代モビリティとサステナビリティな社会への貢献

100年に1度の変革期が訪れているという自動車業界。激変する環境の中、EVシフト・DX・サステナビリティ、そして人材不足というさまざまな課題への対応が迫られています。
「住商オートリース」と「三井住友銀オートリース」の統合により生まれた「住友三井オートサービス(以下、SMAS/エスマス)」は、その後も数多くの企業統合を通じて様々な知見を積み上げ、従来のカーリース事業だけではなく、時代のニーズに対応しながらモビリティにまつわるあらゆる課題解決にまい進してきました。
目指すのは「サステナブルな社会に向けたモビリティプラットフォーマー」。多様化している事業について、そして「クルマ社会の発展と地球環境の向上」にどのように貢献していこうとしているのか、代表取締役社長の佐藤 計氏に伺います。
カーリースだけではない、「移動」にまつわる事業を多数展開
御社が提供するサービス概要について教えてください。
佐藤当社は法人向けのカーリースを祖業としていますが、時代のニーズに沿って様々なサービスを展開してきました。特に人材不足・人手不足の影響から、車両管理の煩雑な業務から解放してほしいという企業ニーズが急増しており、この対応に注力しています。
大きく整理しますと、当社がご提供するサービスは3段階に分かれています。まずカーリースと車両管理業務、次に社有車を使う社員・ドライバーへの支援サービス、そして車両と社員・ドライバー双方を管理する総務部の負担軽減に繋がるサービスとなります。
カーリースは当社の祖業ですが、車両管理に関わる様々なサービスとして例えば車両の購入、点検、部品交換、車検整備、事故対応などを当社が自社システムで一元管理してご提供しています。
次に社員・ドライバーへの支援サービスは、当社が数年前に開発したMaaSアプリ「Mobility Passport」をご提供しています。日報管理や社有車予約、アルコールチェック等、年々煩雑になるドライバーの業務効率を改善します。さらにレンタカーの手配も出来ますので移動に関わる手続きがスムーズになります。この「Mobility Passport」は車両台数最適化、稼働率向上にも大きな効果を発揮しており、おかげ様でユーザー数が急増しています。
そして最後に、総務部の負担軽減のサポートとして「車両管理BPO(Business Process Outsourcing)」というサービスをご提供しています。一言で言えば、顧客企業における総務業務の代行といったイメージです。

佐藤 計氏
当社は安全対策にも力を入れています。昨今は以前と比べ、主に若年層の運転機会が減ってきていますので、顧客企業のご要望に沿って、そういった方々を対象に安全運転講習を強化しています。教習所で開催することもあれば、オンラインで開催することもあります。SMASでは2019年にテレマティクスサービス※1として、車載器から取得したデータを活用する新しいサービス「SMAS-Smart Connect」の提供を開始しました。ドライバーがリスクのある運転をした際に警告を発したり、ドライバーカルテを作成して安全運転指導を行ったりもします。
この「SMAS-Smart Connect」から搭載車両から取得したデータを可視化し、お客さま専用のダッシュボードに提供しています。実際の運行データをもとに、「安全運転推進」だけでなく、「EV導入」「稼働率向上」「サステナビリティ推進」など、お客さまの様々な目的にも対応できるものとなっています。
(※1)Telecommunication(通信)とInformatics(情報工学)の造語。移動体に携帯電話などの通信システムを利用してサービスを提供することの総称。

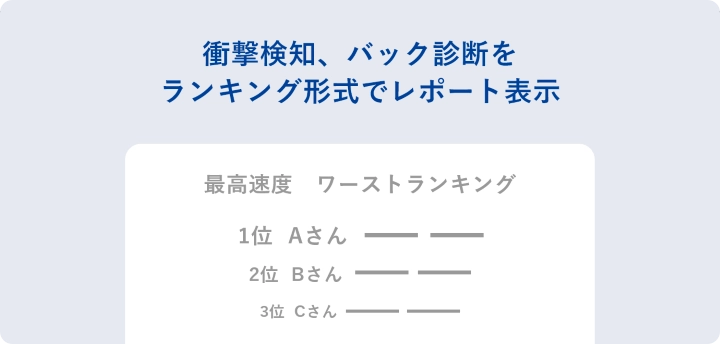
クルマや移動に対する消費者のニーズは、近年大きく変化していると思われます。SMASに対して企業が求めるニーズは、どのように変化していますか?
佐藤先ほども少し触れましたが、人手不足の影響から、車両管理のわずらわしい負担を軽減して欲しいというニーズが増えてきています。車両管理に金融機能を付加したカーリースがメイン業務だった従来と比べて、ビジネスの形式が大きく変化しています。
やはり人手不足の影響は大きくあるわけですね。
佐藤はい、例えば47都道府県で1,000台の社用車をお使いのお客さまがいたとします。モデルタイプや車両価格、使用開始時期や走行距離が異なる車両について、車検や点検、事故への対応、償却コスト計算、雪道対応のスタッドレスタイヤへの交換など、すべてを自社で行うのは大変非効率なだけではなく、相当な人材と管理体制が必要となります。SMASのサービスを活用いただければ、企業の担当者は全車両をWeb上で一元管理し、車両の状態を把握することができます。整備や輸送手配等の業務効率化を実現するだけでなく、車両の稼働率を引き上げ、1,000台の社用車の一部を減車してコスト削減するといった施策なども検討できるようになります。
自動車産業のプレイヤーが一変するEV時代
2024年3月にはコーポレート・ロゴマークを刷新し、新たな企業ブランディング広告も展開されています。なぜこの時期に刷新したのか、理由を教えてください。
佐藤今、クルマは「所有」する対象から「利用」する対象へと大きく変わりつつあります。そして、これから先は従来よりも一層、クルマというモノから、移動・輸送というサービスに世の中のフォーカスが移っていきます。さらに、従来のガソリン車からEVへのシフトが進むと、自動車産業に関わるプレイヤーも大きく変化していきます。またEVの先には自動運転に代表される、SDV※2の世界が待っています。
このように取り巻く環境が激変していくことから、当社としても目指すべき方向性を再整理し、認知度を引き上げ、プレゼンスを確立する必要があると考えました。また社名は変わりませんが、「SMAS」の4文字で世の中に認知して貰うことが重要と捉えています。そうした背景から、昨年10月には「CEATEC 2024」「Japan Mobility Show 2024」へ同時出展し、自動運転車をはじめとする実車展示や各種モビリティ・ソリューションを紹介し好評を博しました。
(※2)ソフトウェア・デファインド・ビークル。エンジン機能など一部で電気電子制御される一方、主として機械部品が協調することで走行機能を実現する車両のことをさす。

ロゴデザインも、我々が目指す「サステナブルな社会に向けたモビリティプラットフォーマー」としての方向性を謳ったデザインに一新しました。

ガソリン車からEVへのシフトが進むことで、自動車産業のプレイヤーも大きく変わるとのことですが、具体的にはどのように変わるのでしょうか?
佐藤自動車業界の経営動向に関するニュースが連日紙面を賑わせておりますが、今後もさまざまな変化が頻繁に起きる可能性があります。EVになるとクルマという名前は付いていますが、従来のガソリン車とは開発、設計、販売、サービスなど根本的に異なるものになります。またEVはSDVに繋がってきますので、DX企業の参入や、充電・エネルギーマネジメント分野との協業も増えてきます。
大きな変化が訪れるなか、我々の認知度を引き上げて、顧客企業や、様々なサービス・知見をお持ちの企業に、「まずはSMASに相談してみよう」と思っていただく流れを生み出していきたいと考えています。
多くの企業で人材不足が顕在化しています。これに対し、SMASのサービスはどのように貢献できるでしょうか。
佐藤当社のサービスをご利用いただくことで、各企業の業務負担は大幅に軽減されますし、それによって人材不足は大幅に緩和されると思います。ただもう少し先を見越した場合には、自動運転のサービスを本格普及させることも必要だと思います。それが出来れば、社会課題の解決にもなると考えています。当社は既に自動運転車のリースも手掛けておりますが、これからさらなる知見を積み上げていきたいと思います。
話は変わりますが、SMASでは全国の自治体の皆さまに対して、EVのご提案も積極的に行っています。災害時におけるライフラインの復旧は電気が比較的早いので、EVであれば電気が通っていれば動かすことが出来ます。逆に電気が止まっている場合、EVがあれば「動く蓄電池」として照明や携帯電話などに電気を供給することも出来ます。これは電気が復旧するまでの間、大変有効な活用方法となります。サステナビリティの視点だけでなく、BCP(Business Continuity Plan-事業継続計画)対策としてもEVは有効です。

EVの導入促進で、サステナビリティ課題を解決
やはり、自治体のEVに対する期待度は高いのでしょうか?
佐藤はい、各自治体の皆さまも非常に高い関心をお持ちです。我々は、サステナブルな社会を実現するために、現実的に取り得る手段の一丁目一番地がEVの導入促進と考えています。
現在、国内外から複数のメーカーのEVを集めた試乗会「SMAS e-PARK」を各地で実施しています。また、予算に応じて中古(リユース)EVのご提案も行っています。カーリースでは長期間乗車できる仕組みを取り入れることで、償却コストを抑え、EVのリース料金をガソリン車と同程度にすることができます。それでもコストが高いと感じられる場合にはリユースEVをお勧めしています。

大阪の各自治体ではリユースEVを導入して、以前よりさまざまな実証実験を行っています。例えば、バッテリー残量が少なくなって警告灯が出てから、どのくらいの距離を走れるのか?平坦な道と山道では走行距離に差が出るのか?完全にバッテリーが切れたときはどのように対処すればいいのか?といったユーザーの不安を解消するための実証実験を行ってきました。
充電スタンドの設置場所に対するコンサルティングも手がけています。自宅に充電スタンドを置くのは難しいので、運行中の経路充電ポイントをどこにするべきなのか。ユーザーの不安を払拭しながら、地道にEVの普及活動を進めています。
当社が初めてEVをリースしたのは今から16年前、2009年に遡ります。それ以来、さまざまな失敗や苦労を重ねてきました。今まで培ってきた知見や経験をもとに、EVの普及に全力で取り組んでいきます。
グローバルに事業を展開するモビリティプラットフォーマーとして
では、御社の今後の展望について教えてください。
佐藤SMASは国内で法人向けのオートリース事業を手がけてきた会社ですが、これからは海外にも積極的に拡大していきます。現在は日本以外にオーストラリア、タイ、インドネシア、インドというアジアパシフィック地域の4カ国で事業展開をしていますが、今後はできるだけ早いペースで海外ネットワークを築いていきます。
そして、海外のパートナー企業との連携も進めています。当社は現在、世界第6位の規模となる100万台超の車両を保有管理していますが、保有管理台数世界2位を誇るヨーロッパの「Arval(アーバル)」、同じく世界4位の「Element Fleet Management(エレメント)」と三社間の提携を2023年に結んでいます。この三社間で相互に顧客を紹介するなど、戦略的アライアンスを拡大していきます。
国内においては法人リースに加えて、グループ企業で個人リースを展開しています。これらに加えて、より利用期間の短いレンタカー、必要時にだけクルマを借りるカーシェアリングを当社のメニューに加え、様々なご要望にお応えしていきたいと考えています。
PROFILE※所属および肩書きは取材当時のものです。
-

住友三井オートサービス株式会社 代表取締役社長
佐藤 計氏
1961年、東京都生まれ。一橋大学社会学部卒業後の85年に住友商事株式会社入社。自動車国内事業部長、自動車リース事業部長、執行役員ライフスタイル・リテイル事業本部長、常務執行役員生活・不動産事業部門長補佐を経て、2022年、住友三井オートサービス株式会社代表取締役社長に就任、現在に至る。
関連リンク
その他の記事を読む
-
 その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト
その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト -
 最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント
最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント
アンケートご協力のお願い
この記事を読んだ感想で、
最も当てはまるものを1つお選びください。
アンケートにご協力いただき
ありがとうございました。
引き続き、DX-linkをお楽しみください。

