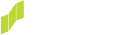�T�X�e�i�r���e�B
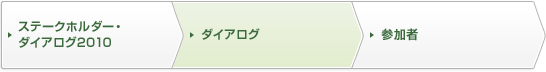
 ����̖��_�܂��A�]���̘g�g�݂̉��P�Ɍ�����
����̖��_�܂��A�]���̘g�g�݂̉��P�Ɍ�����
- �i��
- �ŏ��ɁA�uSMBC���z���]���Z���v�̊T�v�̐��������肢���܂��B
- ����
- ���s�ł�2006�N������A������Ƃ̊��ʂł̎��g�݂�]�����A�Z���̍ۂɋ�����D�����鏤�i��W�J����ȂǁA��Ƃ̊��z���������㉟�����Ă��܂����B�����2008�N10������͒�����Ƃ�����ƌ����ɁuSMBC���z���]���Z���v�̎�舵�����n�߂܂����B���z���Ɋւ���]���̋q�ϐ����m�ۂ��邽�߂ɁA�O���[�v���V���N�^���N�̓��{�����������ɋƖ��ϑ����A���q���܂ɂ��L�����������������[�Ƃ��q���܂ւ̃q�A�����O�����ƂɁA7�i�K�ŕ]������d�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B�Z���ɍۂ��ẮA���o�c�̍���̍X�Ȃ�i�W�Ɍ�����������]�����ʂ̊Ҍ�������ق��A�v���X�����[�X�ɂ����\���s���܂��B���̗Z���ɂ��A�D�ꂽ���z�������{���Ă����Ƃ�������ƂƂ��ɁA���s�����m���邱�Ƃł��̊�Ƃ̎Љ�I�]���̌���Ɋ�^���A����ɎЉ�Ɋ��o�c�̎��_���L�߂�ꏕ�ƂȂ�ƍl���Ă��܂��B
- ���c��
- �]���Ɏg�p����钲���[��q�����܂������A�Ƃ�킯������ƂɂƂ��ẮA��ʕ]����������e�̎��������悤�ł��B�܂��A�Љ�I�ɍŋߒ��ڂ���Ă��鐶�����l���̂悤�ɁA����̗���ɉ����ĕύX���ׂ����ڂ�����̂ŁA����I�ɒ����[���������K�v������܂��ˁB
- ������
- ���ꂩ��y�뉘���̂悤�ȃl�K�e�B�u�v�f�����łȂ��A���̉��P�ɂȂ���|�W�e�B�u�ȗv�f���ϋɓI�ɕ]������Ƃ悢�Ǝv���܂��B
- �ԒJ
- �����ł��ˁB�]���A������݂��Ƃ���Ƃ�����Ƃ��������Z�����ɍۂ��ẮA���X�N�ƂȂ肤��l�K�e�B�u�v�����`�F�b�N���邱�Ƃɏœ_�����Ă��Ă����̂ŁA�|�W�e�B�u�Ȗʂ�]�����ĉ��l���グ��d�g�݂�����܂���ł����B�ǂ̂悤�ȃ|�W�e�B�u�v�f��]�����邩�ɂ��Ē��o��������߁ASMBC���z���]���Z���̎d�g�݂�ʂ��āA��Ƃɂ�������z���̌���ւ̗�����[�߁A�f�[�^��~�ς��Ă������ƂŁA�������ł����z���o�c���v���X�ɕ]������d�g�݂����Ă������Ƃ��ł���ƍl���Ă��܂��B
- ���䎁
- �Ƃ���ŁA���̗Z�����悤�ƍl�����Ƃ́A���łɊ��z���������n�߂Ă��āA���M�̂����Ƃł���ˁB�Ⴂ�]������P�[�X�͂Ȃ��̂ł͂���܂��H
- ����
- ���͎����������̂悤�ɗ\�z���Ă����̂ł����A���ۂ́A�u���ꂩ����������n�߂�̂ŁA���������̊������̐i���x���������́uSMBC���z���]���Z���v�̕]�����ʂ����p���Ē���I�Ƀ`�F�b�N���Ă��������v�Ƃ�����Ƃ���������Ⴂ�܂��B
- �i��
- ���������Ӗ��ł́A�����[�̕]���̓R�~���j�P�[�V������i�Ƃ������ʂ�����܂��B���������ϓ_�ł͂������ł��傤���B
- �c����
- �t�B�M���A�X�P�[�g�ɗႦ��A�����[�̃`�F�b�N���ڂ́u��_�v�ŁA���Ђ̋��݂̃A�s�[���́u�\���_�v�̂悤�Ȉʒu�Â��ł��ˁB�X�^���_�[�h�ȕ]���ɉ����āA�����������ւ�����I�Ȗ{�Ƃ͉����A���炽�߂đ��������@��ɂ��Ȃ�܂��B�����[�̐v���悭�ł��Ă���̂ŁA���ꂩ����P���Ă����A����Ɋ��҂ł���Ǝv���܂��B�܂��A���������̊�Ƃ���ނ��Ă��钆�ŁA�L���IR�A�����̕�����CSR�̕����Ԃ̘A�g�����Ă��Ȃ��P�[�X�������Ɗ����܂��B���̂悤�ȗZ���̏ꍇ�A�L��A�����Ɗ��̒S���҂̃R�~���j�P�[�V�����̏ꂪ�ł���̂������b�g�ł��ˁB

 �M���������܂�A�Z����̍L�܂����������
�M���������܂�A�Z����̍L�܂����������
- �c����
- ��قǂ��w�E���������悤�ɁA�����[�ɂ͔��ɍׂ�����̓I�Ȏ���������āA������Ƃɂ͓������Ȃ����̂����Ȃ��Ȃ��ł��B��Ƃ̋K�͂ɂ���Đg�̏�ɍ������R�����ł���悤�ɂ��Ă͂������ł��傤���B�Ⴆ�u�ǂ�Ȋ����������Ă��܂����H�v�Ƃ����P���Ȗ₢�����ɂ��āA�R���͌������]������̂�������������܂���B
- ���c��
- �]����̖ڈ����K�v�ł��B�Ⴆ�A�ō��]�����������ƂŁA�V���Ŏ��グ����悤�Ȗ�肪���������ꍇ�A�i��������̂��B���邢�́A���ɒ�]�����������Ƃ́A���ɍ��]����_����`�����X�͂���̂��B���\���邩�ǂ����͕ʂƂ��āA���j�͂������ق��������Ǝv���܂��B���̊��z���]���̎d�g�݂́A������č��ł͂Ȃ��Ƃ͂����A����B�����ƐM�p����܂���B��x�l���������]�����������ɂȂ�悤�ł́A�]���̐M�������m�ۂł��܂���B
- ������
- �]�����ꂽ�������ێ����Ă��邩�ǂ����̃��j�^�����O���K�v�ɂȂ��Ă��܂��ˁB���j�^�����O�����{�ł����Ƃ́A�]����������ł��Ă���Ƃ������Ƃł��B
- ���䎁
- ��s���]���E���j�^�����O�菇����������ׂ����ǂ����́A��̘_�_�ł����A���i�K�ł̔��f�͈꒷��Z���Ǝv���܂��B��������A�]���E���j�^�����O�̊e�i�K�ŋ�s���ǂ�����Ď�̓I�Ɋւ��邩���œ_�ł��B�����P�Ɍ��т��ݏo��̎��ƓW�J�𑣂��A��s�ɂƂ��Ă����v���ɂȂ���V���Ȏ������v�𑝂₵�Ă����邩���A��ƂƂ��Ă̋�s�ɂƂ��ďd�v�ȉۑ�ł��B
- ����
- ���ꂩ��͊e�c�ƓX�ł��̏��i��̔����邱�Ƃɉ����āA���̏��i��ʂ��Ċ��z���������x�����邱�ƂŁA�O��Z�F��s�ƌڋq�̌��ѕt�������߂邫�������ɂȂ邱�Ƃ�]��ł��܂��B
- �c����
- ���Ƃ��̂��̂����z���^�ɂ��邽�߂ɂ́A���Ȃ�̎������K�v�Ȋ�Ƃ�����܂�����A��������̂悤�ȏ��i�̎��v���g�傷��\���͑傫���Ȃ��Ă����Ǝv���܂��ˁB
 �A�g���Ċ������A���Z�ƊE�̐M�������߂���
�A�g���Ċ������A���Z�ƊE�̐M�������߂���
- ������
- �O��Z�F��s�́A�u�G�N�G�[�^�[�����v�ɂ���������Ă��܂����A���������v���W�F�N�g�Z���̎��_������g�܂�镔���ƁA1�̊�Ƃ�]���ΏۂƂ��Ċ��z���]���Z�������镔���Ƃ́A�ǂ̂悤�ɘA�g���Ă���̂ł��傤���H
- �ԒJ
 ���s�ł́A�o�c�̊NJ������ł���o�c��敔��CSR�S�̂����A���ꂼ��̃v���_�N�g�̒S���ƘA�g���Ă��܂��B�o�c��敔��ʂ��āA�g�b�v�̃R�~�b�g�����������d�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B
���s�ł́A�o�c�̊NJ������ł���o�c��敔��CSR�S�̂����A���ꂼ��̃v���_�N�g�̒S���ƘA�g���Ă��܂��B�o�c��敔��ʂ��āA�g�b�v�̃R�~�b�g�����������d�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B- ������
- �uSMBC���z���]���Z���v�ł́A��Ƃɑ��ē��{�������������t�^�����]�����O��Z�F��s�����p�����Ă��܂��B�]�������p���闧��ƂȂ邩��ɂ́A���������ɑ������������j����ɑ���R�~�b�g�����g���������Ƃ����߂���Ǝv���܂��B���̈Ӗ��ŁA���Ȃ��i�߂Ă���u�����Z�s�������v�̍���Ȃǂ��A���[�_�[�V�b�v������Đi�߂Ă����ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���B
- ���c��
- ���s�Ƃ̍��ʉ��Ƃ��Ĉ�s�����Ŏ��{����̂ł͂Ȃ��A���Z�ƊE�ňꏏ�ɘA�g���Ă��A�F�m�x���Љ�I�M��������ɍ��܂�܂��B
- ���䎁
 �s�������̍���Ɋւ��ẮA���̎哱�ł͂Ȃ����Ԃ��A�g���Đi�߂��ق��������Ǝ��͎v���܂��B�I�����_�ł́A�������A���ƕ]���ړx�̒~�ς�������Z�̃v�����A�K�ȃv���W�F�N�g��I��ŗZ�����Ă��܂��B���̕]�����m���Ȃ�A�u���̋�s�ɔC����A�Љ�ǂ��Ȃ�悤�ɂ��������v�Ƃ������]�����a���҂��瓾����悤�ɂȂ�܂��B
�s�������̍���Ɋւ��ẮA���̎哱�ł͂Ȃ����Ԃ��A�g���Đi�߂��ق��������Ǝ��͎v���܂��B�I�����_�ł́A�������A���ƕ]���ړx�̒~�ς�������Z�̃v�����A�K�ȃv���W�F�N�g��I��ŗZ�����Ă��܂��B���̕]�����m���Ȃ�A�u���̋�s�ɔC����A�Љ�ǂ��Ȃ�悤�ɂ��������v�Ƃ������]�����a���҂��瓾����悤�ɂȂ�܂��B
 �d�v�ȃL�[���[�h�́A�u�Ȃ���v��u������₷���v
�d�v�ȃL�[���[�h�́A�u�Ȃ���v��u������₷���v
- �i��
- �����̒�����Ƃł͏ȃG�l�̎��g�݂��i��ł��炸�A���̑傫�ȗ��R�Ƃ��āu�����s���v���������Ă��܂����A����ɑ��ĉ����ł���ł��傤���H
- �c����
- �u�����s���v�Ɠ����Ɂu�l��s���v���v���ɂ���Ǝv���܂��B�Ⴆ�A�uSMBC���z���]���Z���v�̒����[�ɂ��Ă��A���e���������ċL���Ɏ肪���Ȃ�������Ƃ�����͂��ł��B�܂��́A���z���ɑ��Ăǂ̂悤�Ȃ��Ƃ�����Ă��邩�A�Ⴆ�Ί��Ȃ��F�肷��u���J�E���Z���[�v��A�G�R����ɍ��i�����u�G�R�s�[�v���v�͉��l���邩�Ƃ��������Ƃ����₵�A���̌�ŊȈՉ����ꂽ�]�����@��I���ł���悤�ɂ��Ă͂ǂ��ł��傤���B�^�C�����[�ɗZ�����邽�߂ɁA�X�s�[�f�B�ɗZ���ł���悤�ɂ��邱�Ƃ��d�v�ł��B
- �c����
- ��s�́A�X�܂�����c�Ƃ̕������܂��܂Ȑړ_�������Ă��܂�����A�u���f�B�A�v�Ƃ��Ă̓���������Ă��܂��B�l�Ɛl�A�l�Ɗ�ƁA��ƂƎ����̂��Ȃ��������ʂ����܂��B���̓��F�����āA���̗Z���𗘗p����Ɖ��炩�̂������ł�����A�����֘A�C�x���g�ɎЈ����Q������ƃ|�C���g�ɂȂ�ȂǁA������Ƃ̕��X����s�̊��z���^�T�[�r�X�E���i���g���Ď��ƂW�����A�L�v�Ȑ��ʂ��o�����������Â��肪�ł����炢���ł��ˁB
- ����
- ���������Ӗ��ł́A�܂��͑����ɂ��铖�s�E�������ւ̊S�����߂āA���q���܂̈ӎ���s���𗝉����邱�Ƃ����ꂩ��܂��܂��d�v�ɂȂ�Ɗ����Ă��܂��B

 ���K�o���N�����炱���A���z�������Z�ɑg�ݍ��ސӖ�������
���K�o���N�����炱���A���z�������Z�ɑg�ݍ��ސӖ�������
- ������
- ����܂ł́u���v�Ƃ����g�g�݂��z�����u�T�X�e�i�r���e�B�v�̎��_���d�v�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B�u���Z�ƃT�X�e�i�r���e�B�v�̃e�[�}���A���ێЉ��NPO�ANGO�̊ԂŊS�����ɍ��܂��Ă��܂��B���{�ł��A���������̗a�������Ɏg���Ă��邩�A�a���҂̗���ōl���悤�Ƃ����L�����y�[����W�J����NGO������Ă��܂��B���[���b�p�ł́A�N���X�^�[���e�̐����Ɋ֗^���Ă����ƂɗZ�����Ă����s���`�F�b�N����NGO������܂��B���Љ�I���͂Ɋւ��Ă͌����܂ł�����܂��A�푈����j��Ɋ֗^���Ă����Ƃւ̗Z���́A��s�ɂƂ��ă��X�N�ɂȂ�̂ł��B�ǂ�Ȋ�Ƃɑ��ėZ�����Ă��邩�A�A�J�E���^�r���e�B�����߂�ꂽ�Ƃ��ɂ�����Ɛ����ł���A�M�������߂邱�Ƃ��ł��܂��B
- �c����
- ��{�̋�ʂ��A�X�e�[�N�z���_�[���Ƃɕ\����K�ɕς��ē`���邱�Ƃ��d�v�ȃ|�C���g�ł��B�U�߂�PR������PR����������ł���A�]���͍��܂�܂��B���̗Z���̍ő�̃����b�g�́A��͂�v���X�����[�X�ŎO��Z�F��s����ƈꏏ�Ɋ������ɗ͂����Ă��邱�Ƃ�PR�ł��邱�Ƃ��Ǝv���̂ŁAWeb�ł̃����[�X���s�ȊO�ɂ��APR���L���Ă�����邱�Ƃ����҂��܂��B�܂��A���̏��i���L�߂Ă�����ŁA�L���b�`�R�s�[�̂悤�ȃR�~���j�P�[�V�������[�h�ɂ��H�v�̗]�n�����邩�Ǝv���܂��B
��قǘb��ɂȂ����]���̕t�^�ł����A�ߋ��̍s�ׂւ̕]���ł͂Ȃ����Ƃ���ۂÂ��A�u���ꂩ��X�e�b�v�A�b�v�������l��������������v�Ƃ����p�������ʓI�Ɏ������Ƃ��ł���A��������l��������Ǝv���܂��B - ���䎁
- �]���̕t�^�Ɋւ��āA���K�o���N�����炱�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����X�N������Ǝv���܂��B���Ɋ��Ɋւ��ẮA�V���ȋK�����ł���Ƃ��A�V���ȗL�Q���������o����Ȃǂ̗\���ł��Ȃ����X�N������܂����A�N�������̃��X�N�������Ď������������Ȃ���A���g�݂��L�܂�Ȃ��B���g�݂��L�܂�ƃ��X�N�͌y������A�t�Ɏ��v�@��ɓ]����\��������܂��B���������������X�N�����ł���̂́A���K�o���N�ł��B
- ���c��
- ���Ƃ̊��z���́u����ē�����O�v�ƌ����Ă���A����͂�茵���������Ō����邱�ƂɂȂ�܂��B�����āA���z���Ɏ��g�ނ��Ƃ����҂���钆����Ƃ������Ȃ�܂��B�����炱���A���̊��z���]���Z���𒆏���Ƃɑ��čׂ₩�Ƀ��j�^�����O�ł���悤�ɁA����ꂽ������l�ނ�����d�g�݂Ƀ��x���A�b�v���Ă������Ƃ����҂��܂��B���Z���S���������̈Ӗ��ł��A����͏d�v�Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B