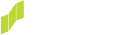サステナビリティ
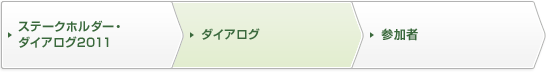
 サプライチェーンでの情報の共有化が鍵
サプライチェーンでの情報の共有化が鍵
- 沢味氏
- まず、現在の食品産業や農業が抱える課題について、ご意見をお聞かせいただけますでしょうか。
- 中嶋氏
- 戦後、人口の急激な増加と高度経済成長に対応するため、大量生産で安価に商品を提供する食料供給システムが構築され、人々の生活は潤いました。しかし、1990年代以降、豊かな食は当たり前になり、消費者の志向が変化していきました。これに対しフードチェーンは、かつてのシステムから脱皮できず、現在でも多様化する消費者のニーズに対応できているとはいえない状況です。いわば制度疲労に陥っているのです。例えば、量販店は商品の品揃えを優先して大量の在庫を抱え、売れ残ると価格を下げて販売しています。これを賄うために、製造現場では更なるコストの抑制と、効率性の追求に走らざるを得なくなっています。その影響が、サプライチェーンの川上にいる農業従事者や、川中にいる食品関連企業にまで及んでいます。こうした状況を改善するために、よりよい商品を提供し、その価値を消費者にきちんと認めてもらえるようシステムのあり方を変えていかなくてはならないと思います。
- 小沼氏
 その通りだと思います。私も、消費者の食の意識は、近年ますます高まっていると感じます。特に、2008年の中国冷凍餃子の中毒事件をきっかけに、食品の安全性や品質に対する関心は一気に高まりました。こうした流れの中で、今、求められているのは情報の発信です。食品に関する正しい情報を適宜提供することで、消費者は商品の持つ価値を見極め選別することが可能になります。こうして生まれたニーズに応じて商品の開発・製造をしていくことが今後の課題といえるでしょう。アサヒビールでは、社長の小路が提唱する「創って、造って、価値を提供する」というスローガンのもと、取り組みを推進しています。「創」は、お客さまの潜在ニーズを探り出して具現化すること、「造」は技術力を活かして安全で信頼できる高品質の商品を製造することです。この2つの視点から、既存のニーズに応えるだけでなく、期待を超えて新しい市場を創造すること、および営業活動、社会活動を通して、消費者のみならず社会への付加価値の提供を目指しています。
その通りだと思います。私も、消費者の食の意識は、近年ますます高まっていると感じます。特に、2008年の中国冷凍餃子の中毒事件をきっかけに、食品の安全性や品質に対する関心は一気に高まりました。こうした流れの中で、今、求められているのは情報の発信です。食品に関する正しい情報を適宜提供することで、消費者は商品の持つ価値を見極め選別することが可能になります。こうして生まれたニーズに応じて商品の開発・製造をしていくことが今後の課題といえるでしょう。アサヒビールでは、社長の小路が提唱する「創って、造って、価値を提供する」というスローガンのもと、取り組みを推進しています。「創」は、お客さまの潜在ニーズを探り出して具現化すること、「造」は技術力を活かして安全で信頼できる高品質の商品を製造することです。この2つの視点から、既存のニーズに応えるだけでなく、期待を超えて新しい市場を創造すること、および営業活動、社会活動を通して、消費者のみならず社会への付加価値の提供を目指しています。- 沢味氏
- 食料供給システムの再構築、新しい価値の提案、どちらにおいても情報の活用が鍵を握ることになりますね。
- 中嶋氏
- そうですね。確かに情報は鍵だと思います。農家の方々の多くは、自分たちが作った農産物が最終的にどのような形で消費者に提供されているか知らないとおっしゃいます。しかし、サプライチェーン全体でもっと情報を共有化すれば、新しい商品やサービスを開発する力が生まれるはずです。現代の消費者は「もっとよいもの」を常に求め続けています。これに応じていくには情報の活用が欠かせません。
- 沢味氏
- 例えば、アサヒビールさんでは、どのように情報を活用されているのでしょうか。
- 小沼氏
- アサヒビールでは、食品の安全性を保証するために、「原材料検査標準」「原材料リスク管理標準」などを制定し、原材料の受け入れ時と使用時に厳しい品質検査を実施するほか、「購買基本方針」に基づき、サプライヤーの皆さまにご協力いただき、原料・資材工場の訪問やアンケート調査を実施しています。こうして品質に関する情報と問題意識を共有化するとともに、不十分な点が見つかった場合には、改善に向けた取り組みを共同で推進していける体制を整えています。
- 沢味氏
- 企業が創り上げた価値を消費者に発信するだけでなく、消費者や取引先が求めることを情報として把握し、それを活用することでまた新たな価値を創造できるような、よい循環ができあがることが重要ですね。
 食品における原材料の重要性
食品における原材料の重要性
- 沢味氏
- 情報以外にも、企業が重視するべきことはさまざまあると思います。「SMBC食・農評価融資」にも多くの評価項目がありますが、特に注目されたポイントは何でしょうか。
- 山本
 制度設計では、企業として推進すべき取り組みに加え、今後の経営に関わる発展的な取り組みなどに焦点を当てて評価基準を策定しました。その際、原材料へのこだわりは、是非評価項目に入れたいとの思いがありました。というのも、近年こだわりのある商品を求める消費者が増えており、企業はそのニーズに応えるべく日々努力しています。では、こだわりのある商品とは何かというと、技術も大事ですが、最終的には原材料となる農産物に行きつくわけです。しかし、いくら原材料にこだわっても、消費者が最終商品として手に取ったときに、そのこだわりが伝わらなければ意味がありません。このような考えから制度設計にあたって、原材料まで含めた企業のこだわりを、消費者や取引先にいかに伝えていくかという部分を重視しました。
制度設計では、企業として推進すべき取り組みに加え、今後の経営に関わる発展的な取り組みなどに焦点を当てて評価基準を策定しました。その際、原材料へのこだわりは、是非評価項目に入れたいとの思いがありました。というのも、近年こだわりのある商品を求める消費者が増えており、企業はそのニーズに応えるべく日々努力しています。では、こだわりのある商品とは何かというと、技術も大事ですが、最終的には原材料となる農産物に行きつくわけです。しかし、いくら原材料にこだわっても、消費者が最終商品として手に取ったときに、そのこだわりが伝わらなければ意味がありません。このような考えから制度設計にあたって、原材料まで含めた企業のこだわりを、消費者や取引先にいかに伝えていくかという部分を重視しました。- 小沼氏
- アサヒビールの場合、ビールの主原料は麦芽やホップですが、日本のポジティブリスト制度に基づく農薬の残留基準と、サプライヤー所在国における残留基準とを比較しながら管理しています。更に、アサヒビール独自の品質規格を設けて原料・資材工場において品質監査を定期的に実施しています。近年では、品質・コスト・納期という従来の要素に加え、環境・社会面での効果とのバランスをいかに取るかが課題となっています。また、消費者に対しては、CSRレポートやWebサイトを通じてアサヒビールの取り組みを紹介することを重視しています。
- 中嶋氏
- お話の通り、最近の食品業界のCMを見ると、原材料へのこだわりを伝えるものが多数あります。しかし、消費者は原材料の重要性を十分に理解していないというのが私の印象です。特に、加工食品が、原材料にどれだけこだわる意味があるのか、必ずしも伝わっていないと思います。以前、大学の授業で生徒たちと調味料工場を見学した際、独自開発された割卵機を見せてもらいました。この機械は1分間に数百個もの卵を割ることができますが、手で黄身をつまめるくらいの新鮮な卵しか割れません。なぜかというと、それは品質のよいものをつくるための工夫なんですね。製造時の細やかな配慮を目の当たりにして、「原材料にこだわりました」とCMで訴えていることが腑に落ちました。最近は工場見学がブームですが、これは消費者に企業の努力を直に見てもらうよいチャンスになると思っています。
- 深山
- 原材料へのこだわりは、他社との差別化になるだけでなく、リスク管理という点でも効果的です。サプライチェーンの多層化やグローバル化の結果、いつ、どこで、どんな事故が起こるかわからなくなってきています。企業として原材料の調達に真摯に取り組み、事故が起こらない、もしくは起こったとしても早期に対応ができる体制を作ることで、リスクをコントロールすることが重要だと思います。
- 中嶋氏
- そうですね。拡大するサプライチェーンの中でリスクのコントロールポイントがどこにあるか。企業内でできるところは全部コントロールしていると思いますが、取引先がどのような行動をしているかも把握しなくてはいけませんね。
- 深山
- 自社ですべてコントロールすることが理想ですが、サプライチェーン全体を統括することは難しいと思います。そこでやるべきことは、自社のポリシーを示すことです。自らの姿勢や取り組みを公開することでステークホルダーへの波及効果が期待できると思います。
 企業のリーダーシップが新しい社会の創造につながる
企業のリーダーシップが新しい社会の創造につながる
- 沢味氏
- 企業のポリシーに関わる部分は、経営層の思想が大きなウェイトを占めるのではないでしょうか。
- 山本
- その通りだと思います。食と農の取り組みは新規事業や事業経営の根幹に関わることが多いため、経営層がリーダーシップを取っていくことが必要です。そこで「SMBC食・農評価融資」の評価基準では、最初にリーダーシップに関する項目を入れました。
- 小沼氏
- アサヒビールグループは、2000年に環境配慮に対する考え方・方針を具体化した「環境基本方針」を制定しました。我々はさまざまな飲料や食品を扱っていますが、そのすべてが自然由来の素材を活かしたものです。自然の恵みを育んだ地球に感謝し、環境保護に取り組んでいくことを基本理念として掲げました。こうした理念や価値観は経営者に脈々と受け継がれ、2009年に発表した“自然のめぐみを、食の感動へ。「世界品質」で信頼される企業を目指す”という長期ビジョンにつながっています。こうした自社の価値観をそれぞれのステークホルダーとどのように共有していくかが課題ですね。
- 中嶋氏
 食品関連企業の経営トップは、新しい食のあり方を提案するリーダーだと思います。アサヒビールさんの取り組みは、これまで見過ごされていたものを消費者に気づかせるよいきっかけになるでしょう。食べることは誰にとっても身近なことですから、食と合わせて情報を発信することは、新しい社会の創造につながる可能性があると考えています。しかし、夢は語るだけではなく、実現しなくてはいけません。経営者の方々には、リアリズムの立場から新しい価値を提案していただきたいと思っています。
食品関連企業の経営トップは、新しい食のあり方を提案するリーダーだと思います。アサヒビールさんの取り組みは、これまで見過ごされていたものを消費者に気づかせるよいきっかけになるでしょう。食べることは誰にとっても身近なことですから、食と合わせて情報を発信することは、新しい社会の創造につながる可能性があると考えています。しかし、夢は語るだけではなく、実現しなくてはいけません。経営者の方々には、リアリズムの立場から新しい価値を提案していただきたいと思っています。
 グローバルにもローカルにも対応した“懐の深い”評価へ
グローバルにもローカルにも対応した“懐の深い”評価へ
- 沢味氏
- 最後に、「SMBC食・農評価融資」への期待もしくは課題についてご意見をいただきたいと思います。
- 小沼氏
- ESG(Environmental<環境>、Social<社会>、Governance<ガバナンス>)投資はすでに世界の潮流として広まりつつありますが、その中でも「SMBC食・農評価融資」の誕生はエポック・メイキングな出来事だといえるでしょう。今や「食の安全・安心」というテーマは一般的に議論され、当たり前のことになった感があります。しかし、今回、評価融資に取り組んだことで、これまで食品業界は「食の安全・安心」という言葉の意味をきちんと捉えないまま使ってきたのかもしれないと、痛切に感じました。この言葉の裏には具体的にどのような行動が必要とされているのか、改めて気づかされました。「食の安全・安心」の本質を原点に戻って考えるきっかけを与えた「SMBC食・農評価融資」は素晴らしい制度だと思います。
- 中嶋氏
- 食品関連企業は、グローバルに事業を展開する大企業から、ローカルレベルでモノづくりをされている中小企業までさまざまです。「SMBC食・農評価融資」の評価項目は、どちらにも目配りができる“懐の深い”ものであってほしいと思います。例えば、グローバル化は、食の安全の保証を難しいものにするだけでなく、特定の地域への需要集中による資源の枯渇を招く危険性があり、自然への配慮が欠かせません。今、消費者が求めているのは、信頼のおける相手から信頼できる商品を買うことです。しかし、消費者のニーズが多様化しているため、どのように対応すればいいかと問われたとき、明確な答えを提示することは困難です。そのような問いに答える一助として、この融資を通じたメッセージを打ち出してほしいと考えています。
その観点でいうと、先ほど紹介のあった“自然のめぐみを、食の感動へ。「世界品質」で信頼される企業を目指す”という長期ビジョンは、“自然”が最初に挙げられている点が大変素晴らしいと思います。それから“食の感動”というのも、私がかねてより重要だと考えているキーワードです。食べることは人々に感動をもたらします。この感動を生み出すのは味だけではありません。食という文脈の中には、フェアトレードや自然との共生、地域の文化など、さまざま感動を提供する場面があるのです。こうした要素を評価項目の中に加えてもらえれば、食品メーカーにも、原材料の生産者にも励みになるし、更によいものが生まれてくるのではないかと思います。 - 山本
- さまざまな事業者にとって“懐の深い”評価にしていくこと、これは今後の重要な課題だと思います。評価手法の策定に当たっては、できるだけ多くのテーマを盛り込み、地域の中小企業なども一定の評価ができるよう工夫しましたが、評価基準の精緻化など、改善の余地が残されていると考えています。
- 深山
- 本日、皆さまのお話を伺い、社会が目指すべき方向を評価項目に採用することが、企業の食や農に関する取り組みの支援につながると実感できました。しかし、これは当行だけの力で実現できることではありません。「SMBC食・農評価融資」はさまざまな有識者の方からご意見をいただき、修正を重ねながら開発に至りました。今後も、皆さまのご意見を取り入れながら評価項目の改善に努め、銀行としてお客さまによりよい融資商品を提供すると同時に、日本の食生活の向上と農水産業の強化、ひいては社会全体への貢献を目指したいと思います。
【留意事項】
※SMBC食・農評価融資は、調査票とヒアリングにより「体制整備」の状況を評価させていただくもので、三井住友銀行が工場の監査や製品の検査をするのではなく、「食品の安全性」や「法規制の遵守状況」などを保証するものではありません。
※また、本評価は一時点かつサンプリングによるものであり、評価結果を永続的に保証するものではありません。
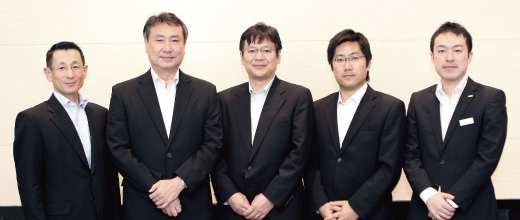
会社概要 | 株主・投資家の皆さまへ | サステナビリティ | ニュースリリース