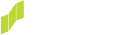サステナビリティ
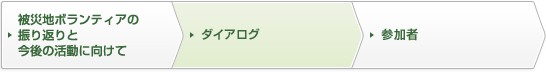
 流行ではない、継続した復興支援をしていくために
流行ではない、継続した復興支援をしていくために
- 中村
-
SMFGでは、三井住友銀行はじめグループ各社において、これまで多くの被災地支援活動を行ってきました。震災から1年4ヶ月が経過した今も、各社それぞれに活動を継続しています。本日は、被災地支援の中でもボランティア活動に焦点を当て、災害支援の専門家である吉村氏を迎え、過去・現在・未来の時間軸で考えることで、SMFGとして今後どのような支援が出来るかを検討したいと考えています。

 被災地復興の難しさを実感した震災直後のボランティア活動
被災地復興の難しさを実感した震災直後のボランティア活動
- 小河氏
- まず、これまでのボランティア活動参加者の経験を伺って、震災後の活動を振り返り、その上で吉村さんから今の被災地はどうなっているのかを伺いたいと思います。
- 大坪
- 2011年7月に東松島で初めてボランティア活動に参加しました。当時は全銀協(全国銀行協会)の仕事をしていて、銀行業界として被災地に何ができるかを考える立場にあったことがきっかけでした。現地で行ったのは側溝等に溜まったヘドロかきの仕事でした。現地の方から「何も片付いていない状況でこのまま忘れられてしまうのではないかと不安に感じている中、来てくれるだけでも嬉しい」と言われたことが非常に印象に残っています。
- 大河
- 私がボランティアに参加したのは2011年5月と6月で、それぞれ石巻と東松島での活動でした。震災から2か月が経っていたので参加前にはやることがあるのかと疑問に思っていました。しかし実際は膨大な作業が残されていただけでなく、見覚えのある石巻の風景は跡形もなくなっていて作業中は心が凍りついたように何も感じられない状況でした。そうして感情を押し殺さないと作業をすることが出来なかったからです。最終日にはそれまでこらえていた感情が溢れてしまいました。困っているのは現地の方のはずなのに、果物などを分けてくれて涙が出そうなくらい嬉しかったです。
- 船井
- 私は2011年の8月に石巻のボランティアに参加しました。震災復興の役に立ちたいと考えていたところ、社内イントラでボランティアのことを知り、部店長の後押しもあって参加を決めました。現地では写真の洗浄作業を行いました。「写真の洗浄?」と思っていましたが、実際に作業してみると持ち主にとってはとても喜ばれる作業であることが分かりました。私の出身は大阪ですが、関西の人にとってみると東北の被災地の実感がなかなか湧きにくいと思います。そのような人たちに被災地の情報を伝えていくことが、ボランティアに参加した者の役割の一つだと思っています。
- 千葉
- 2011年4月から8月まで、個人としてではなく会社として、仙台市の災害ボランティアセンターの運営スタッフ業務を行いました。SMBCコンシューマーファイナンスでは、全国に展開しているお客様サービスプラザで働く社員に参加を募り、「力になり隊」を結成し、交代で被災地にメンバーを送り込む等、全社を挙げて支援を行いました。被災地では毎日色々なニーズがあがってきます。更に活動をよくするためにどうすればいいか、日々ミーティングを行いました。スタッフの方々の被災地支援に対する志は高く、時には、非常に白熱した議論になっていました。
- 渡邊
- 私からは、SMBCコンシューマーファイナンスがボランティアセンターの運営業務に携わってきた背景をお話したいと思います。もともとお客様サービスプラザでは、震災以前から地域のニーズを徹底的に探ろうという意識を強く持っていましたので、震災直後から、「被災地にある拠点として何か役に立ちたい」という声が多くあがっていました。そこで、お付き合いのあった社会福祉協議会や地域で活動しているNPO団体の方々とお話をしたところ、運営側のスタッフが足りないことが分かりました。それであれば、サービス業として強みのある電話対応などで貢献できるだろうと、運営業務のボランティアスタッフとして参加しました。ここでの要望は短期ではなく、長期での支援でした。当初「力になり隊」は4月から6月までの予定でしたが、現地では長期運営スタッフへのニーズが強くあり、盛岡では10月末まで活動を延長しました。そこで強く感じたことは、他県の社会福祉協議会の職員も応援に来ていましたが、運営スタッフが圧倒的に少ないということです。職員の方も被災していた中で、朝から晩まで献身的に業務をしていた姿が忘れられません。
- 加藤
- 私は2011年7月にSMBC日興証券の新入社員の社会貢献活動研修として被災地支援をしてきました。ヘドロかき等側溝清掃の作業をしたのですが、想定以上の量で現地の大変さがよくわかりました。被災地の皆さまが元の生活に戻るには、とても長い時間が必要だと思いました。我々の活動に対して現地の方々は本当に感謝してくれました。物資や資金の提供だけでなく、実際に現地に入ることが大事だと思います。ボランティアは現地に本当に必要にされていることだと実感しました。
- 吉村氏
-
阪神淡路大震災のとき、火災を消せず多くの命を救えなかった悔しさが心に残っていました。震災を知ってすぐ石巻から気仙沼に入ったときには、あまりの状況に気持ちが前に出ませんでしたが、そのときのことを思い出し、諦めてはダメだと強く思いました。
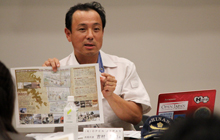
実感されていないかもしれませんが、皆さんはこれまで被災地で非常に重要な活動をしていただいています。例えば写真を一枚一枚洗浄する作業は、先が見えずととてもつらい作業ですが、本当に喜ばれることです。また、運営業務では、ボランティアとして現場に来た人たちがすぐ活動できる準備をしておくことがすごく大事です。その運営に長期間関わってくれた「力になり隊」は非常に評価できます。運営の仕事は地味だし被災者に会わないこともあるので役に立っているのかどうか迷いの出る仕事です。しかし、それができているから毎日数千人単位でくる人たちをすぐ現場に送ることができます。また、宮城では石巻、東松島と女川で7割の犠牲者が出た一方、石巻に比べて東松島にはボランティアがなかなか入りませんでした。それらの地域に率先して入っていったことも評価できるポイントだし、感謝しています。
 求められている心のケア
求められている心のケア
- 小河氏
- 震災直後と最近では被災地の状況に変化が起きていると言われています。実際にどのような違いがあるのでしょうか。
- 林
- 私は、ボランティアには過去2回参加しました。2011年7月の一回目には民家や側溝に溜まったヘドロかきを行い、2012年2月には、既に重機が入った後の土地で、重機が拾いきれなかった瓦礫の除去を手作業で行いました。一回目と二回目では求められるものが変わっていた印象があります。広域な被災地で、人の手で細かい瓦礫を除去するには数十年の時間がかかるだろうと思いました。金融機関として業務を通じた支援や義援金の拠出もあると思いますが、それよりも現地ではまだまだ人手が不足していると感じました。
- 寒河江
- 震災から11か月が経った2012年2月に、ボランティアに参加しました。世の中では震災に関するメディアの露出も減っており、なんとなく終息を感じている時期でしたが、被災地にはまだ、人の手を必要とする作業が多く残っていました。また、現地ではボランティアの受け入れ態勢がとても良く整っていて、手袋なども結局現地で借りることになりました。むしろ自分たちが助けられる立場になっていて、本当に役に立っているのかと自問を続けていました。そのような中で救われたのは「わざわざ遠くから支援をしに来てくれることだけで助けになる」という現地の方の言葉でした。物理的な撤去作業がある程度済んだ状況でも、人は人でしか救えないということが強く印象に残りました。
- 鷹羽
- 私は、新入社員の社会貢献活動研修の引率として被災地支援を行いました。SMBC日興証券では、社会貢献活動を入社時研修のプログラムの一つとして位置付けています。昨年は東松島と七ヶ浜、今年は南三陸で活動を行いました。今年度、まず昨年活動した七ヶ浜の状況を視察したところ、瓦礫はほぼきれいに片付いていたため、新入社員に臨場感が伝わらない状況でした。しかし南三陸に入った途端、バスから見える景色は一変しました。何も片付いていない現状を見た新入社員は言葉を失いました。その時の印象を今年参加した新入社員のアンケートから二例ご紹介したいと思います。
「参加前はこのタイミングで被災地のボランティアに参加することに果たしてどれくらいの意味があるのか疑問に感じていた。しかし、実際に被災地を見て180度考えが変わった。現地は悲惨な状況で、その中で頑張っている人が大勢いた。」「東北の復興は進んでいなかった。我々がやったことは小さなことかもしれないが、その積み重ねが大事だと感じた。漁師の方から感謝されたことが非常にうれしかった。これからしなければならないことはボランティアの大切さを周りに伝えることだと思う。」
私たちは今回、南三陸の漁業で養殖いかだの錘(おもり)に使用する60kgの土嚢を数多く作る、いわゆる復興支援をしに行ったのですが、現地はまだまだ復旧すらできていない場所がほとんどです。 また、物的な整理が進まないこともそうですが、仮設住宅での生活が長引くほど、心を病んでくる方が増えているようです。実際にアルコール中毒者や自殺者が増加していると聞いています。今、何が必要かと言えば、被災者の心のケアではないかと思います。 - 吉村氏
-
例えば漁業に関して言えば、「ボランティアなんかに何が出来るんだ」と漁師さんたちは外部から人を受け入れることに当初否定的でした。しかしどこから手を付けていいかわからない状況の中、ボランティアが手伝いにきた時は、自然と受け入れるようになっていました。頼れるのがボランティアしかいなかったからです。今は漁師さんたちに活気が戻ってきており、水産物の値も戻っています。

現地の人たちはボランティアの活動を良く見ています。作業の中には行政の仕事だと思うものもあるかもしれませんが、とにかく現地で活動することが、現地の人たちを後押しするし、勇気づけます。今手伝ってほしいことの一つとして、例えば自治体の復興計画を分かりやすく伝えることがあります。自治体のホームページには色んな復興プランが出ていますが、ご年配の方には意味が分かりません。そこで分かりやすく説明してくれる人がいると、とても安心できるし助かります。私たちはこのように、ボランティアスタッフそれぞれの特技や強みをいかした活動を提案しています。また、仮設住宅に関しては、酒を飲み続けて亡くなる人たちが増えています。仮設住宅では、将来に大きな不安を抱え、自暴自棄になっている人たちが増えています。これは今、非常に深刻な問題になりつつあります。
 SMFGだからできる復興支援
SMFGだからできる復興支援
- 小河氏
- まだまだ残っている瓦礫撤去などの物的な整理だけでなく、人の心のケアという課題も出てきているようです。そこで、被災地復興の今後に向け、SMFGだからできる支援には、どのようなことがあるでしょうか。
- 千葉
- SMBCコンシューマーファイナンスでは、「力になり隊」で築いたネットワークを活かしていくことができると思います。具体的には、社会福祉協議会のサポーター制度や、社会福祉協議会の「復興の輪ミーティング」というものがあります。そこでは今、仮設住宅の問題が話し合われています。例えば被災者に義援金が渡された頃、それを狙った足元を見るような宗教や訪問販売などの問題がありました。いったんは終息しましたが、今また訪問販売が問題になりつつあります。そこで、金融業の知見を活かし、金銭啓発のセミナーを開催しています。金融トラブルに合わないための講座を開催したり、今は子ども向けのセミナーも企画しています。今後は、相談相手も分からない被災者の自立を後押しするため、ライフプランニングのお手伝いをすることが可能ではないかと考えています。これは本業に直結することだけを狙うのではなく、現地でのコミュニティの形成やメンタルケア、参加した社員の見識を高めることにもつながるだろうと思います。
- 林
- 仮設住宅に住んでいる人たちの意見をお聞きしたところ、生きる意欲はあっても具体的にどのようにして自立のきっかけを得ればいいのか分からないという意見がありました。被災者のやりたいこと、やるべきことを聞きながら、金融機関として実現をサポート出来る活動ができるといいのではないでしょうか。
- 鷹羽
- 復興国債の営業をしている新入社員の中には、営業と同時に積極的に被災地の情報伝達を行っている者もいます。業務を通して接したお客さまなどに広く伝えていくことも、役目の一つではないかと思います。
- 吉村氏
- 現地に最も必要なことは継続した支援です。私はよくボランティアスタッフに、何か継続的に支援できることはないか、課題を出すことにしています。ある学生はホームページの作成に手を挙げてくれました。これは東京に帰ってからも出来る支援の一つの例です。
現地に人が戻り、以前のように復旧するには、難しい問題がたくさんあります。例えば津波の影響で元々住んでいたところに戻ることができず、移住が必要な被災者も大勢います。しかし住宅ローンが組めないなど、解決の糸口は見つかっていません。やはり一気に大きなことを目指すのではなく、継続した支援を希望します。SMFGらしく継続した支援を行うためにはこのダイアログのように、対話をする機会を設けることが重要だと思います。震災を風化させないために、社内で語り合う場などを数多く設定してはどうでしょうか。
加えて、現地から離れていてもできる具体例を一つご紹介したいと思います。阪神淡路大震災のとき、ある信用金庫が緊急通報システムを開設しました。頼る人がいない高齢者にとっては非常に重要な仕組みです。通報の窓口となる信用金庫が日常業務の中で救急車の手配をしたりする仕組みです。これは被災者のニーズに合っているだけでなく、本業の強みを生かすことができ、且つ継続した支援になります。 - 会場から
-
以前、写真洗浄の短期のボランティアを行いました。また参加したいと思っているのですが、日常の業務もあり継続した参加はできないので、自分自身は何も貢献できていないのではないかと感じています。そのような人も多くいると思いますが、短期の活動ばかりで本当に被災地の役に立てるのでしょうか。

- 吉村氏
- 数人のグループでボランティアに来てくれることはよくあります。例えば漁師さんの手伝いは一人の漁師さんに一人つくケースが多く、大人数で来るよりも対応しやすいです。このような支援は今後も必要ですし、短期、少人数での支援活動でもできることはたくさんあります。
 息長く現地に求められる活動をしていく
息長く現地に求められる活動をしていく
- 中村
-
ボランティア活動においては、現地で活動している方々との情報交換を密にし、現地のニーズを常に尊重することが大切です。例えば、被災地の仮設住宅の問題をなんとなく感じていても、東京で考えているだけでは、実際どんな問題があるのか、本当のところは分かりません。現地が望んでいないものをこちらが押し付けることは本末転倒です。吉村さんたちのような、現地で活動されている専門家の意見を取り入れながら、現地が求めている活動を行う、という方針を、常に堅持しなければならないと考えています。

また、ボランティアの経験を通じて、改めて「人から感謝される」ことのありがたさを実感し、通常の業務に持ち帰る参加者も多いようです。こればかりが目的ではありませんが、結果的にボランティア参加を通して社員の意欲を高め、それが通常の業務にも反映されるような好循環も生み出していきたいと考えています。
最後に、重要なことは「忘れないこと」だと思います。ボランティア参加者の多くは、戻ってきてから自然と所感文やレポートを書き、周りの人たちに送っています。きっと書かずにはいられない気持ちになるのだと思います。このような気持ちを持つ仲間を増やすことも大事だと思っています。被災地で息長く活動していくためには、グループ内でのボランティアネットワークを増やし、支援活動の裾野を広げていくことが重要です。今後も、多くの参加者・関係者から忌憚のない意見・アイデアをもらいながら、震災復興に向けた思いを風化させることなく、現地と継続的なコミュニケーションを続けていきたいと思います。
会社概要 | 株主・投資家の皆さまへ | サステナビリティ | ニュースリリース