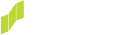サステナビリティ
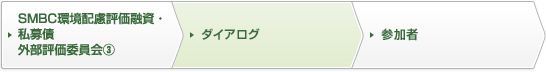
 Ⅰ.「SMBC環境配慮評価融資」の2011年度取り扱い状況を受けて
Ⅰ.「SMBC環境配慮評価融資」の2011年度取り扱い状況を受けて
2011年度の取り扱い状況
- 司会
- 最初に「SMBC環境配慮評価融資/私募債」の2011年度の状況について、説明をお願いします。
- 藤崎
-
SMBC環境配慮評価融資の、2008年10月(取り扱い開始期)から2012年3月(見込み)までの取り扱い累計件数は125件、金額にして約3,362億円にのぼります。SMBC環境配慮評価融資のスキームを使って展開しているその他の資金調達商品も含めると、実績は192件、約4,697億円となります。さらに、2006年から取扱っている中小企業向け融資商品「SMBC ECOローン」を含めた、当行の環境配慮型資金調達の累計実績になりますと、1,200件、約5,200億円となり、お客さまの取り組みが順調に拡大してきていると言えます。一度お借り入れ頂いたお客さまの中には、自社の環境経営への取り組みを客観的にチェックするため、2度、3度と繰り返しお借り入れいただく企業も増えています。
また、昨年までは融資・私募債の2つを商品の対象としておりましたが、2011年度は融資枠の設定にもお使いいただけるよう、取り扱い範囲を拡大しました。
昨年度からの改善点
- 藤崎
- 昨年度からの改善点として、環境配慮評価の軸となる評価基準を改定しました。現在、グローバルな視点で見ると、グループ全体での環境経営が重要視されています。そのため、従来は評価の範囲を単体とするかグループ全体とするかはお客さまの任意としていましたが、今回グループ全体の環境配慮状況に重きを置く評価方法に改定しました。
また、設問についても、「環境取り組みの変化の要因分析」を意図した項目を追加した他、例えば「物流過程」における環境配慮はどうかなど、プロセス毎の環境配慮状況を確認していただけるような構成としました。温室効果ガスの把握についても、自社や自社グループだけでなく、サプライチェーンの排出状況も考慮しているか確認する設問を追加しました。最後に、東日本大震災を受け、緊急時の環境影響の変化を把握できているか等の関連項目を追加しました。
加えて、昨年の外部評価委員会での意見を受け改善した点も申し上げます。まず、「本商品を通じてより多くのお客さまの環境取組みを拡大していただくために、海外にも目を向けてはどうか」というご意見や、海外企業からの環境経営に対する評価ニーズが増えている背景を踏まえ、現在、海外のお客さまの環境経営を評価できるスキームを作るべく準備を進めています。2つめに、「地方企業や地銀のサポートも必要ではないか」という意見を受け、中小企業向けの「SMBC環境配慮評価融資 eco バリュー up」のスキームを、まず三重銀行に展開しました。現在他の地銀にも展開できるよう、スキームのさらなる構築を進めており、地銀が当スキームを地方の企業に展開することで、当行がカバーできない地方のお客さまの環境取組みのご支援が出来れば良いと思っています。3つめに、「昨今のグリーンビルディングにも対応できるような商品を開発してはどうか」という意見を受け、「SMBCサステイナブル ビルディング評価融資」を開発しました。現在、2011年11月の開始から4ヶ月間で7社、10棟の建物の環境やリスク対応状況について評価をさせていただいています。最後に、「環境配慮の他に、社会性の評価も追加してはどうか」という意見を受け、2011年11月に、「SMBC事業継続評価融資」という新たな商品をリリースしました。企業が天災やIT不具合などの有事の際に、しっかりと事業の継続ができるよう、BCP(事業継続計画)やBCMS(事業継続マネジメントシステム)仕組み作りのご支援をさせていただくことを目的としています。
環境評価融資に取り組む意義について
- 藤井氏
- 企業の環境対策には、コストとビジネスの両面があると思います。金融機関として、企業が抱えている環境コストを把握しなければ、それは財務面でのリスクとなり得ます。ビジネスの側面に関して言えば、規制や各社の先駆的な取り組みによりマーケットが拡大するため、企業が抱えるリスクと機会を評価し、適正なファイナンスを付けることが望まれます。つまり、「金融が企業を育てる」といった視点が必要なのだと思います。様々な格付け等の手法や、関係省庁への規制(better regulation)策定への働きかけ等により、資源の適正配分を金融の力を用いて行うことが重要ではないかと思います。
- 司会
- 産業界では、ビジネスとしてESG評価(環境・社会・企業統治に関する評価)を開始した動きがあるようですね。
- 寺田氏
- 銀行は産業界の規範的存在であると考えられています。環境についても同様に産業界を牽引する立場であってほしいですね。ESG評価については、例えば、近年では情報サービス会社がESG情報を投資家向けに提供していますが、投資家の利用促進策については発展途上にあります。こうした取組みと環境評価融資の目的は似たところがあると考えられるため、金融界全体の取組みを促進する意味でも、評価の内容や、情報の品質レベル設定等について、連携を取ることは一つの方策ではないでしょうか。
環境評価融資を魅力ある商品にするための仕組みについて
- 宮井氏
-
パナソニックでは、環境を経営の基軸に据えており、環境対策をコストからビジネスへ転換させていかなければならないが、環境は社会システムとの連動性が高いため、個社だけでは対応が困難です。環境対応を実効的なものにするためには、大きな社会の流れを変えるような規制・インセンティブ等、社会システムの変革が必要です。また、企業としてもお客様・消費者のニーズがまだ不明瞭な状況の中で取組んでいかねばならないことから、そのような企業を支援するような仕組が重要であると考えます。

金融機関に集まる多くの情報を提供し、環境取組について企業側に気付きを与えることにより、より魅力的な環境評価融資の商品にすることが可能ではないでしょうか。 - 寺田氏
- CDP(カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト)でトップクラスに選ばれた企業とそうでない企業の過去6年の投資のリターンの開きは2.5倍になったと聞いています。企業の中でも対応レベルの差が開いているのです。
- 伊東氏
- 例えば日本の搬送業界では、ベンチャー企業が起業し難い体質となっています。過去30年~40年続いた厳しい経営環境や顧客の強い値下げ要求により、環境対応やIT化等のイノベーションが起こらなかったからでしょう。SMBC等の大手金融機関には、中堅企業のエンドユーザが「環境対応実施には、明確にメリットがある」ということを認識できるよう支援いただきたいですね。
- 藤井氏
- 金融機関には、本業を用いて環境に革新的な技術を持つ企業やベンチャー企業にファイナンスする、既存の取引関係にベンチャー企業を取り入れるようなビジネスマッチング等、従来よりも一歩踏み込んだ取り組みが必要であると考えます。特に環境分野は市場の育成が必要な分野であり、金融機関は、取引先の気づきや社会ニーズを拡大するる役割を担っていると考えています。
地方および地方銀行への展開の必要性について
- 藤井氏
- 今後は、単独での展開だけでなく、地方銀行と競合しつつ協調融資や仲介融資を実施し、環境配慮型のビジネスや地域のプロジェクト(風力や太陽光等)を共に育てる展開が望ましいと思います。先般採択された環境金融行動原則に署名されたからには、是非、原則に沿った実績を上げていただきたいですね。
- 司会
- 成長性判断や高度な与信判断が出来る地方銀行の数はまだ多くないため、藤井氏の発言の通り、先端を走るSMBCには期待される部分が大きいのではないでしょうか。
 Ⅱ.中堅・中小企業の環境経営のあり方および金融機関の関わり方について
Ⅱ.中堅・中小企業の環境経営のあり方および金融機関の関わり方について
中堅・中小企業が環境経営に取り組む意義について
- 司会
- 中堅・中小企業は、日本において、全企業数の99.7%、雇用の約7割を占めており、多くの雇用、付加価値を生み出しています。また、サプライチェーンの中核を担うなど、日本の産業の基盤を支えており、中堅・中小企業は日本経済にとって重要であるといえます。大企業が環境経営を行う上で、取引先へどのようなことを要請しているのかお聞かせ頂けますでしょうか。

- 宮井氏
-
パナソニックでは、eR ('eco ideas' relations)を基本においています。多くの「ステークホルダーと共に」との考え方に則り、取引先との協業を進めています。
具体的には、2012年4月1日に発効する予定の「グリーン調達基準第6版」において、従来の環境マネジメントや化学物質管理だけではなく、GHG(温室効果ガス)排出削減、資源循環の取り組み、生物多様性の取り組み等、より項目を広げて、多くの取引先と共に環境経営を進めようとしています。
それは、取引先様の区別ではなく、共に環境への取り組みを進めることを目的としています。これまでも取引先様とは、ECO・VC活動(共に環境経営に取り組む活動)を実施しており、今後も継続してまいります。 - 寺田氏
- 環境コミュニケーション大賞の奨励賞への応募企業(中小企業)の環境レポートの内容から伺えることは、中堅・中小企業は納入先に対するサプライヤーリスクのみを想定して取り組みを実施しているのではなく、自社の環境への取り組みレベルを向上させ、工程を効率化させることによるコストダウンを目指しているということです。環境経営を積極活用することで、調達におけるリスク(資源枯渇、エネルギー調達による価格高騰リスク、サプライヤーのCSRリスク等)をヘッジし、生産ラインの効率化によって成果を上げる中堅・中小企業が見受けられます。中堅・中小企業のエコビジネス成功事例はそれほど多くは聞きませんが、意欲ある中堅・中小企業は多いため、今後は銀行の後押し、バックアップ体制が求められます。銀行にとっては顧客担当者が個々の案件の本質を見抜いた上で、リスク(新プロジェクトや製品)に一歩踏み込めるのか、が重要になっていくでしょう。
- 宮井氏
- 生産効率の向上がCO2削減に資する等、中堅・中小企業の中には、経営活動の中で環境経営を既に実施しているケースが多く見受けられます。パナソニックのECO・VC活動のように、中堅・中小企業に自社の環境への取組み成果を気付いていただけるような視点も重要だと思います。
中堅・中小企業の環境経営を促進するための金融機関に関わり方について
- 伊東氏
-
当社は全国で一番に「SMBC環境配慮評価融資/私募債ecoバリューup」を受けたことについて、誇らしく思っています。監査法人からの環境経営に関する評価も自社の弱点を補う上で、大変参考になりました。当社が販売している顧客の省エネ率を向上させる製品は、売れば売る程、環境貢献出来るという性格を持ち合わせています。今後、融資された資金を活用し、営業の促進、商品開発に役立てたいと考えています。

- 藤井氏
- 一般的には銀行は貸出先企業の環境リスクの把握に関心が向かいがちですが、同時に取引先企業の環境に関する「プラス面」を評価し、アピールし(例:A社と取引したら、自社の環境負荷の低減が可能であることをアピールする等)、その結果を情報開示する役割、さらに取引先や顧客をより環境配慮行動をとるように促す役割も期待されています。特にSMBCには、環境評価融資取引額を上回るような社会的貢献が可能であることを認識していただきたいですね。今後は、行政規制を先取りし、日本社会が目指すべきモデル案を社会に提示してほしいと思います。
そうすることで、銀行間の横並び行動ではなく、他行との差別化(SMBCの環境経営評価はB銀行よりも高いレベルであり、取引企業の評価も高まるとの認識の広がり)も可能になると思います。そのためには、銀行自らが評価の尺度を開発することも重要です。環境の金融市場の拡大が現実しつつある今、SMBCにはプロジェクトの評価だけではなく、ラベリングなどで企業価値を更にアピールすることを推奨したいと思います。 - 吉田
-
私の所属する当行の成長産業クラスタープロジェクトチーム(現:プロジェクトファイナンス営業部 成長産業クラスター室)では、2010年7月より、今後成長が期待される分野として、環境・水・新エネルギー・資源の4セクターにフォーカスを当て、プロジェクトファイナンスや案件化に向けた事業調査等を実施しています。 環境が一つの成長分野であると捉えていますが、コストと捉えられがちな環境への取り組みを、効果的にマーケットに広げていくには、規制との連動が重要であると考えています。

また、国内に加え、海外における日本企業の事業展開も支援しています。具体的には、NEDO(独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)の補助金を受けたマレーシアのグリーンタウン化、METI(経済産業省)の補助金交付による中国・天津市のスマートグリッド等への協力が挙げられます。新興国において、電気等のライフラインは価格が抑えられる傾向にあり、これらの環境技術の導入については、成長と価格のバランスをどのように取るのかが大きなテーマとなっています。一定レベルの環境基準を求めるためには、現地国の基準の底上げが課題となっていますが、そのためには、環境基準の達成がもたらす効果を現地政府機関に示すことが重要であるため、日本政府(MOE・METI等)と連携した環境技術の普及が必要です。これらの取り組みを通じて、民間銀行として、投資回収性(バンカビリティ)のあるプロジェクトおよびそれらの効果を研究しているところです。
今後も、官民連携での基準・規制の提案実施や、中堅・中小企業の環境技術を世界に普及するためのビジネスマッチングに、銀行として積極的に取り組んでいきたいと考えています。来年度においては、冒頭にもありましたが、環境配慮型融資のアジア地域への拡大にチャレンジする予定です。 - 寺田氏
- 当社は、自社製品が売れる程、業界の省エネにつながるとの意識の下、売上の向上および新製品の開発に努めています。何より、社長自身が動くことにより、会社の良い先導力になれればと考えています。SMBCには、ベンチャー企業が成長しやすい土壌を形成するために、環境経営を推進するにあたって、エンドユーザにとってどのようなメリットがあるかアピールしてほしいですね。
 Ⅲ.おわりに
Ⅲ.おわりに
有識者からのコメント
- 寺田氏
-
宮城県山元町の復興プランでは、今までの居住地を危険区域とし、新築を禁止し、新たな場所に駅を誕生させ、コンパクトシティを誕生させる案があります。環境配慮不動産の究極の理想形はコンパクトシティであると考えていますが、地方銀行や自治体と協働し、このような意義あるプロジェクトに手を貸していただきたいと思います。メガバンクが手にしているお金の使い方により、社会や環境が大きく左右されるのではないかと考えます。

- 藤井氏
- 規制やルールが完全に整備されていない中でも、環境マーケットは発展していきます。このため、SMBCには規制ルールを後押しするような自主的な取り組みを深め、先進的な取り組みをアピールすることを期待します。その際、日本総合研究所や新日本有限責任監査法人のような専門家チームと連携し、標準化をにらんだ客観性の高い仕組みを作ることが大事です。そうした仕組みづくりで、メガバンクとしての総合力を発揮したうえで、それらを実践するフロントランナーとしての役割を社会にPRする循環が形成できればよいと思います。
環境配慮融資やESG評価等の評価の要素は、難しいようですが、よくよく考えると銀行の通常業務における企業やプロジェクトの評価においても同様の困難さや予測の要素は、含まれています。将来的には、これらの環境評価を従来型の財務評価に加え、本業の法人営業に昇華させることにより、他行と差別化を図っていける銀行が力を発揮するのではないでしょうか。 - 伊東氏
- 当社は、自社の環境配慮型製品を顧客に周知することが重要であると考えています。当社商品を使えば、ECOで快適な作業環境が得られることを、法人のエンドユーザーに独自のセミナー等でPRしているが、自社の力だけでは十分なPR活動が出来ないため、例えばSMBC主催のセミナーで事例を紹介いただくなど、バックアップをお願いしたいと思います。大企業のみならず中小企業への支援も引き続きお願いします。また、現在ある大学と、共同で植物工場の野菜の新しい環境配慮型搬送形態を研究中だが、こういったこれからの新分野へも地銀を巻き込んだ取組み支援が望まれるのではないでしょうか。
- 宮井氏
- 環境ビジネスを成長産業にするためには、意思を持って変えることが必要であり、そのためにはアピール、情報開示、コミュニケーションが極めて重要であると考えます。SMBCの環境融資は素晴らしい取り組みであるため、更なるPRの実施を推奨します。
3・11の震災を境に、環境経営の更なる加速が社会からの要請であることを強く感じるようになりました。個社だけではなく、官民連携の上で日本を変える必要性があるため、SMBCにおいても、環境評価融資制度の拡大等、更なる前進を望みます。

今回の外部評価委員会を受けて
- 成田
- 毎年、日本最大級の環境展示会であるエコプロダクツ展に出展し、中小企業の技術を紹介するビジネスマッチングを行っています。昨年は6,000件の引き合わせを行い、今年は10,000件、来年はその1.5倍とすることを目標としています。また、中小企業の環境技術を海外のローカル企業に紹介する試みも始めています。これらの活動について、PR活動が不足していることを今回認識しました。また、宮井氏の発言の通り、自社の環境への取り組みに気付いていない中小企業については、SMBCでは現場力を引き上げ、「目利きができる銀行員」を育成し、バックアップしていきたいと考えています。ベンチャーの支援については、環境を手掛けているベンチャー企業を支援するのか、またはベンチャー企業の環境取り組みを資金面から支援するのか等、更なる検討が必要であると感じました。
- 髙島
- 本日は、環境対応はコストであるとの発想から脱するためのインセンティブ、金融機関の役割についてご指導いただきました。環境に関して、各企業が明確なメリットを実感できるよう、工夫を凝らしていきたいと思います。また、環境評価の実施、評価結果の開示、PR等の活動、お客様の活動を紹介できる場の提供、企業の環境力のポテンシャル評価についてのご提案をいただき、環境配慮融資への拡大への激励も頂戴しました。今後の日本、世界、次の世代を育てるような企業が起業できるような環境を創る際に、「環境」をキーワードに据えて企業を支援することが、銀行の根源的な役割に立ち返ることでもあると気付かされました。
震災における価値観の転換を期に、ゼロサムではない豊かさを創ることの必要性を感じています。製品を売れば環境貢献につながるようなシンプルなビジネスモデルを持った企業を多く支援することが、経済的なメリットにも繋がるのではないかとの認識を持ちました。
本日は貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。
会社概要 | 株主・投資家の皆さまへ | サステナビリティ | ニュースリリース