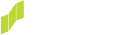�T�X�e�i�r���e�B
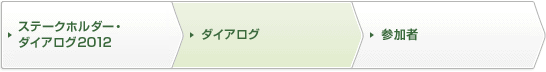
 �玙�x���ɂ���ď��q�������x�����Ă���
�玙�x���ɂ���ď��q�������x�����Ă���
- ����
 �O���ɗL���҂̊F���܂������N���A�㔼�͂��̖���N���āA�r�l�e�f�����ƂƂ��āA�܂��A���Z�@�ւƂ��Ăǂ̂悤�Ɋւ���Ă��������̂��Ή�����c�_���Ă��������Ǝv���܂��B�ŏ��ɂr�l�e�f������܂Ŏ��g��ł������e�����Љ�������B
�O���ɗL���҂̊F���܂������N���A�㔼�͂��̖���N���āA�r�l�e�f�����ƂƂ��āA�܂��A���Z�@�ւƂ��Ăǂ̂悤�Ɋւ���Ă��������̂��Ή�����c�_���Ă��������Ǝv���܂��B�ŏ��ɂr�l�e�f������܂Ŏ��g��ł������e�����Љ�������B- ����
- ��ʓI�ɏ��q���Ɋւ��Ċ�Ƃ��O�Ɍ������ē�������������Ƃ����ꍇ�A�u�玙�x���v�ւ̎��g�݂��\���̂��镪��̂ЂƂƍl���Ă��܂��BSMFG���ł́A�O���[�v�e�Ђŏ]�ƈ��T�|�[�g�v���O�����Ƃ������̉��ɁA���x�̐�����i�߂Ă��܂����B��̓I�ɂ̓O���[�v�S�̂ň玙�x�Ɛ��x�A���x�ɐ��x�A�Z���ԋΖ����x�ȂǂɊւ��Ă͊��ɖ@�������铱�����s���Ă���A�܂���Ƃɂ���Ă͑����⋋���̎x���A�����E�o�Y���@�ɑސE�����Ј����Čٗp���鐧�x�Ȃǂ�����A�d���Ɖƒ�̗������x�������������i�߂Ă��܂��B
 ����Ŋ�ƊO�ɑ��ẮA��N�̉Ă��납����{�����u�r�l�a�b�v���{�m�v���W�F�N�g�v�ɂ����āA�玙�x�����s���R�̒c�̂ɑ��ē���m�o�n�@�l�Ƃ��Ă̔F��擾�Ɍ����������^�c��A��t���̊Ǘ��Ȃǂ̃A�h�o�C�X���s���܂����B����͌��ʓI�Ɉ玙�x�����s���Ă���g�D��c�̂��x������Ƃ����ւ����ɂȂ����Ă��܂��B��t��ʂ��āA�Г��̖�1��2�疼���Q������{�����e�B�A����Ŏ����I�Ȏx�����s���Ă��܂��B���̂悤�Ȋ����̎��т͂���Ȃ�����A����͊������\���ɑ̌n�����Ă��炸�A����̉ۑ肾�Ɗ����Ă��܂��B
����Ŋ�ƊO�ɑ��ẮA��N�̉Ă��납����{�����u�r�l�a�b�v���{�m�v���W�F�N�g�v�ɂ����āA�玙�x�����s���R�̒c�̂ɑ��ē���m�o�n�@�l�Ƃ��Ă̔F��擾�Ɍ����������^�c��A��t���̊Ǘ��Ȃǂ̃A�h�o�C�X���s���܂����B����͌��ʓI�Ɉ玙�x�����s���Ă���g�D��c�̂��x������Ƃ����ւ����ɂȂ����Ă��܂��B��t��ʂ��āA�Г��̖�1��2�疼���Q������{�����e�B�A����Ŏ����I�Ȏx�����s���Ă��܂��B���̂悤�Ȋ����̎��т͂���Ȃ�����A����͊������\���ɑ̌n�����Ă��炸�A����̉ۑ肾�Ɗ����Ă��܂��B
 ��q�̌Ǘ��ޒn��̖��
��q�̌Ǘ��ޒn��̖��
- ����
- �r�l�e�f���玙�x���ɑ��Ċ�ƊO�̊������ǂ̂悤�ɂ��Ă����ׂ����Ƃ����ۑ肪�������܂����B�ł́A�����Ƃ��Ĉ玙����芪�����ɂ͂ǂ̂悤�Ȗ�肪�N���Ă��āA�ۑ�ɂȂ��Ă���̂ł��傤���B
- ���V
 ���q�����Ə��q�Љ�ɂ�����q��Ă̖��͔��ɖ��ڂɊ֘A���Ă��܂��B���q���Ƃ͍��v����o�����ł�����2.1��������Ԃ��������邱�Ƃ��w���܂����A���̒��ł�1.5�������q���ƌĂ�ł��܂��B���{�̏o������2005�N�ɍŒ��1.26���L�^���A�������N��1.39���x�Ő��ڂ��Ă��܂��B���̂܂܂̏������ƁA����1.2�`1.3�Ő��ڂ��邾�낤�ƌ����Ă��܂��B�P�N�Ԃɐ��܂��q���̐��͑�ꎟ�x�r�[�u�[���̍��i1947�`49�j�ɔ�ׂ�40�����x�ɂ����܂���B
���q�����Ə��q�Љ�ɂ�����q��Ă̖��͔��ɖ��ڂɊ֘A���Ă��܂��B���q���Ƃ͍��v����o�����ł�����2.1��������Ԃ��������邱�Ƃ��w���܂����A���̒��ł�1.5�������q���ƌĂ�ł��܂��B���{�̏o������2005�N�ɍŒ��1.26���L�^���A�������N��1.39���x�Ő��ڂ��Ă��܂��B���̂܂܂̏������ƁA����1.2�`1.3�Ő��ڂ��邾�낤�ƌ����Ă��܂��B�P�N�Ԃɐ��܂��q���̐��͑�ꎟ�x�r�[�u�[���̍��i1947�`49�j�ɔ�ׂ�40�����x�ɂ����܂���B
�n�d�b�c�������ɂ����鍇�v����o�����Ə����J���͗��̊W�Ō���ƁA�����̏A�Ƃ��i��ł��鍑�łނ���o�����������Ƃ����f�[�^������܂��B�܂��A������{�ł͋}����15����64�̐��Y�N��l�����������Ă����A�����Ȃ�ƘJ���̒S���肪�s�����邱�ƂɂȂ�܂��B�l�������������J���͗��̉��݂ɂ�����20����40���炢�܂ł̏����̘J���͗����グ�邱�Ƃ��A���{�Љ�̉i�����Ɍ������܂���B����ƎႢ�����̔D�P�E���E�q��Ă𗼗������邱�Ƃ����傫�ȉۑ�ł��B
���q���̒��ړI�v���́A�������̏㏸�A�Ӎ����A�����������܂��B���̔w�i�ɂ͂��܂��܂ȗv�����l�����܂��B�A���P�[�g���ł͈玙�E����Ɋւ���o�ϓI���S���g�b�v�ɂ��܂����A���ꂪ�^�̖��Ȃ̂��ǂ����͔��f������A�ނ���q��Ċ��Ɋւ����肪�d�v�ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B�Ⴆ�ߔN�̎q���ƉƑ��̏ł́A���{�ɂ͐��E�ō������̕�q�ی���Ã��x�����������ŁA��o���̏d���̊����̑�����q���̋s�҂̌���������܂��B�s�Ҍ����́A1999�N�̂P���P�猏���瑝���𑱂��A2009�N��4��4�猏�A10�N��5��5�猏�A11�N��6�������Ă��܂��B�Љ�̕ω����A�q�������̐�����ω����������A�ƒ�E�n��̈玙�͂Ɗw�Z�̋���͂͒ቺ���A����Ɏq�����������łȂ��A�e�q�̐S�̖�肪���ɐ[���ȏŁA���ꂪ�s�҂ɂȂ����Ă��܂��B�q���̐S�ɉe�����鑽�l�Ȗ��̑����E�[���������݂̖��_���ƌ����܂��B
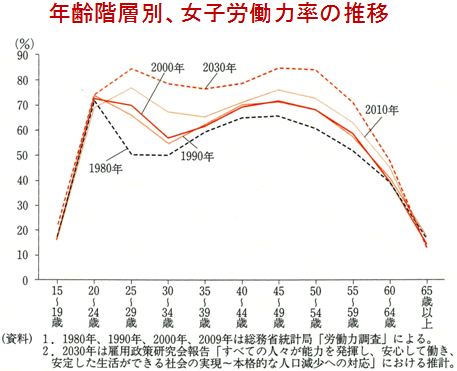
- �r�{
 ���c���Ɗw���ɕ����ď����������Ǝv���܂��B���c�����͋s�҂̑��������ɐ[���ŁA���̔w�i�ɕ�q�̌Ǘ�������܂��B��q���Ǘ����錴���̈�ɓ��{�̘J���̖�肪����A���{�ł͒����ԁi�T50���Ԉȏ�j�����Ă���l�̊����̏��Ȃ��łn�d�b�c36�J����35�ʁA�]�Ɏ��Ԃ̒�����36�J����35�ʂł��B�j���̉Ǝ��E�玙���Ԃ�1��59���ŁA����͂n�d�b�c����131���̔����ɂ������Ȃ������ł��B�j���̈玙�ւ̊֗^���ƂĂ��Ⴂ������܂��B������͒n��R�~���j�e�B�̊�������܂��B����ׂ͗ɒN���Z��ł��邩������Ȃ��Ƃ��A���X�̍��������Ƃ͂����R���r�j�ʼn�������ȂǁA�Љ�̕ω��������Đl�Əo��@������Ă��܂��A�Љ��̌Ǘ������q��Ă̑�ς��ɂȂ����Ă���ƍl�����܂��B�w���Ɋւ��Ă��q�����X�g���X������w�Z���̖\�͂������Ă��āA�����߁A�s�o�Z�����ƂȂ��Ă��܂��B�q���̃X�g���X�̌����͂Q����ƍl���Ă��܂��B��́A�V�тƂ����R�̌��ȂǁA�q�����{����ׂ������Љ�̕ω��ƂƂ��ɖ����Ȃ��Ă��Ă��āA�����I�ɂ������قƂ����q�����V�Ԏ{�݂������s���̂��߂ɕ�����Ă��܂��B�Ⴊ�ς����Ă��A�����Ⴎ����ɂȂ邩��Ƃ������R�ōZ��ŗV��ł͂����Ȃ��Ƃ����w�Z������܂��B�ߔN�K�v�������܂��Ă���w���ۈ�������s�����A�������̂�����̋c�_���[�܂��Ă��܂���B
���c���Ɗw���ɕ����ď����������Ǝv���܂��B���c�����͋s�҂̑��������ɐ[���ŁA���̔w�i�ɕ�q�̌Ǘ�������܂��B��q���Ǘ����錴���̈�ɓ��{�̘J���̖�肪����A���{�ł͒����ԁi�T50���Ԉȏ�j�����Ă���l�̊����̏��Ȃ��łn�d�b�c36�J����35�ʁA�]�Ɏ��Ԃ̒�����36�J����35�ʂł��B�j���̉Ǝ��E�玙���Ԃ�1��59���ŁA����͂n�d�b�c����131���̔����ɂ������Ȃ������ł��B�j���̈玙�ւ̊֗^���ƂĂ��Ⴂ������܂��B������͒n��R�~���j�e�B�̊�������܂��B����ׂ͗ɒN���Z��ł��邩������Ȃ��Ƃ��A���X�̍��������Ƃ͂����R���r�j�ʼn�������ȂǁA�Љ�̕ω��������Đl�Əo��@������Ă��܂��A�Љ��̌Ǘ������q��Ă̑�ς��ɂȂ����Ă���ƍl�����܂��B�w���Ɋւ��Ă��q�����X�g���X������w�Z���̖\�͂������Ă��āA�����߁A�s�o�Z�����ƂȂ��Ă��܂��B�q���̃X�g���X�̌����͂Q����ƍl���Ă��܂��B��́A�V�тƂ����R�̌��ȂǁA�q�����{����ׂ������Љ�̕ω��ƂƂ��ɖ����Ȃ��Ă��Ă��āA�����I�ɂ������قƂ����q�����V�Ԏ{�݂������s���̂��߂ɕ�����Ă��܂��B�Ⴊ�ς����Ă��A�����Ⴎ����ɂȂ邩��Ƃ������R�ōZ��ŗV��ł͂����Ȃ��Ƃ����w�Z������܂��B�ߔN�K�v�������܂��Ă���w���ۈ�������s�����A�������̂�����̋c�_���[�܂��Ă��܂���B
������͎q���������l�ԊW�̒��ɂ��邱�Ƃł��B�ڂ���̂��w�Z�̐搶���e���A�N���X�̗F�B���炢�ŁA�ٔN��̗F�B���l�ȂǁA���낢��ȉ��l�ς��������l�����Ɛڂ���@�����܂���B
���͂���������܂����A��Ԗ�肾�Ɗ����Ă���̂́A�q���̎��_�ł̋c�_�������Ă��āA�q���ɂ₳�����Ƃ������_���A�C�O�Ɣ�ׂē��{�ɂ͂قƂ�ǂȂ��Ƃ������Ƃł��B���A�ł͎q���̌���������Ă��邩���`�F�b�N����@�ւ�ݒu����ׂ����ƌ����Ă��āA�����̍��ł͎q���I���u�Y�}�����u����Ă��܂����A���{�ɂ͂���܂���B�C�O�ł͎q���ɂ₳�����X�Â���iChild Friendly Cities�j�ȂǁA���A�̎q���̌������̎��_�ɉ������c�_����������܂��B
���q���E�玙�x���Ƃ������ꍇ�A���[�N���C�t�o�����X�Ɋւ��Ă͕�e�����łȂ����e���܂߁A���c���������łȂ��w����܂őΏۂ��L���A�R�~���j�e�B�Â���ł͕�q�̌Ǘ����������q���̐l�ԊW��̌����L���邱�Ƃ��ۑ肾�ƍl���Ă��܂��B- ���R
 �q��ĂɊւ��Ă͑��q�o�Y���̕�e�̔N����ς�30���A���s�ł�33�̒n�������܂��B�����̂Ȃǐ��x��̃t�H�[�}���Ȏx���ƒn���R�~���j�e�B�̃C���t�H�[�}���Ȏx���̗��ʂŁA�Ӎ����Ȃǎ���w�i�ɑΉ������V���������A�q��Ẵ��f���������K�v������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�q��ĂɊւ��Ă͑��q�o�Y���̕�e�̔N����ς�30���A���s�ł�33�̒n�������܂��B�����̂Ȃǐ��x��̃t�H�[�}���Ȏx���ƒn���R�~���j�e�B�̃C���t�H�[�}���Ȏx���̗��ʂŁA�Ӎ����Ȃǎ���w�i�ɑΉ������V���������A�q��Ẵ��f���������K�v������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���l�̗�ł́A�����ȏ�̕�e���o�Y�O�ɏ������q���̐��b���������ƂȂ���e�ɂȂ��Ă��܂����A�����E�o�Y�ɂ͎q��Ă̌Ǘ����A���S��������܂��B���̔w�i�ɂ͎q��Ďx���{�݂����f�{�݂��ƌ����Ă���ȂǁA�q�������Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv�����炢�q���Ƀt�����h���[����Ȃ����̐��̒�������܂��B�q��ĉƒ�̌Ǘ��Ɋւ��Ă͔��R�Ƃ����s�����𑽂��̕�e�E���e�������Ă��܂��B�Ⴂ����͓]�o�����������A����ɒm�荇�������Ȃ�������A�V���O���}�U�[�ł͐e�����Ŏq�������܂���ĂĂ����ɂ͌��E������܂��̂ŁA��͂�n��Љ�q��Ă���������d�g�݂������Ă����K�v������܂��B���x��̘b�Ō����Γ��{�͏��O���ɔ�ׁA�f�c�o�ɑ��Ďq����q��ĉƒ�ւ̎x�o����߂銄�������ɏ��Ȃ��B���ꂪ�玙�{�݂̕s���⎿�̒ቺ�ɊW���Ă���ƍl�����܂��B��������������܂��Ďq��Ă����₷���n��Љ�ɂ��邽�߂ɂ͎q��Ďx��������m�o�n�̈琬���厖�ł��B���{�ɂ͉��ی��Ƃ�������Ҍ����̎d�g�݂͂����Ă��q�������ւ̎d�g�݂͂܂��܂��ア�̂�����ŁA2015�N�x�Ɍ����č��͐V�������x����낤�Ƃ��Ă��܂��B���ꂪ�e�n��ŋ@�\����d�g�݂ɂȂ�悤�Ɋ�Ƃ��܂߂Ďq��ĂɊւ�邠����l�����������ƎЉ�ɑ��Đ����o���Ă����ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���B
 ���Ɗ�Ƃ����͂��邱�Ƃň玙���͉����ɋ߂Â�
���Ɗ�Ƃ����͂��邱�Ƃň玙���͉����ɋ߂Â�
- ����
 ����܂ł̋c�_�ŏo�����̓X�E�F�[�f�����o�����Ă������ł��B�X�E�F�[�f���̏o�����͌o�ςƐ���̈����2011�N�ȍ~��1.9�Ő��ڂ��邾�낤�Ƃ������̌����ɂȂ��Ă��܂��B�X�E�F�[�f���ł����Ɏ���܂Œ������Ԃ�������܂������A��������������Ƃ��ē��{����]�����Ă�Ǝv���܂��B�d�t�ł��o�������Ⴂ���͕ۈ�{�݂̕s���ƁA�����̘J�����̒Ⴓ���W���Ă��܂��B�d�t�ł͏����̘J������70���ɂ��邱�Ƃ�ڕW�ɂ��Ă���A�o�����̍����k�������͊T�˂��̖ڕW��B�����Ă��܂��B�܂��A�ۈ牀�̓��������X�E�F�[�f���ł́A3�Ζ�����63���A3�Έȏオ94���ƍ����ł��B
����܂ł̋c�_�ŏo�����̓X�E�F�[�f�����o�����Ă������ł��B�X�E�F�[�f���̏o�����͌o�ςƐ���̈����2011�N�ȍ~��1.9�Ő��ڂ��邾�낤�Ƃ������̌����ɂȂ��Ă��܂��B�X�E�F�[�f���ł����Ɏ���܂Œ������Ԃ�������܂������A��������������Ƃ��ē��{����]�����Ă�Ǝv���܂��B�d�t�ł��o�������Ⴂ���͕ۈ�{�݂̕s���ƁA�����̘J�����̒Ⴓ���W���Ă��܂��B�d�t�ł͏����̘J������70���ɂ��邱�Ƃ�ڕW�ɂ��Ă���A�o�����̍����k�������͊T�˂��̖ڕW��B�����Ă��܂��B�܂��A�ۈ牀�̓��������X�E�F�[�f���ł́A3�Ζ�����63���A3�Έȏオ94���ƍ����ł��B
�X�E�F�[�f���ɂ����Ďq��Ă͏�����������̂Ƃ�������������܂������A���{���A���e�݂̂�����2�����̕��e�玙�x�ɂ����Ă���A�Љ�̈ӎ����ς��A��Ƃ����͓I�ɂȂ������ƂŒj���̈玙�Q�����������܂����B�܂��A�����̎Љ�i�o���}�����A�x�[�r�[�u�[�������������ߕۈ牀���s�����Ďq����a�����Ȃ�����������܂������A�����̂ɐӔC���������A�e���ۈ牀�ɓ��ꂽ���Ɛ\�����Ă���3�J���ȓ��ɏꏊ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ƃ����@�����ł������ƂŁA���ł͎��I�ɂ������x�̍����ۈ牀���K��������悤�ɂȂ��Ă��܂��B�܂��A���Ǝ����̂��e�q�̃l�b�g���[�N�Â�����x�����邱�Ƃŕ�q�̌Ǘ���h���ł��܂��B�܂��A�q�����a�C�ɂȂ����Ƃ��ɂ͋�����80����ۏႳ�����x�ɂ�N��120����邱�Ƃ��ł���̂������e�ɂƂ��ĂƂĂ��傫�ȈӖ��������܂��B
��Ƃ̓����Ƃ��Ă͂���30�N�ŃX�E�F�[�f����Ƃ̉Ƒ��ɑ���l�������傫���ς��܂����B�G�[���N�\���Ƃ����X�E�F�[�f���̑��Ƃ���삯�Ĉ玙�x�ƒ��ɎЉ�ی�����o�鋋����80���́A�c��20�����x�����t�@�~���[�|���V�[���f�������ƂŒj���̈玙�x�ɂ̎擾���i�݂܂����B�Ȃ����ƌ����A�ł��傫�ȃn�[�h���ł��������^���ۏႳ�ꂽ���Ƃ����łȂ��A�玙�x�ɂ�������j���͎d���̃}�l�W�����g�����ɂȂ��ċA���Ă�����A�Г��ɂ��玙�x�ɂ��������i��������ȂǂŊ�Ɠ��̕��͋C���玙���d������l�����ɏ������ω�����Ƃ����z�����܂ꂽ����ł��B
�������X�E�F�[�f���ł���肪�Ȃ��킯�ł͂���܂���B�����̃L�����A�u�����i��ł���A�o�Y�̍�����i��ł��ăX�g�b�N�z�����ł͑��q�̏o�Y��35���炢�ɂȂ��Ă��܂��B�������c�Ƃ��Ȃ��ȂǁA��Ƃ̓w�͂������č����{�������Ă��鏭�q�����A��q�̌Ǘ��A�c���̋s�҂Ȃǂ̓X�E�F�[�f���ł͂قƂ�Ǖ������Ƃ͂���܂���B- ����
- ���q������玙�x���͖���N�����ł������L���e�[�}���Ƃ������Ƃ��悭������܂����B�ȏ�̖���N���Ăr�l�e�f�̍l���������߂Ă����������������B
- �v��
 �M�d�Ȃ��ӌ��ƃV���b�L���O�Ȏ�����������������ϊ��ӂ��Ă��܂��B���q�����Ɋւ��Ă͐��{���x���ł����낢��ȋc�_������Ă��܂����A���{�łً͋}�x������[���x�������{��ɔ��f����Ă��Ȃ��Ɗ����Ă��܂��B�����̘J���̖͂��A���q���̖��͓��{�������I�ɔ��W���Ă������߂̉������ׂ��꒚�ڈ�Ԓn�̖��ł͂Ȃ��ł��傤���B�����g�A�C�M���X�Ŏq����7�N�Ԉ�Ă��o��������܂����A�C�M���X�͎q���ɑ�σt�����h���[�ł��B�j���[���[�N�ł���q���ɗD�����Љ�ɂȂ��Ă��܂��B���{�A�Ƃ��ɓ����ł͎q���ɔ��ɗ₽���B�Ȃ����{�͂��̂悤�ɂȂ��Ă��܂����̂��l���������܂��B
�M�d�Ȃ��ӌ��ƃV���b�L���O�Ȏ�����������������ϊ��ӂ��Ă��܂��B���q�����Ɋւ��Ă͐��{���x���ł����낢��ȋc�_������Ă��܂����A���{�łً͋}�x������[���x�������{��ɔ��f����Ă��Ȃ��Ɗ����Ă��܂��B�����̘J���̖͂��A���q���̖��͓��{�������I�ɔ��W���Ă������߂̉������ׂ��꒚�ڈ�Ԓn�̖��ł͂Ȃ��ł��傤���B�����g�A�C�M���X�Ŏq����7�N�Ԉ�Ă��o��������܂����A�C�M���X�͎q���ɑ�σt�����h���[�ł��B�j���[���[�N�ł���q���ɗD�����Љ�ɂȂ��Ă��܂��B���{�A�Ƃ��ɓ����ł͎q���ɔ��ɗ₽���B�Ȃ����{�͂��̂悤�ɂȂ��Ă��܂����̂��l���������܂��B
���̒��ŁA�r�l�e�f�Ƃ��ĉ����ł��邩�������ƍl�������Ă��܂����B�Г��ł͂��낢��Ȏ��g�݂����Ă��Ċ�ƂƂ��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ۑ���ꕔ�����Ă��Ă͂��܂����A����ΊO�I�ɁA���邢�͖{�Ƃ̒��łǂ̂悤�ɖ��Ɏ��g��ł�����̂��A���̓_�ɂ��Ă��ӌ��������ƍl���Ă��܂��B
 ��Ƃ����Љ�ւ̉e����
��Ƃ����Љ�ւ̉e����
- ����
- �ł́A�r�l�e�f����ƂƂ��āA���邢�͋��Z�@�ւƂ��Ă��̖��ɂǂ��ւ���Ă��������̂��ɂ��ċc�_���Ă��������Ǝv���܂��B��s����Ƃ��ăX�E�F�[�f���ł͂ǂ̂悤�ȗႪ����܂����H
- ����
- �q��Ė��Ɗ��̖��͎��Ă��āA��Ƃ̎��含�����ɔC���Ă͂Ȃ��Ȃ����܂������܂���B�傫�Șg�g�݂����鍑�⎩���̂ɉe���͂����āA��ƂƂ��Ă̖��ӎ��M���ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���B�X�E�F�[�f���ł���Ɠ��ɕۈ牀�����Ȃǂ̓���������܂����A���܂肤�܂������Ă��܂���B��Ƃ̖����Ƃ��Ă͊�Ր��������q���ɃX�|�[�c�̈琬���x�������肷��Ⴊ��������܂��B�{�Ƃ̒��ł͊�Ƃ̊��]���Ɠ����悤�ɁA�玙�x�̕]�����̂����铮�������Ă͂ǂ��ł��傤���B
- ����
- ��قǁA����N�̒��Œn��E�Љ�q���ɗ₽���̂ł͂Ȃ����Ƃ����ӌ�������܂����B
- ���R
- �t�@�~���[�t�����h���[�ȎЉ�ɂ��邽�߂ɑ��Ƃ̖����͔��ɏd�v���ƍl���Ă��܂��B�Ⴆ�Δ�s�@�ɏ��Ƃ��Ɏq���A�ꂪ�D�悳���͍̂��ۃX�^���_�[�h����Ƃ��擱�����Ⴞ�낤�Ǝv���܂��B�ł͋��Z�@�ւɂ͉����ł��邩�H�ƍl����ƁA�b�r�q�̈�Ŏ��Ђ̃t�@�~���[�|���V�[�����J������A��s�̗��p�҂̎��_�Ō���ƊO���Ђ̕���V���O���}�U�[�Ȃǂ������̏����̕��X�ɂ��v�搫������ΗZ�����₷������ȂǁA�Ƒ��̑��l���ɑΉ��ł����s�̂�������l������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�m�o�n�̗��ꂩ�炷��ƁA��Ƃ͎Љ�I�ɗǂ����������Ă��Ă����܂��A�s�[���ł��Ă��Ȃ��悤�Ɍ����܂��B�`���������������玙�x���c�̂ɑ���x���Ȃǂ��A�����ƐϋɓI�ɍs���āA�������ǂ�ǂ�J�����Ē��������Ǝv���܂��B
- ���V
- �����Ȉ�Ƃ����q���̑�َ҂̗���Ƃ��ẮA������S���q�������̈琬���Љ�S�̂������Ɛ^���ɍl���A�q���ƉƑ��̂��߂ɍ��⎩���́A��Ƃ͐ϋɓI�ȓ��������Ē��������Ǝv���܂��B�܂��A�Љ�S�̂Ŏq��Ă��x�����邱�Ƃ�ʂ��āA�s�҂����炵�Ă������Ƃ��K�v�ł��B��w�I���n���猾���A�����̐����K���a�̃��X�N�ɂȂ����̏d�o���͍���o�Y�Ɩ��炩�ɊW������܂��B�Ⴂ�N��Ō������邱�Ƃ��ł��A�L�����A�`���ƔD�P�E�o�Y�E�玙�𗼗��ł����Ƃ̓�������l���Ē��������Ǝv���܂��B
- �r�{
- ��Ƃ��ł��邱�ƂƂ��Ă�3����܂��B���ɁA�ۈ珊�s���Ɋւ��Ċ�Ƃ̑�Ƃ����ƁA������Ɠ��ۈ珊�Ƃ����b�ɂȂ�܂����A�ނ���q���̗���ōl����ƒʋ͕��S�Ȃ̂ŁA�ŋ߂͊�Ƃ̕s���Y�����p���Ă��̒n��̂��߂̕ۈ�{�݂����铮��������܂��B���Ƃ��Ɗ�Ɠ��ۈ珊�ɂ��悤�Ƃ��Ă����Ƃ����F�肱�ǂ����Ƃ��Ēn��ɂ��J��������Ђ�����܂����B2�ڂ͂m�o�n�̎x���ł��B�����ʂŎx��������A�m�o�n�͎������ł������Ă���̂ŁA�X�y�[�X��݂������ł��x���ɂȂ�܂��B��Ђ̎������̈�p���Ј��̃{�����e�B�A�����ɊJ�����āA���̎Ј��̃{�����e�B�A��������Ђ̎Љ�v�������Ƃ��ăA�s�[�����Ă����Ƃ�����܂����B3�ڂ́A�m�o�n�̃j�[�Y�Ɗ�Ƃ��v���ł��邱�Ƃ��}�b�`���O����@�\�ł��B�C�M���X�ł͊w�Z�Ɗ�Ƃ��Ȃ��@�ւ��n��ɂ���܂��B���Z�@�ւ������̊�ƂƐړ_�����郁���b�g���������āA��Ƃ��q��Ďx���⋳��̌���ɂȂ��R�[�f�B�l�[�g�g�D�̂悤�ȋ@�\�����Ă�ƁA�n��⋳�猻��ɂƂ��đ�Ϗ����鑶�݂ɂȂ�܂��B
���̂ق��A��s�Ƃ��Ă͈玙�x���ɐϋɓI�Ȋ�Ƃ��L���ɂȂ�悤�Ȏs�����A�^�p�v�̈ꕔ�������{��{�݂�n���ƒ�Ȃǎq���E�q��Ďx���Ɏg�����Z���i�̊J���Ȃǂ��l�����܂��B�܂��A�ۈ��q��Ďx���Ɋւ���r�W�l�X��������Ȃ��A���̂悤�ȎY�Ƃ̌��S�Ȉ琬�̊ϓ_�ŁA�{�Ƃ�ʂ��Ċ�Ƃ̎��̕�����]���ł���悤�Ȏd�g�݂�����Ƃ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���q�����͎����\�ȎЉ������Ƃ����Ӗ��ŁA�����ł�����ƍl���Ă��܂��B��ƂƂ��Ă̑Ή����A�����ɑ����@�����p�ł���Ǝv���܂��B - ����
- �r�l�e�f�͂��������f���炵�����������Ă���̂ł����A�ЊO�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�������ア��ۂ�����܂��B�Ⴆ�ΐ�i��ƂŃO���[�v�������ċ�����PR���s������A���邢�́A�m�o�n�ƈꏏ�ɃI�s�j�I�����`�����Ă����Ȃǂ̊������ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
- ���R
- �I�s�j�I���̌`���ւ̊�Ƃ̊ւ����Ƃ��āA���q�����ɂ��Ă̖��ӎ���A�������Ă�����e�A���ꂩ��ڎw���Ă��������Љ�ւ̃R�~�b�g�����g�������Ē�����ƂƂĂ��e���͂��傫���Ǝv���܂��B

 ���ӎ����������ɂ��Ĉ玙�x���Ɏ�g��ł���
���ӎ����������ɂ��Ĉ玙�x���Ɏ�g��ł���
- �v��
- �m���ɂr�l�e�f�ōs���Ă��邳�܂��܂Ȏ�g�݂ɂ��ẮA���܂��Љ�ɔ��M�ł��Ă��Ȃ��\��������܂��B��s�A�����ċ��Z�O���[�v�̎Љ�ɑ���e���͂Ƃ������̂��l����ASMFG���玙�x���ɐϋɓI�ɂȂ��Ă������ƂŐ��Ԃɂ����e����^���邱�Ƃ��\�ɂȂ�Ǝv���܂��BSMFG�̂b�r�q�ɂ����āA�����ւ̎�g�݂͔��ɑ傫�ȃe�[�}�̈�ŁA��Ƃ̊��ւ̔z���x���������Ă��ėZ�����������߂�Ƃ������i�́A�Љ�I�ɂ��]�����Ă��܂��B����Ɣ�ׂ�Ə��q���E�玙�x���ɂ��Ă͂܂��܂����g�݂�����Ă��Ȃ����Ƃ��������Ă��܂��B��قǁA�q��Ė��Ɗ����͎��Ă���Ƃ̂��w�E������܂������A�O���[�v�̒��ł��܂���s�Ƃ��ă\�t�g�ʂ��܂߂Ăł��邱�Ƃ��瑁�}�ɒ��肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɗ����Ă��܂��B�o�c�w�̒��ł����q�����ɂ��Ă͋������ӎ��������Ă���̂ł����A����ŎГ��ɂ����Ė��ӎ������L�������������Ă���Ƃ���ł��B���[�N���C�t�o�����X�ȂǎГ��̐��x�͍��܂������A���x���g�������C�����悭�g����ɂ��邩�ƌ����ΕK�����������Ȃ��Ă��Ȃ���������܂���B�Г��̖��ӎ��̋��L��i�߁A�������ӌ�����ł���ł���̓I�ɓ������ĎЊO�ɔ��M���Ă��������Ǝv���܂��B
- ����
- �{���͂��܂��܂Ȋϓ_����M�d�Ȃ��ӌ��A�����܂��Ƃɂ��肪�Ƃ��������܂����B�L���҂̊F���܂���͏��i�E�T�[�r�X�̊J���A���̒��ւ̔��M�A�����ւ̐Z���ȂǍL���͈͂ɂ킽���đ傫�ȏh����܂����B�r�l�e�f�����q�����Ƃ����傫�ȎЉ�ۑ�ɍv���ł���悤�A��g��ł������ӂ�V���ɂ������܂����B