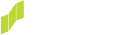�T�X�e�i�r���e�B
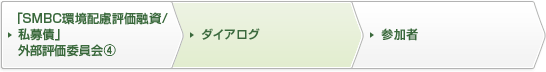
 �T�D SMBC�����g�ފ��r�W�l�X�̕������ɂ���
�T�D SMBC�����g�ފ��r�W�l�X�̕������ɂ���
�@�@�`ESG��g�E���J���i�����j�̓����܂��`
��������
- ����
 �{���̊O���]���ψ���̋c��ɂȂ��Ă���܂�SMBC���z���]���Z����5�N�O�ɊJ���������i�ł��B�O���ψ���͔N1��̊J�Âł����A���̊��z���]���Z���̊C�O�W�J��A�V����ESG�]���̓����ȂǁA���N���܂��܂ȃA�C�f�A�Ղ��A���ۂ̎��g�݂ɔ��f���Ă��܂����B�{�������Њ��݂Ȃ����ӌ���������������������Ǝv���܂��B��낵�����肢�������܂��B
�{���̊O���]���ψ���̋c��ɂȂ��Ă���܂�SMBC���z���]���Z����5�N�O�ɊJ���������i�ł��B�O���ψ���͔N1��̊J�Âł����A���̊��z���]���Z���̊C�O�W�J��A�V����ESG�]���̓����ȂǁA���N���܂��܂ȃA�C�f�A�Ղ��A���ۂ̎��g�݂ɔ��f���Ă��܂����B�{�������Њ��݂Ȃ����ӌ���������������������Ǝv���܂��B��낵�����肢�������܂��B
����܂ł̎�舵����
- �i��
- �ŏ��ɁuSMBC���z���]���Z��/����v��2012�N�x�̏ɂ��āA���������肢���܂��B
- ����
- 2008�N10���ɁuSMBC���z���]���Z���v�̎�舵�����J�n�������܂��āA���̌�A������Ƃ̂��q���܂ɂ����p���₷���悤���肵���uSMBC���z���]���Z�� eco�o�����[up�v�A�����̊����\��ϐk���\��]������uSMBC�T�X�e�C�i�u�� �r���f�B���O�]���Z���v�A�����č��N4�����uSMBC�T�X�e�C�i�r���e�B�]���Z���v��lj����A���i���C���i�b�v���g�[���Ă��܂����B����ɁA�H�̈��S�ւ̎��g�݂�]������uSMBC�H�E�_�]���Z���v�A�V�ЂȂǗL���ɂ������Ƃ̎��ƌp���ւ̑Ή���]������uSMBC���ƌp���]���Z���v�A���Ȃɂ��u���q�⋋���x�v�ȂǁA������ȊO��������ƁA�]���^�������B�̃X�L�[�����g�������̂͌���7���i����܂��B2008�N10������2013�N3���܂ł̎�舵�������͗v��298���A7,644���~�B���̂������z���]���Z���̎�舵����145���A4,742���~�ɂ̂ڂ�܂��B�ŋ߂ł́A�e����z���]���Z���������p���������Ă������q���܂��A���Ђ̎��g�݂̐i�����q�ϓI�Ɋm�F���邽�߁A�ēx�����p�����Ƃ����P�[�X���������Ă��܂��B��N�x�́A81����15�������s�[�^�[�ɂ����̂ł����B
2013�N�x����̐V���Ȏ��g��
- ����
 �uSMBC�T�X�e�C�i�r���e�B�]���Z���v�́A�ߋ��̊O���ψ���Œ������ӌ����A�J���������̂ł��B����܂Ŏ��g��ł������z���]���Z���̃X�L�[�������p���Ȃ���A�]�����ڂƂ��āA���A�Љ�A�K�o�i���X�Ƃ���ESG�̎��_��lj����܂����B����ɁA���g�݂��̂��̂����łȂ��A���J���̏��]�������Ă��������Ƃ����̂��傫�ȓ����ɂȂ��Ă��܂��B
�uSMBC�T�X�e�C�i�r���e�B�]���Z���v�́A�ߋ��̊O���ψ���Œ������ӌ����A�J���������̂ł��B����܂Ŏ��g��ł������z���]���Z���̃X�L�[�������p���Ȃ���A�]�����ڂƂ��āA���A�Љ�A�K�o�i���X�Ƃ���ESG�̎��_��lj����܂����B����ɁA���g�݂��̂��̂����łȂ��A���J���̏��]�������Ă��������Ƃ����̂��傫�ȓ����ɂȂ��Ă��܂��B
��������̊J���Ɋւ��铮��
- �i��
- �����A��Ə��J���̐V��������Ƃ��ē��������ڂ��W�߂Ă��܂��ˁB
- �s����
 ���Ă̊�ƕ́A�������\�Ȃǂ̏���Ŋ������Ă��܂����B�������A���ꂾ���Ŋ�Ɖ��l�Ⓤ�����l�f����͓̂���Ȃ�A�����ȊO�̏��A����������������悤�ɂȂ��Ă��܂����B���Ƃ��A���[���b�p�ł�2003�N�̉�v�@���㉻�w�߂Ŕ�������̊J�����v������A����27�J�����ׂĂɂ����Ă��̍����@�����������܂����B�܂��A�A�����J�ł́A2009�N�Ƀj���[���[�N�،��������ESG�𒆐S�Ƃ����Ə��𓊎��Ƃɒ��邱�Ƃ\�����ق��A�i�X�_�b�N�iNASDAQ�j��ESG���̊J����ϋɓI�ɐi�߂�����œ����Ă��܂��B�������������͐�i�������łȂ��A������u���W���Ȃǂł�����Ƃ��Đi��ł��܂��B����A���{�ł́A1,000�Јȏ�̉�Ђ�CSR����������쐬���Ă��܂����A���̐���5�N�ԂقƂ�Ǖς���Ă��܂���B�������A�C�O�̓����Ƃ̓������ł��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł��B
���Ă̊�ƕ́A�������\�Ȃǂ̏���Ŋ������Ă��܂����B�������A���ꂾ���Ŋ�Ɖ��l�Ⓤ�����l�f����͓̂���Ȃ�A�����ȊO�̏��A����������������悤�ɂȂ��Ă��܂����B���Ƃ��A���[���b�p�ł�2003�N�̉�v�@���㉻�w�߂Ŕ�������̊J�����v������A����27�J�����ׂĂɂ����Ă��̍����@�����������܂����B�܂��A�A�����J�ł́A2009�N�Ƀj���[���[�N�،��������ESG�𒆐S�Ƃ����Ə��𓊎��Ƃɒ��邱�Ƃ\�����ق��A�i�X�_�b�N�iNASDAQ�j��ESG���̊J����ϋɓI�ɐi�߂�����œ����Ă��܂��B�������������͐�i�������łȂ��A������u���W���Ȃǂł�����Ƃ��Đi��ł��܂��B����A���{�ł́A1,000�Јȏ�̉�Ђ�CSR����������쐬���Ă��܂����A���̐���5�N�ԂقƂ�Ǖς���Ă��܂���B�������A�C�O�̓����Ƃ̓������ł��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł��B
���A��ƕ́A����ɐV�����X�e�b�v�Ɉڂ��Ă������Ƃ��Ă��܂��BESG�̏d�v�������܂�Ɠ����ɁA�C���^�[�l�b�g�Ȃǃ��f�B�A�����W�������ƂŁA�������A��������Ɍ��炸���܂��܂Ȋ�Ə���̒��ɂ��ӂ��悤�ɂȂ�܂����B�K�v�ȏ��������o�����Ƃ�����Ȃ������ʁA���������߂���悤�ɂȂ�܂����B�����Ƃ́A�������Ɣ�������̂��ꂼ��d�v�ȕ�����p���āA��Ƃ̐헪�Ɍ��т��A�����I�ɒZ���E�����E�����̊�Ɖ��l�����߂Ă������߂̕ł��B���̂悤�Ɋ�Ƃ������I�ȕ������������w�i�ɂ́A���[�}���V���b�N�ȍ~�A�������Z���w���ɗ���Ă���̂�������Ӗ�����������܂��B
������Z���ɍL����ESG�]��
- �r�䎁
 �������Ɣ�������̊J���́A�ӔC�����ɂ��ւ����̂ł��B�u�Љ�I�ӔC�����v�Ɏn�܂�A�u�����\�ȓ����v�uESG�����v�ƁA���͎̂���ƂƂ��ɕω����Ă��܂������A�ӔC�����̊T�O��1920�N�ォ�瑶�݂��܂��B���̒������j���l�����Ă��A�ӔC����������Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ��킩��ł��傤�B��Ƃ͎Љ�̒��ɂ���A����҂��s�A�����ƂȂǂƂƂ��ɑ��݂��܂��B����������A�ނ�ɐM�����Ă����Ȃ��ƁA��Ƃ͐��藧���܂���B
�������Ɣ�������̊J���́A�ӔC�����ɂ��ւ����̂ł��B�u�Љ�I�ӔC�����v�Ɏn�܂�A�u�����\�ȓ����v�uESG�����v�ƁA���͎̂���ƂƂ��ɕω����Ă��܂������A�ӔC�����̊T�O��1920�N�ォ�瑶�݂��܂��B���̒������j���l�����Ă��A�ӔC����������Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ��킩��ł��傤�B��Ƃ͎Љ�̒��ɂ���A����҂��s�A�����ƂȂǂƂƂ��ɑ��݂��܂��B����������A�ނ�ɐM�����Ă����Ȃ��ƁA��Ƃ͐��藧���܂���B
����́A��ɎЉ�̖ڂɂ��炳��Ă��邱�Ƃ��Ӗ����܂��B�Љ��Ƃ�����ڂ����A�ӔC�����̎��_�Ȃ̂ł��B���A���E�̃R���Z���T�X�Ƃ��āA��������AESG����ڂ���Ă���A���������ϓ_���瓊�����s����悤�ɂȂ��Ă��܂��B���̏�������SIF�Ɠ��l�̑g�D���e���ɂ���A���N1���ɐӔC�����Ɋւ���e���̓��v�f�[�^�������Ŏ��܂Ƃ߂����\���܂����B����ɂ��ƁA���N�A���E�Ŏ��{���ꂽ�ӔC������1,356���~�ɒB���܂����B�ӔC�������^�p��ЂȂǂɂ���ĉ^�p�����S���Z���Y�ɐ�߂�V�F�A�́A���[���b�p�ł�49���A�A�����J12���A��A�t���J35���B����ɑ��ē��{��0.2���Ƃ����c�O�ȏł��B����ɁA�ӔC��������@�ʂɕ��͂���ƁAESG���ƍ������𑍍����ē������f���s���u�C���e�O���[�V�����v�ɕ��ނ������̂͑S�̂�46���ł����B���̐����������Ӗ����Ă���̂��A���{�ł��\���ɍl���Ă����K�v������Ǝv���܂��B- �y�c��
- ���N5���A�O���[�o���E���|�[�e�B���O�E�C�j�V�A�e�B�u�iGRI�j�̍��ۉ�c�ɂ����āAESG���������ɊJ�����ׂ����������u�T�X�e�i�r���e�B�E���|�[�e�B���O�E�K�C�h���C���v�̑�l�ł����\����܂����B���ۉ�c���J���ꂽ�A���X�e���_���ɂ́A������u���W�����瑽���̏o�Ȏ҂��K��A��������̊J���ɑ��钍�ړx�̍�����������������܂����B���E�Ŕ�������̊J�����i�ޔw�i�ɂ́A���ۓI�Șg�g�݁A�e�����{�̋K���A�،�������ɂ��v���ȂǁA���܂��܂ȗv��������܂��B�������A���̓��{�ɂ͂ǂ̃h���C�u���Ȃ��悤�ȏŁA�e��Ƃ̎��含�Ɉς˂��Ă���C�����܂��B���̂悤�ȍ����̏ɂ����āA�����Z���h���C�r���O�t�H�[�X�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ɗ��҂��Ă��܂��B
- ���B
- ���݁A��K�͂ȃv���W�F�N�g�֘A�Z���ň��̊��E�Љ�z���������Ƃ���u�G�N�G�[�^�[�����v�ɂ�78���̋��Z�@�ւ��������Ă���A�Z���ɂ����Ă����z�������߂铮���͐��E�I�ɐi��ł��܂��B�܂��A�[���Ȋ������������N������Ƃɑ��ċ�s���Z���ł��Ȃ��悤�K�����钆���̂悤�ȍ�������܂��B���������K���ɉ����A��s�ɂ́A���X�N�Ǘ��̎��_������ւ̔z�������߂��邱�Ƃ�����܂��B�킩��₷���Ⴊ�y�뉘���ł��B�y�뉘���ɂ���ēy�n�̒S�ۉ��l���ʑ�������s�ɂƂ��Ă�����ł���A��s�͑��������Ɏ��g��ł��܂����B��s���S�����������Ƃœy�뉘���i�Ƃ����o�܂�����A�����X�N�ւ̔z������s�ɋ��߂鐢�̒�����̃v���b�V���[������܂��B
- �i��
- ���Z�@�ւł�ESG�]����i�߂�C���Z���e�B�u�������Ă���悤�ł����A��Ƒ��ł͂������ł��傤�B
- �y�c��
 �����̊�Ƃł́AESG�ȂǂɎ��g��CSR����ƗZ�����傪�܂��������蓝������Ă��Ȃ��̂�����ł��BESG�ւ̎��g�݂́A�Z���邽�߂Ƃ������A�����I�ȃp�t�H�[�}���X�̉��P�A��Ƃ̃u�����h���l�̌����ړI�Ƃ��Đi�߂��Ă��܂��B�ӔC������CDP�i�J�[�{����f�B�X�N���[�W���[��v���W�F�N�g�j��ʂ��āAESG�ƗZ���������Ɍ��ѕt���Ă������A���ꂪ�d�v�ȃ|�C���g�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�����̊�Ƃł́AESG�ȂǂɎ��g��CSR����ƗZ�����傪�܂��������蓝������Ă��Ȃ��̂�����ł��BESG�ւ̎��g�݂́A�Z���邽�߂Ƃ������A�����I�ȃp�t�H�[�}���X�̉��P�A��Ƃ̃u�����h���l�̌����ړI�Ƃ��Đi�߂��Ă��܂��B�ӔC������CDP�i�J�[�{����f�B�X�N���[�W���[��v���W�F�N�g�j��ʂ��āAESG�ƗZ���������Ɍ��ѕt���Ă������A���ꂪ�d�v�ȃ|�C���g�ɂȂ�Ǝv���܂��B- �r�䎁
- �����ł��Z���ł��A�ߋ��̍�������ł͓K�Ȕ��f���ł��܂���B�����Ƃ��Z�������������͂�����ӎ����Ȃ��܂܁A��Ƃ̃|���V�[��̐���m�邽�߁A������������Ă���̂��Ǝv���܂��B��Ƃ������I�ɂǂ̂悤�ȏ��i�Ɏ��g��ł����̂��B�ǂ̂悤�ɊC�O�헪��i�߂Ă����̂��B�����āA�ǂ̂悤�Ɋ�Ɖ��l�����߂Ă����̂��B�����������ɔ������傫���ւ��̂ł��B��������́A�����̊�Ɖ��l�𑪂���̂����Ƃ�����ł��傤�B
 �U.�V���i�uSMBC�T�X�e�C�i�r���e�B�]���Z���v�ɂ���
�U.�V���i�uSMBC�T�X�e�C�i�r���e�B�]���Z���v�ɂ���
���]���Z���𖣗͂��鏤�i�ɂ��邽�߂�
- �i��
- �V���Ƀ����[�X���ꂽ�uSMBC�T�X�e�C�i�r���e�B�]���Z���v���Z�����ƂɂƂ��Ė𗧂��i�ƂȂ�ɂ́A�ǂ̂悤�ȕ]�����ځE���@���K�v�ɂȂ�Ǝv���܂����B
- �r�䎁
- ����̗���ƂƂ��ɕ]���̎��_�͂ǂ�ǂ�ω����Ă����̂ŁA�K�v�ɉ����ĕ]�����ڂȂǂ����肵�Ă������Ƃ��K�v�ł��B���AIIRC�i���ۓ����]�c��j�̋c�_�ł��AGRI�̃K�C�h���C���ł����ڂ���Ă���̂́A�u�}�e���A���e�B�v�ł��B�}�e���A���e�B�Ƃ́A�����A�����Ȃǂɏd�v�ȉe�����y�ڂ��v���̂��Ƃ��w���܂��B�ԗ��I�Ɏ��g�ނ̂ł͂Ȃ��A��ƂɂƂ��ĉ����d�v�����܂��l���Ȃ���Ȃ�܂���B�e��Ƃ̃}�e���A���e�B�m�ɂ����]�������߂��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
- �s����
- �����ɂ�����}�e���A���e�B�́A�����Ƃ���Z�@�ւ���Ƃ̒����I�ȉ��l�n���\�͂�]������ɂ������ďd�v�ȏ��̎��_�ɗ��������̂ł��B�����O��Ƀ}�l�W�����g�����f���܂��B
- �y�c��
- ��I�ȕ]���͂�����x�K�v���Ǝv���̂ł����A�[����[�܂ŊJ�������莖�Ɠ����ɍ��킹�ďd�v�ȗv�f���i��A���̕����[�߂Ă������Ƃ��A�厖�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�܂��AESG�ŗD��Ă��邾���łȂ��A���ꂪ�����Ƀr�W�l�X�p�t�H�[�}���X�ɍv�����Ă��邩�Ƃ������_���K�v�ł��傤�B���g�݂���������̂��߂ɂȂ��Ă��Ă���Ƃ̂��߂ɂȂ��Ă��Ȃ���A�����Ƃ���Z�@�ւɂ͋^��̗]�n���c��܂��BESG�ƃr�W�l�X�������ɘA�����Ă��邩�A�����Ȃ��CSV�iCreating Shared Value�j��]������ׂ��ł��B�r�W�l�X�Ƃ̃C���e�O���[�V�����́A��Ƃ̑������ė~�����Ƃ��낾�Ǝv���܂��B
- ���B
 �}�e���A���e�B�Ȃǂ̂��b�����������āA��s�̐V���Ȗ��������ɕ�����ł����悤�Ɏv���܂��B����͗Z����ɑ���s��ESG�̊ϓ_����G���Q�[�W�����g(��������)���s�����Ƃł��B���Ƃ��A�u��Ђ̃}�e���A���e�B�͂��̓_�ɂ���܂��v�ƁA��s�����Ă��Ă����B���q���܂̒��ɂ́A�u���Ђŏ\���ȕ��͂����Ă��邩��w�E�͕K�v�Ȃ��v�Ƃ���������Ƃ����邩�Ǝv���܂����A�����������g�݂��V�����C�Â��ނ��ƂɂȂ邩������܂���B
�}�e���A���e�B�Ȃǂ̂��b�����������āA��s�̐V���Ȗ��������ɕ�����ł����悤�Ɏv���܂��B����͗Z����ɑ���s��ESG�̊ϓ_����G���Q�[�W�����g(��������)���s�����Ƃł��B���Ƃ��A�u��Ђ̃}�e���A���e�B�͂��̓_�ɂ���܂��v�ƁA��s�����Ă��Ă����B���q���܂̒��ɂ́A�u���Ђŏ\���ȕ��͂����Ă��邩��w�E�͕K�v�Ȃ��v�Ƃ���������Ƃ����邩�Ǝv���܂����A�����������g�݂��V�����C�Â��ނ��ƂɂȂ邩������܂���B- �y�c��
- ���z���]���Z����2�x3�x�Ɨ��p���Ă����Ƃ̒��ɂ́A�����I�ȕ]�������łȂ��A���ЂɂƂ��Ẵ}�e���A���e�B���@�艺�������Ƃ����j�[�Y�����邩������܂���ˁB���Z�@�ւ��O���̃X�e�[�N�z���_�[�̐����ق���悤�Ȍ`�Ńt�B�[�h�o�b�N���s���A��Ƃ����g�݂��p�����Ă����C���Z���e�B�u�ɂ��Ȃ邵�A���x���A�b�v�Ɍ��ѕt������Ǝv���܂��B���������|�W�e�B�u�X�p�C��������������A���݂��̐M�������������̂ɂȂ�͂��ł��B
������Ƃ����ʓI�Ɏx�����邽�߂�
- �i��
- ���]���Z���y�����邽�߂ɕK�v�Ȃ��Ƃ͉��ł��傤���B
- �r�䎁
- �����Ȋ�Ƃł��A�D�ꂽ���g�݂��s���Ă���Ƃ��낪����̂ŁA������ǂ̂悤�ɕ]�����Ă��������ۑ�ɂȂ�Ǝv���܂��B������ƌ����̊��}�l�W�����g�V�X�e���Ƃ��ẮA���Ȃɂ��G�R�A�N�V����21�▯�Ԏ哱�̃G�R�X�e�[�W�Ȃǂ�����܂����A�������������̘g�g�݂����p������A���邢�͒n����s�ƘA�g������A���g�݂��L���Ă������������ł��ˁB
- �y�c��
- CDP���͂��߁A��Ɖ��l�𑪂�w�W�͂��łɑ������݂��܂��B����ɁA���ꂼ��̎w�W�͒���I�ɓ��e����������A���������ύX�ɑΉ����Ă������Ƃ����߂��܂��BCSR�̒S���҂ł���Έ�ʂ藝���ł���Ǝv���܂����A�ʂ����Čo�c�w�A��������͂ǂ����Ƃ����ƁA�w�W���������G�������ۂ͔ۂ߂܂���B�����̊�ƂɊ��z���]���Z���Ɏ��g��ł��炤�ɂ́A�Ȃ�ׂ������̍��ۊ�ȂǂɓK�������A�G���g���[���x���������邱�Ƃ��K�v�ł��傤�B
- �s����
 ������Ƃɑ��ẮA���ԓI��ESG�̕]�������Ă��A���܂�Ӗ����Ȃ��Ɗ����Ă��܂��BESG�̎w�W���g���āA�ǂ�����Ċ�Ɖ��l�̌���A���邢�̓��X�N������������Ă������A���R�ȍ앶�����Ă��炤�̂���1�̕��@�ł͂Ȃ��ł��傤���B��������A�����Ɍ�������ǂ������Ă��邵�A�o�c�헪�𗧂Ă邱�Ƃ��ł���͂��ł��B
������Ƃɑ��ẮA���ԓI��ESG�̕]�������Ă��A���܂�Ӗ����Ȃ��Ɗ����Ă��܂��BESG�̎w�W���g���āA�ǂ�����Ċ�Ɖ��l�̌���A���邢�̓��X�N������������Ă������A���R�ȍ앶�����Ă��炤�̂���1�̕��@�ł͂Ȃ��ł��傤���B��������A�����Ɍ�������ǂ������Ă��邵�A�o�c�헪�𗧂Ă邱�Ƃ��ł���͂��ł��B
 ������
������
�L���҂���̃R�����g
- �r�䎁
- �ŋ߁A�C���p�N�g�C���x�X�g�����g�̍������{�ő傫�ȐL�т������Ă��܂��B�S���W�߂�w�i�Ƃ��āA�O���Ăł��邱�Ƃ�A���s�̂̊i�t����AAA�ł��邱�ƂȂǁA���܂��܂ȗv�����l�����܂����A�����̎g�r�����m�Ȃ��Ƃ��d�v�ȗ��R��1�ł��B���Ƃ��A���E���̃��N�`�������Ȃ��l�����̂��߂Ɏg���B���邢�́A�A�t���J�̋���̂��߂Ɏg���B�����Ƃ͎��������̂������ǂ̂悤�Ɏg����̂����ӎ����Ă���̂ł��B�]���^�̎������B�ɂ́A���������̂������ǂ̂悤�Ɏg���Ă��邩�A��s���ǂ̂悤�Ȋ�Ƃ��������Ă���̂��A�a���҂ɂ��킩��Ƃ��������b�g������܂��B��ʂ̏���҂ɂ��A�s�[�����銈���������Ƃ悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
- �s����
- �T�X�e�C�i�r���e�B�Ɋւ���Z���́A��Ƃ��������Ĉ���I�ɐ������Ă������߂ɕs���Ȃ��̂ł���A�s��o�σ��J�j�Y���������悤�Ǝ��g�ވ��{�����̐���ɂ����v���܂��B���{���܂߁A�X�e�[�N�z���_�[���ׂĂ��������݁A���{�̌o�ς��悭��������i�߂Ă������������Ǝv���܂��B����ɁA���̐����X�L�[�����C�O�ւ��W�J����A���E�����݂�ȃn�b�s�[�ɂȂ�܂��ˁB������������郊�[�h���Ƃ��āASMBC�̕]���^�������B������ɍL�߂Ă������������Ǝv���܂��B
- �y�c��
 ��s�̊��z���]���Z���̎�舵�������͒����ɑ������Ă�����̂́A�Z���S�̂���݂�ƁA�܂��{���I�ȉe���͂�����Ƃ�����i�K�ł͂���܂���B���ЂƂ����[���b�p��49�����z���鐅����ڎw���ė~�����ł��ˁB�e�������ɂȂ�Ȃ��悤�C�����邱�Ƃ��K�v�ł����A��̓I�Ȑ��l�ڕW��ݒ肵�Ĕ䗦�������ƍ��߂Ă������������Ǝv���܂��B�r�䂳���ʂ̏���҂ւ̃A�s�[���Ƃ�����Ă�����܂������A���Ƃ��Ί��z���]���Z���̔䗦��50���ɂȂ�ΖڂɌ����鐬�ʂɂȂ�Ǝv���܂��B���������F�����L�܂�A��s�̃R�[�|���[�g�J���[�̂悤�ɁA�g�̋�s�h�ɂȂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
��s�̊��z���]���Z���̎�舵�������͒����ɑ������Ă�����̂́A�Z���S�̂���݂�ƁA�܂��{���I�ȉe���͂�����Ƃ�����i�K�ł͂���܂���B���ЂƂ����[���b�p��49�����z���鐅����ڎw���ė~�����ł��ˁB�e�������ɂȂ�Ȃ��悤�C�����邱�Ƃ��K�v�ł����A��̓I�Ȑ��l�ڕW��ݒ肵�Ĕ䗦�������ƍ��߂Ă������������Ǝv���܂��B�r�䂳���ʂ̏���҂ւ̃A�s�[���Ƃ�����Ă�����܂������A���Ƃ��Ί��z���]���Z���̔䗦��50���ɂȂ�ΖڂɌ����鐬�ʂɂȂ�Ǝv���܂��B���������F�����L�܂�A��s�̃R�[�|���[�g�J���[�̂悤�ɁA�g�̋�s�h�ɂȂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
����̊O���]���ψ������
- ����
 ���Z�@�ւƂ��Ă̋@�\���ő���ɔ������Ȃ���A�{�Ƃ�ʂ��ĎЉ�I�ӔC���ʂ����Ă����B���ꂪCSR�Ƃ������̖̂{������ׂ��p���Ǝv���܂��B���������l���̂��ƁA���s�͊��z���]���Z���ɒ��͂��Ă��܂����B�{���̊O���]���ψ���ł́A������I�Ȏ��g�݂����q���܂̖{�Ƃɖ��ڂɊW���Ă��Ă��邱�ƁA�����̃X�e�[�N�z���_�[�ւ̓K�ȏ��J�������߂��鎞��ɂȂ��Ă��Ă��邱�Ƃ���ɋ����ĔF���������܂����B�܂��A�}�e���A���e�B�ɂ��Ă��A�ǂ̃X�e�[�N�z���_�[�ɑ��āA���ɑ��ă}�e���A���Ȃ̂��Ƃ������Ƃ���������l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɗ���������ł��B
���Z�@�ւƂ��Ă̋@�\���ő���ɔ������Ȃ���A�{�Ƃ�ʂ��ĎЉ�I�ӔC���ʂ����Ă����B���ꂪCSR�Ƃ������̖̂{������ׂ��p���Ǝv���܂��B���������l���̂��ƁA���s�͊��z���]���Z���ɒ��͂��Ă��܂����B�{���̊O���]���ψ���ł́A������I�Ȏ��g�݂����q���܂̖{�Ƃɖ��ڂɊW���Ă��Ă��邱�ƁA�����̃X�e�[�N�z���_�[�ւ̓K�ȏ��J�������߂��鎞��ɂȂ��Ă��Ă��邱�Ƃ���ɋ����ĔF���������܂����B�܂��A�}�e���A���e�B�ɂ��Ă��A�ǂ̃X�e�[�N�z���_�[�ɑ��āA���ɑ��ă}�e���A���Ȃ̂��Ƃ������Ƃ���������l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɗ���������ł��B
�{���������M�d�Ȃ��ӌ������ƂɁA���i�̌������A�V���i�̊J���Ɏ��g��ł��������Ǝv���܂��B��i�I�Ȏ��g�݂��邢�͏��J������Ɖ��l�Ƃ��ēK�ɔ��f�����悤�A���̒��͕ς���Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B���s�͂��̎���������`���ł���悤����t�s�͂��Ă܂���܂��B�{���́A�����Ԃɂ킽��A���肪�Ƃ��������܂����B