脱炭素までのロードマップを作成し、CO2削減を支援。三井住友銀行とJMACがSustanaのコンサルティング・アドバイザリーサービスを提供する理由

三井住友銀行が開発し、すでに累計2000社以上の企業に導入されているCO2排出量算定・削減支援クラウドサービス「Sustana(サスタナ)」。2022年にSustanaを提供開始して以来、企業の脱炭素に対する意識はどのように変化し、今後どのような取り組みが求められるようになるのか。今回は、Sustanaが株式会社日本能率協会コンサルティング(以下、JMAC)の協力を得て提供している「コンサルティング・アドバイザリーサービス」について関係者に伺いました。
時代は「CO2の可視化」から「CO2の削減」へ
2022年5月にSustanaをローンチしてから2年ほど経過しましたが、企業の脱炭素への取り組み状況はいかがでしょうか?
中野企業が排出する温室効果ガス(GHG)を分類するためのScope1~3という範囲があります。Scope1で定義されている範囲は企業が自らの活動で直接排出するCO2排出量です。Scope2で定義されている範囲は企業がエネルギーを購入して使用する電力などの間接的なCO2排出量です。Scope3で定義されている範囲はScope1とScope2以外の間接的なCO2排出量のことで、一例をあげると社員の通勤や出張、製品の輸送の際に生じる排出量がScope3に該当します。大企業を中心にScope1~3の算定が始まり、定着化してきていると認識しています。サプライチェーン全体のCO2排出量を可視化するScope3にフェーズが移っていくことで、中堅中小企業にもCO2排出量の算定が求められ、お客さまの課題も高度化していると感じます。
河合これまでの脱炭素の取り組みは「排出責任の可視化」にありました。具体的には、企業活動における排出の責任範囲ともいえるScope1~3の算定、製品におけるLCA(ライフサイクルアセスメント)※1やCFP(カーボンフットプリント)※2の対応などです。しかし、昨今は東証プライム市場の企業を中心に「CO2排出量の可視化フェーズ」から、「CO2排出量の削減フェーズ」や「脱炭素の取り組みの内容を評価するフェーズ」へ移ってきています。
排出量の算定は、活動量×原単位で算定を行いますが、この活動量は物量ベースと金額ベースの2種類があります。
「CO2排出量の可視化フェーズ」において、「情報開示のためにとりあえず算定する」というスタンスで、金額ベースで算定してきた企業は、排出量を削減しようとすると、金額を削減しないといけなくなります。どういうことかというと、例えばAという商品を100万円で仕入れた場合の排出量について考えてみます。2024年に100万円で仕入れ、CO2排出量が1tだったものが、2025年に円安等の影響で150万円になったとすると、金額にCO2排出量が紐づいてしまうため、1.5tの排出量となってしまいます。2024年と2025年を比較した時に、同じAという商品を仕入れているにも関わらず、CO2排出量が増加して見えてしまいます。つまり金額ベースでの算定では、「排出量の削減=コストダウンの取り組み」となってしまいます。それだと物価上昇が続く現在では排出量は削減が難しいどころか、逆に増加してしまいます。そのため、世の中の削減フェーズへの移行の風潮に合わせて、金額ベースではなく物量ベースで実際の事業活動に合う排出量を算定する企業が増加しています。脱炭素の取り組みの内容評価については、グローバルな情報開示システムを運営するイギリスのNGOであるCDP ※3から、企業へ毎年寄せられる質問書への回答に対するお問い合わせが増えています。2024年からは気候変動だけではなく、森林保全や水セキュリティ※4も回答の対象となり、企業はますます実態の伴った幅広い脱炭素の取り組みが必要になるでしょう。
(※1)製品・サービスの資源採取から製造、組立、物流、使用、破棄、リサイクルに至る過程の環境影響を分析、評価すること。
(※2)製品・サービスの資源採取から製造、組立、物流、使用、破棄、リサイクルに至る過程で排出されるGHG(温室効果ガス)をCO2換算して製品・サービスに明示すること。
(※3)企業が環境影響を管理するための、グローバルな情報開示システムを運営するイギリスのNGO。特定の企業に質問書を毎年送り、回答内容について分析・評価し、結果を開示している。
(※4)世界の水需要が増加する一方で、気候変動による干ばつの影響等により、水の供給は減少傾向にあるため、企業は水問題が事業に与える現在および将来の影響を理解し、対策をする必要がある。CDPは時価総額や業種における水の影響度を基準に選定した企業に「水セキュリティ質問書」を企業に送付し、回答を促している。

河合 友貴氏
脱炭素の実現には、経営層の理解が必要
社内に専門の部署を設置しているのか、外部の専門人材に頼るのか、脱炭素の取り組みはどのような体制で実施する企業が多いのでしょうか?
清滝どちらのケースもあると思いますが、企業からは「新たに専門部署を新設したものの、専門的な知識を持つ人材がいないため苦労している」「総務や管理業務の担当者が兼任していて、業務負担が増えた」といった課題をよく耳にします。
河合グループ会社内のシェアードサービス※5を利用したり、外部にアウトソーシングしたりする企業も多くあります。弊社でも算定に関する支援のほか、算定プロセスの改善や排出量削減に向けたアドバイス、算定代行サービスなども行っています。
(※5)複数のグループからなる企業が、間接部門における業務を集約させて、効率化やコスト削減を狙うこと。
現状、脱炭素の取り組みに着手できていない企業には、どのような悩みや課題があるのでしょうか?
中野やはり専門人材がいないため、「CO2排出量の算定方法が分からない」といった声や、「算定はできても排出量の削減の方法が分からない」「相談できる相手がいない」などとさまざまな課題があります。専門人材がいても、法規制の動向も日々変化し、削減のソリューションやそれらを導入する際の補助金など、さまざまな情報収集が必要であり、そのための壁打ち相手のニーズもあります。
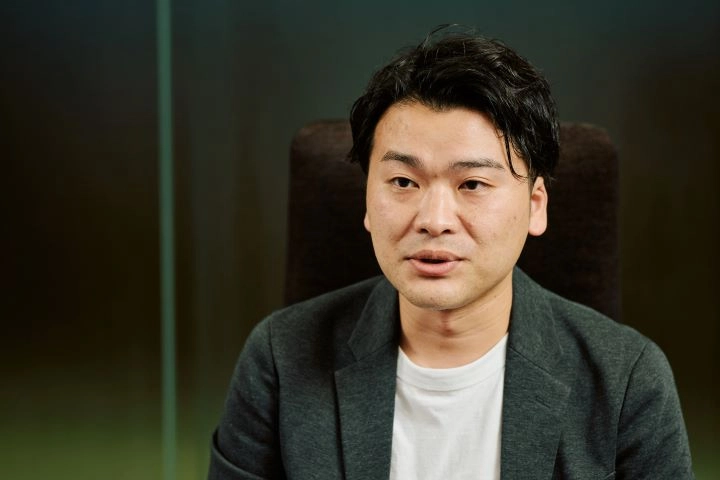
中野 孝啓氏
河合第一に挙げられるのは経営層の理解ですね。脱炭素の潮流を義務やリスクと捉えるか、チャンスと捉えるかによって、企業の取り組み方針や深度も変わります。経営企画部門やサステナビリティ部門が最新の情報をキャッチしていても、経営層に危機意識がなく悠長にかまえているケースもあります。「とりあえず業界内で最低水準でなければいい」と考えている企業もありますが、実際には最低水準どころか周回遅れという危機的状況のケースが大半です。
Sustanaのコンサルティング・アドバイザリーサービスで、脱炭素のロードマップを作成
Sustanaを導入してからの具体的な脱炭素経営のステップと、各ステップで発生する課題について教えてください。
清滝Sustanaの導入初期には、社内で定着させるための教育や運用設計を踏まえた課題があります。その後は「Scope1~2の算定→Scope3の算定→CFPの算定→CDPへの回答、Webサイトや有価証券報告書などでの開示→CO2排出量削減」というフェーズが進むにつれ、より高度な課題が発生します。最初のScope1~2の算定ができないと、当然先のフェーズには進めません。

清滝 悠氏
中野Scope1~2の算定については、CO2排出量算定業務の実施状況に応じた、Sustanaの便利な活用方法をご紹介しているSustana導入ガイドブックを用いてフォローをしています。算定を進めるための体制構築から、社内啓発活動、運用ルールの設計支援などを通じて、導入初期のお客さまをサポートしています。また、自社だけで脱炭素の取り組みを続けることに不安があるお客さまに対して、日本能率協会コンサルティング(JMAC)さまの協力を得て、専門家の助言が受けられる「コンサルティング・アドバイザリーサービス」を2023年6月にローンチしました。
河合Sustana導入の初期段階では、業界内や市場区分内での自社の位置づけを把握できていないお客さまが多くいらっしゃいます。まずは自社の立ち位置の把握から、あるべき姿と現状のギャップを可視化し、今後取り組むべき課題やステップを整理して脱炭素経営の実現に向けたロードマップを作成します。このお手伝いをするのが初期段階の「コンサルティング・アドバイザリーサービス」の内容です。
自社の客観的な立ち位置を把握してもらい、目指すゴールまでの過程をサポートしていくわけですね。
河合やはり会社としてどこを目指すのか、方針と戦略が固まっていないことにはゴールも決まりません。その戦略を実行するための社内体制と業務プロセスが構築されているかの確認と、さらに脱炭素経営に必要なデータ取得のインフラが整っているかもチェックします。戦略、社内体制、業務プロセス、インフラ、これら4つの確認は欠かせません。
脱炭素の取り組みは、これまで以上に広く深く
「コンサルティング・アドバイザリーサービス」の狙いや内容について教えてください。
中野三井住友銀行としてSustanaの導入を検討されているお客さまに対して、「コンサルティング・アドバイザリーサービス」を提供することで脱炭素経営を加速できればと考えています。
河合面談時間は3時間で、自己認識を把握するために診断シートを記入いただいてヒアリングを行います。お客様自身が思っている立ち位置と、私たちが考える客観的な立ち位置を比較しながら、そのギャップを埋めるための取り組みをご提案いたします。
脱炭素の取り組みは、これまで以上に広く深くなっています。Scope1~3の算定だけでなく、製品単位での排出量も求められ、CDPの回答もより高スコアを狙う企業が増えています。海外の法規制への対応などスピードが求められる場面もあり、各社の方針によりやるべき取り組みもさまざまです。脱炭素の取り組みが進んでいる企業も、そうではない企業も、壁打ち相手として気軽にご相談いただければ幸いです。
どのような企業が利用されると想定していますか?
中野特定の業種に偏ることはないです。CO2排出量の算定が必須な企業さまが対象ですので、大手企業から中堅中小企業まで幅広く対象になると想定しています。
清滝最近はプライム市場の企業から徐々に、スタンダード市場、グロース市場の企業にも脱炭素の意識が広まりつつあり、上場企業からCO2排出量の開示要請を受けたサプライチェーン企業がターゲットになり得ると考えています。
では今後、両社が力を入れていきたいことについて教えてください。
中野「CO2排出量の可視化」の次のステップである、「CO2排出量の削減」に関わる支援に力を入れていきます。Sustanaはレコメンド機能を搭載しており、お客さまの特徴に合わせてCO2削減に繋がるさまざまなアドバイスや情報を提供しています。今後はCO2の排出状況から得られたインサイトをお客さまに還元して、削減活動のお役に立てればと考えています。
河合私は普段、ロジスティクスやサプライチェーンのコンサルティングにも従事しており、CO2の削減とコストの適正化を実現する、ロジスティクス改革のロードマップ策定と実行支援の実績があります。今後は私たちが得意とする「業務プロセスの改善」による省エネ支援にも力を入れたいと考えています。従来の業務プロセスが変わらない限り、CO2排出量の削減もどこかで頭打ちになります。ものづくりのプロセスや物流のプロセス、サービスの提供方法を変えることでお客さまのCO2削減を支援していきます。

PROFILE※所属および肩書きは取材当時のものです。
-

株式会社日本能率協会コンサルティング 生産コンサルティング事業本部 サプライチェーン・デザイン&マネジメントユニット チーフ・コンサルタント
河合 友貴氏
大手電機メーカーで実務経験後、2018年JMAC日本能率協会コンサルティングに入社。
実務経験を活かしたコンサルティングが特徴。サステナビリティ・環境分野では、SDGs推進マスタープラン策定/実行支援、GHGプロトコルスコープ3排出量算定、マテリアルフローコスト会計(MFCA)などのテーマを支援している。 -

株式会社三井住友銀行 デジタル戦略部 部長代理 デジタルビジネスエキスパート
中野 孝啓氏
ベンチャー企業にて業務系SaaSサービスの責任者として、サービス立ち上げから事業開発を経験。2022年に三井住友銀行にキャリア採用で入行し、Sustanaのデジタルマーケティングを推進。2024年4月よりSustanaの開発のプロジェクトマネージャーとしてシステム開発およびデジタルマーケティングに従事。
-

株式会社三井住友銀行 サステナブルソリューション部 戦略企画グループ 部長代理
清滝 悠氏
2007年三井住友銀行 入行。
個人向けリテール営業、中小企業向け法人営業、中堅・大企業向け法人営業を経て、2023年4月よりサステナブルソリューション部に配属。Sustana(サスタナ)を起点とした地方公共団体・事業会社などとの連携やサプライチェーン全体での脱炭素支援業務に従事。
おすすめ記事
その他の記事を読む
-
 その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト
その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト -
 最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント
最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント
アンケートご協力のお願い
この記事を読んだ感想で、
最も当てはまるものを1つお選びください。
アンケートにご協力いただき
ありがとうございました。
引き続き、DX-linkをお楽しみください。
