
東京・大田区の「町工場」であるダイヤ精機の諏訪貴子代表取締役、三井住友フィナンシャルグループの白石直樹執行役員・デジタルソリューション本部長の2人が、中小企業のデジタル改革やDX(デジタルトランスフォーメーション)をテーマに話し合った。
ダイヤ精機のDX事例、中小企業もデジタル化は不可欠
ダイヤ精機の諏訪貴子代表取締役は、創業者である父の急逝を受け、2004年に32歳で主婦から一転、精密金属加工の町工場2代目社長に就任。生産管理システムの一新など思い切った改革を推し進め、経営危機から再生させた。一方、三井住友フィナンシャルグループの白石直樹執行役員・デジタルソリューション本部長は、金融の枠組みを超えてデジタルサービスを次々と創造し、中堅・中小企業のDXも支援しているSMBCグループのデジタル関連事業の推進者だ。
「中小企業のデジタル化」はなぜ必要なのか。デジタル化やDX成功の秘訣は何か。これまでの経験を踏まえて議論してもらった。
白石諏訪社長は社長就任と同時に経営改革に着手し、その中で他の町工場に先駆けて生産管理システムを一新しています。どのような考えがあったのでしょうか。
諏訪社長就任当初、当社の業績は低迷し、改革が必須の状況でした。そこで「意識改革(1年目)」「チャレンジ(2年目)」「維持・継続・発展(3年目)」という「3年の改革」を実行しました。その2年目に挑戦したのが生産管理システムの刷新でした。
「当社の強みは何か」を取引先に聞いてみたところ、技術面もありますが、何よりも「急な依頼への対応力」にあることが分かりました。当時も1カ月に扱う製品数が1万点にも達する究極の多品種少量生産でしたが、「対応力」をさらに高めるにはその徹底した管理が必要でした。従来は受注後の進捗管理は各人がノートやパソコンでバラバラに行っていました。
そこで、生産の進捗を管理し、急な注文にもしっかりと応えられるように生産管理システムを一新したわけです。

諏訪 貴子氏
2021年には、2回目の大掛かりな更新を行い、営業や設計に関する全ての情報を一元管理し、タブレット端末を活用して、全社で共有できるシステムにしました。これにより、営業と生産現場の職人とのやりとりの時間が減り、現場の生産性が向上しました。
これらの成果は、とにかく「そのときに優先すべき作業」が明らかになったことです。納期遅れが大幅に減り、当社の強みの「対応力」に一層、磨きをかけることができました。
白石やはり、これからの時代は、人口減少という大きな時代の流れを見ても、中小企業といえども、DXは不可欠といえますね。例えば、デジタルネイティブのZ世代は、いわゆる「タイパ」をすごく意識しています。
加えて、転職が当たり前の時代になってくると「あうんの呼吸」で行う業務は成り立ちません。人が変わっても同じように業務を遂行できる環境にしておかなければならない。とにかく歯を食いしばってDXを推進し、「これからの時代」にマッチした変革を行うことが求められています。

デジタルソリューション本部 執行役員 デジタルソリューション本部長
白石 直樹氏
諏訪「ミクロな経営環境」からも同じことがいえます。当社の主要取引先は自動車メーカーですが、大きな変革期にあります。将来的にEV(電気自動車)が主流になれば、部品点数が大幅に減る一方、生産拠点の海外シフトも進むため、国内の仕事量は減ってくるでしょう。これまでのような「待ち」の姿勢では仕事はなくなってしまうと思います。
デジタルの力を積極的に利用し、製品やサービスの付加価値を高めるなど、自社の優れた点をより強化していかなければなりません。
メガバンクのような大手金融機関もデジタル化をどんどん進めていますね。SMBCグループでは、自社のデジタル化にとどまらず、新規事業として、中小企業のDX支援にも力を入れており、すでに10社以上の子会社がデジタルサービスを提供していると知り、驚きました。やはり、時代や経営環境の「大きな変化」が影響しているのでしょうか。
銀行も「デジタル化」や新規事業が求められる時代
白石コロナ禍以降、社会全体でデジタル化が加速しています。これに伴い、非金融事業者の新規参入、いわゆる「プラットフォーマー」と呼ばれるIT関連事業者の金融領域への参入が相次いでいます。
かつてマイクロソフト社の創業者、ビル・ゲイツ氏は「銀行の機能は必要だが、銀行は必要なのか(Banking is necessary, banks are not)」と発言しました。これは「銀行は変わっていかなければ生き残れない」ことを示唆しています。
そこで、SMBCグループでは、13年ごろから金融業界の中でも率先してDXに取り組んできました。
デジタル系事業としては中堅・中小企業のデジタル化を支援する「プラリタウン」や電子契約の普及に大きく寄与してきた「SMBCクラウドサイン」など、金融と非金融の両輪で、中小企業や社会の課題解決を目指す事業・サービスを展開しています。

実際に、こうした事業を見てきて、中小企業のDXに難しさも感じています。アナログからデジタルに切り替えるには、最初に現状のアナログのプロセスを見える化してデジタルに置き換える作業が必要ですが、それをできる人的な余裕がない、そうするとせっかく導入したデジタルツールを使いこなせない、あるいは現場がデジタルツールを使ってくれない、また、できるところだけ部分的にデジタル化していくとプロセス全体のシステムが連携できないので効率化につながらない、アナログの仕事のやり方にシステムを合わせていくとツールのアップデートに対応できない……といったことが挙げられます。
諏訪さんが考える、中小企業がデジタル化やDXを進めるときのポイントは何でしょうか。
中小企業のDXで「最初にやるべきこと」とは
諏訪まず、「目的を設定すること」が何より大切です。「紙を減らす」「業務を見える化する」「機械の稼働率を上げる」などの目的が明確になると、それに対して何ができていないのか、課題が抽出できますから、その対策を立てることができます。
加えて、当社の経験からいうと「成功の秘訣」は三つ挙げられます。一つ目は「従業員の意見を聞き、全員の意思で取り組むこと」。二つ目は「全ての機能を初めから使おうとしないこと」。たくさんあるパッケージソフトの機能を欲張って全部使おうとすると使い切れなくて中途半端になりがちです。
当社が生産管理システムを一新したときも、進捗管理と買掛金・売掛金の管理以外は全て捨てました。スモールスタートし、徐々にステップアップしていくことが大切です。マラソンで42.195キロを走ると思うと考えただけでも挫折しそうですが、1キロごとにゴールを設定すれば頑張れる。それと同じです。
そして、三つ目は「習慣化すること」。人は2週間、同じ時間に同じ行動を取ると習慣化されるそうです。情報共有ツールを導入したときは「朝・昼・晩の1日3回、必ずタブレットを開いて情報を確認すること」を義務付けました。

白石なるほど。やはり、何を解決すべきなのか、現状をしっかり分析して、方向性を定める。そして、最初にやるべきことを決めたら、少しずつでも前に進めることが重要なのですね。業務を見える化しないとデジタル化できないため、まずは業務を分解して、明確にしていくことが大事なんだと思います。
諏訪私が最初に行ったのは、業務と業務フローの見直しによる徹底した業務の標準化です。先にお話ししたように、当社の強みが「対応力」なのにもかかわらず、無駄な作業がかなり発生していたからです。
DXの導入方法には、「自社の業務フローに合わせてSEが設計する」「ベースとなるシステムをカスタマイズする」「パッケージソフトを活用する」――という3種類があって、それぞれメリット、デメリットがあります。当社は、安くて簡単に操作ができるという条件に合うパッケージソフトの活用に決めました。
そして、多品種を生産する当社の工場で、リアルタイムの進捗管理ができるように、バーコードを使って簡単に情報が入力できるソフトを探して導入しました。これが当社のDXの第一歩です。
白石パッケージソフトに合わせて業務を変えると、得てしてベテラン従業員の抵抗に遭ったりします。しかも、システムに慣れないうちは熟練者の作業や勘の方が速かったりしますよね。この点に関してはどうでしたか。
諏訪とにかく、日報を書かずに済むなど「楽になること」を強調しました。例えば、日報を書くのに10分かかるとして、20人だと1日200分。それが30日になると100時間にもなるわけです。「これってすごい無駄ですよね」と従業員にアピールしたんです。
新しい生産管理システムの必要性や効果については、私やベンダーがプレゼンテーションを実施しました。そのプレゼンに対する質問をアンケートで受け付け、質問に答える形でまたプレゼンを行う。これをしつこく繰り返すと、徐々に質問がなくなってきます。そうすると今度はいろいろと文句が出てくるんですよ。
白石えっ、文句ですか。
諏訪はい。「ボタンが多過ぎる」とか、「ここでバックの機能が欲しい」とか。ただ、それに対応してカスタマイズしていくと、「自分たちが関わって作り上げた」という思いもあって、とことん使ってくれるようになるんですね。
職人たちは「仕事に役立つ」と納得さえすれば、柔軟に新しいものを取り入れます。
旧システムのシャットダウンは大手企業でも1~3カ月かかります。当社の場合、パソコンの電源も入れたことがない人もいたので、6カ月から1年くらいはかかるだろうと思っていましたが、実際はなんと3カ月で完了しました。
何よりも「トップ」の強い意思が必要だ
白石お話を伺うと、やはり、トップが陣頭指揮を執り、「DXを進める」と宣言して情報を発信し続け、部下のモチベーションを上げていくことが大切なのだと改めて実感しました。
諏訪その通りだと思います。トップが明確に方向性を示さなければ、従業員は不安になります。

白石大手企業でも全く同じです。SMBCグループが従来の金融業務の枠にとらわれない新規事業に積極的にチャレンジできているのは、前CEOの太田(純)が「不退転の決意」を持って従業員に向けて「カラを、破ろう。」と常々呼び掛けてきたからです。この方針は24年3月に就任した現CEOの中島になっても変わらず、「突き抜ける勇気。」というスローガンを掲げています。
例えば、SMBCグループ内では、これまでにない新規事業を作り出すカルチャーを醸成するための仕組みとして、金融というカラを破ってチャレンジする従業員を支援し、社内ベンチャーの社長に抜てきする「社長製造業」というものがあります。事業のアイデアを出した担当者を、その社内ベンチャーの社長として抜てきしており、今では社長製造業で設立した子会社は10社以上になっています。DXはもちろん、こうした銀行全体のカルチャーを変えていく取り組みをしています。
こうした変革に対するさまざまな取り組みを通して、行員も会社が変わってきていることを実感しながら、経営層がその取り組みをサポートしてくれる体制が整っていると感じています。トップが率先して推し進めるデジタル化やDXは、企業のカルチャーにも大きく影響すると思います。
諏訪当社はデジタル化の推進と併せて、若手従業員の採用、育成にも力を入れました。社長に就任した当時は、従業員27人のうち私より年下はわずか3人、6割以上が50代超でした。現在では、生産現場の職人の過半数が30代以下と大幅な若返りを実現できました。
若手従業員が増えたことで、企業文化や雰囲気も大きく変わりました。繰り返しになりますけれども、まず、トップは「目的」を明確にし、できるところから少しずつでもやっていくことが重要だと思います。
ちなみに、これは当社の超精密加工のサンプルで階段状に5段階、段差が付いています。触ってみてください。段差が何ミリか、分かりますか。

白石(指でなぞりながら)一番小さい段差になると、もう分かりませんね。うす~く線はありますが……(笑)。
諏訪一番大きい段差が1ミリで、一番小さいのが1000分の5ミリ、つまり、5ミクロンです。一般の人が指で感じることができるのは5ミクロンが限界といわれています。
私たちは1ミクロンの段差を付けることができます。これは機械では絶対にできません。この超精密加工技術を活用した製品を創業以来造り続けているのです。こうした技術をしっかりと継承していかなければ、私たちのような中小企業に将来はありません。
白石まさに日本が世界に誇る、素晴らしい技術ですね。このような「自社の強み」を、いかにしてデジタル化で伸ばし、将来につなげるか……。それができないと、日本独自の高度な技術もどんどん失われていくのではないかと心配になります。
デジタル化は目的ではなく、あくまで手段として活用することですが、できるところはなるべくデジタル化して効率化し、付加価値の高い技術の研さんや継承に、より多くの時間や労力を費やせる環境をつくり出すことが大切ですね。
今日はお話を伺って、SMBCグループとして、引き続き、お客さまのニーズに応えるデジタルサービスの拡充に努めていきたいとの思いが強くなりました。
諏訪当社も間接業務のデジタル化によって業務を効率化し、持続可能な状態に持っていくことができました。同じようなアプローチで、利益を出せる中小企業はまだまだ多いはずです。今後もぜひ中小企業のDXや変革にお力添えをお願いします。
出展元
「2024/12/18公開 ダイヤモンド・オンラインタイアップ広告より」
PROFILE※所属および肩書きは取材当時のものです。
-

ダイヤ精機 代表取締役
諏訪 貴子氏
1971年東京都大田区生まれ。95年成蹊大学工学部卒業後、ユニシアジェックス(現・日立Astemo)入社。98年創業者の父に請われ、ダイヤ精機に入社するが、経営方針を巡る意見の相違で退社。2004年父の急逝に伴い、同社社長に就任。13年日経ウーマン「2013ウーマン・オブ・ザ・イヤー」大賞受賞。岸田内閣に続き、石破内閣でも「新しい資本主義実現会議」有識者メンバー(現任)。現在、日本郵政、日本テレビホールディングスの社外取締役も務める。
-
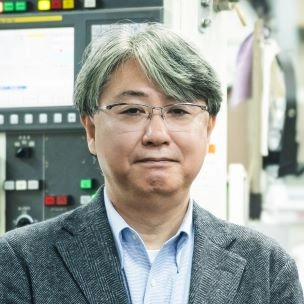
三井住友フィナンシャルグループ
デジタルソリューション本部 執行役員 デジタルソリューション本部長白石 直樹氏
1993年にさくら銀行(現・三井住友銀行)に入行。ホールセール事業部門の企画や営業部署等を経て、2020年より法人デジタルソリューション部長。21年より三井住友フィナンシャルグループ執行役員デジタル戦略部長、24年より現任の執行役員デジタルソリューション本部長。SMBCグループのDX(デジタルトランスフォーメーション)や新規デジタル関連事業開発を推進する。
おすすめ記事
その他の記事を読む
-
 その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト
その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト -
 最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント
最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント
アンケートご協力のお願い
この記事を読んだ感想で、
最も当てはまるものを1つお選びください。
アンケートにご協力いただき
ありがとうございました。
引き続き、DX-linkをお楽しみください。
