中小企業向け使いやすさ最優先。銀行の常識と開発手法を塗り替えた「Trunk」開発秘話

これまで中小企業やスタートアップにとってハードルが高かった、メガバンクでの口座開設。そのイメージを打ち破るべく、SMBCグループが2025年5月に提供を開始したのが法人向けデジタル総合金融サービス「Trunk(トランク)」です。
中小企業のお客さまに、より便利に、お得に使ってもらうためにーー。デザインや操作性、開発手法に至るまで従来の“常識”を塗り替えて生まれました。現場の情熱と挑戦が形になったこのサービス。シリーズの第二弾となる今回は「開発者たち」に焦点を当てます。Trunkの開発者たちはどのような思いで、このプロジェクトに臨み、どんな壁にぶつかり、 どう乗り越えたのか。
三井住友銀行の中村聡氏、岡村英昌氏、岡山晨哉氏、日本総合研究所(以下JRI)の山田美奈氏、さくら情報システム株式会社(以下SIS)の小櫻陽大氏、株式会社NTTデータ(以下NTTD)の五十嵐正裕氏にお話を伺いました。
連載:「Trunk」誕生秘話
- 中小企業向けデジタル総合金融サービス「Trunk」誕生の舞台裏
- 中小企業向け使いやすさ最優先。銀行の常識と開発手法を塗り替えた「Trunk」開発秘話
出発点はユーザー理解。中小企業のお客さまの声を起点に
開発チームとして、Trunkのコンセプトを最初に聞いたときはどう感じましたか。
SMBC中村「法人ネット口座を起点として、中小企業経営の根幹となるおカネ周りの業務を、効率化・改善する様々なサービスのご提供、そして新しいファイナンス体験の実現を目指す」というコンセプトを聞いた当初、我々開発側は、ターゲットとなる中小企業のお客さま像や困りごとの理解が足りていませんでした。そこでまず、具体的なお困りごとを中小企業の経営者に直接インタビューしました。

DX開発グループ グループ長
中村 聡氏
インタビューを重ねて分かったのは、特に規模10人以下では、社長お一人で売り上げから経費管理までを担っており、負担がかなり大きいということです。まさにTrunkは、そうしたお客さまが本業に集中できるようなサービスを目指していたので、その必要性を改めて実感しました。
開発の前に「ワイヤーフレーム(デモ画面)」を作成し、お客さまに実際に触れてもらって、機能の必要性や使いにくさを確認しました。フィードバックをもとに修正を重ね、見通しが立ってから開発に進む「デザイン思考」を取り入れました。
JRI山田「デザイン思考」とは、ユーザー視点で問題を捉え、課題解決を図る思考法です。「デザインや使い勝手が良くなければサービスは使ってもらえない」という認識は初期からチームに根付いており、ユーザーの意見を元に方針を定めることが当然という雰囲気になっていました。

山田 美奈氏
SMBC中村私はOliveを開発したリテールIT戦略部に在籍したことがあり、デザイナーが常駐する環境でUI/UXの重要性を実感しました。その経験が今回も生きています。
今こそ改革。価格も体験も、開発手法も全て塗り替える
SMBC岡山私はTrunkのコンセプトを聞いたとき、改革のチャンスだと感じました。
既存の法人向けインターネットバンキング「Web21」でも機能強化は進めてきましたが、手数料を下げるなど大胆な改革はできていませんでした。そういう意味で、このプロジェクトは、サービスの根本を考え直す機会になると感じました。
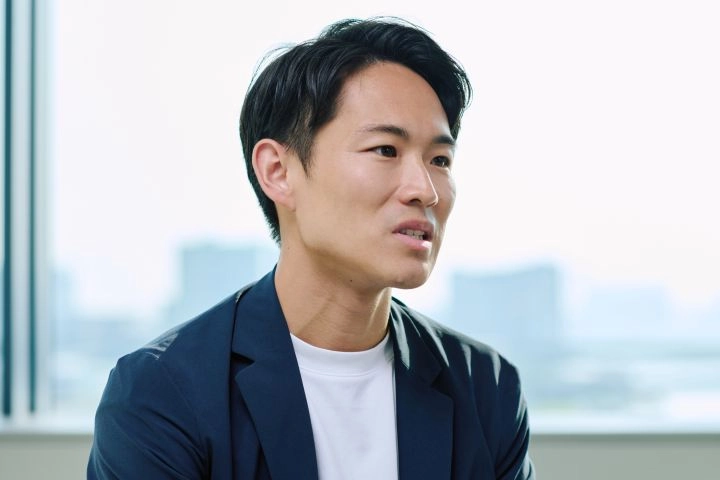
国内商品開発 第二グループ 部長代理
岡山 晨哉氏
ただ、やはり改革には苦労も伴いました。長年「Web21」を手がけてきた私が所属する決済商品開発部やプロジェクト関係各部と一つひとつ合意形成を進めました。
これまでのBtoBプロダクトと意図的に変えた進め方などがあれば教えてください。
SMBC岡山従来サービスは日常的にインターネットバンキングを使い慣れている経理のプロが主な利用者で、投資対効果が見えにくいUI/UXは正直後回しになりがちでした。Trunkでは、中小企業の経営者がマニュアルを見なくても使えるよう、今まで以上にUI/UXに重きを置く必要がありました。そこが大きな違いです。
JRI山田UI/UXに重きを置くというコンセプトを受け、法人向けプロダクトとしては初めて、アジャイル開発に取り組みました。
銀行業務のコア部分はこれまで同様、ウォーターフォール開発で進めましたが、Trunkでは、UI/UXの改善や追加要望が発生する特性を踏まえお客さま向けのチャネルでアジャイル開発を活用しました。
“迷わない操作”へ。画面遷移を最小化、数ステップで完結
Trunkのシステム設計上、工夫した点、苦労した点を教えてください。
SMBC岡村従来のシステムは、マニュアルが何百ページにも及ぶ複雑なものでした。Trunkでは、スマホライクな操作感を意識し、画面遷移を最小化。数ステップで完結できるシンプルな設計を心がけています。

DX開発グループ 部長代理
岡村 英昌氏
JRI山田以前は、口座開設に約200項目もの入力が必要でしたが、お客さまの負担を減らすために見直しを続け、約200項目から約70項目に削減。外部サービスの情報や本人確認で読み取った情報を自動で反映させるなどの工夫も取り入れました。
SMBC中村構想からリリースまでおよそ1年半、実質の開発期間は9カ月という短い期間で、インターネットバンキングや口座開設などありとあらゆるものを刷新しました。
特に口座開設に関する画面は手戻りがないよう、デザイナーに入ってもらってイメージを決定していましたが、ギリギリまで直し続けました。その結果、使いやすいものになったと自負しています。
自前主義からの脱却。価値提供を大前提にアジャイル×外部ツール導入
短期間での開発が求められる中、どのように効率化や優先順位の判断を行ったのでしょうか?
SIS小櫻Trunkの開発では、リリース期限が明確に決まっており、限られた期間で成果を出す必要がありました。そのため、100点を目指すのではなく、「リリースまでにやりきる部分」と「今後の改善に回す部分」を明確にし、柔軟に優先順位を決めて進めました。
すべてをシステムで作り込もうとすると、時間も費用もかかりすぎてしまうため、画面をローコード・ノーコードで変更できるツールを導入し、開発期間の短縮を図りました。
こうして生まれた開発の余力を、システム全体のブラッシュアップやユーザー体験の改善に充てることができ、従来の「すべて自社開発」という発想を転換し、よりお客さまに寄り添った開発体制を築けたと感じています。

小櫻 陽大氏
SMBC中村さらに、だいぶ踏み込んだ判断をTrunkの責任者がしてくれたと思います。開発期間9カ月という期限がある中で、お客さまが本当に必要とするものは何なのかという目線を合わせながら割り切る。その合意形成ができたと思います。
開発チームに大きな裁量を与えてもらい、スタートアップのようにスピード感をもってサービスを育てる環境を整えてもらっています。リリース後もお客さまの声を聞いて、より良いものを作っていく体制をとっています。
JRI山田Trunkプロジェクトは、継続的に改善をするというミッションがあったので、お客さまの反応を見てリリース後に追加で機能改善する相談もしやすいと感じます。
口座・カード・請求書支払い・補助金。中小企業の必須機能を一気通貫で提供
新法人カードについてはいかがですか。
NTTD五十嵐口座開設と同様に、入会申し込みの際にお客さまに入力していただく項目はなるべく省略できるように心がけています。従来は「カードを申し込む」と「口座を開設する」は別々でしたが、Trunkにおいてはなるべく一体感を持ってシームレスに申し込みができるような体験を目指しています。

バンキング・イノベーション統括部 第1インテグレーション担当 主任
五十嵐 正裕氏
新機能も含めて、今後挑戦したい開発について教えてください。
SMBC中村今まさに請求書支払いの新機能を開発しています。中小企業のお客さまが請求書をどう作成・管理し、それをどう処理しているのか。その作業をどうシステムに落とし込めば、不便を改善できるのか。当たり前のことかもしれませんが、お客さまが何に困っているかを本質的に理解し、共感しながらサービスを作り込むことにこだわっています。
もちろん、その新機能のビジネス的な価値をどこに見出し、どこで利益を確保するのかという観点も忘れてはいけません。収益モデルと合わせて、どのような機能にするべきなのか、日々議論をしています。
JRI山田今回の新機能は「請求書の管理だけでなく支払いまで1つのサービスで行える」というところが最大の特徴だと思います。スマホ一つでシームレスに、請求書の読み取りから振込またはカード払いまで申請できるように現在開発を進めています。
そのほか、新機能として補助金サポート機能がリリース予定と聞きました。
SMBC中村お客さまにインタビューすると、補助金の活用ニーズは高いですが、補助金を申請する時間が作れないという課題があることが分かりました。
そこで、Trunkのお客さま向けに補助金の情報を提供したうえで、申請サポート事業者をご紹介する機能をリリース予定です。システム上の工夫としては、Trunkのチャットボット上で、「こういう補助金がおすすめです」というように提案をしてくれるAIを組み込んでいます。
Trunkでは、銀行サービスという殻を破ってお客さまの業務の中まで入り込み、バックオフィスの効率化を支援するサービスを提供していきます。これからも、Trunkの中に機能を改善・追加し、「Trunkがあれば大丈夫」と言えるようなサービスを作っていきたいと思います。

連載:「Trunk」誕生秘話
- 中小企業向けデジタル総合金融サービス「Trunk」誕生の舞台裏
- 中小企業向け使いやすさ最優先。銀行の常識と開発手法を塗り替えた「Trunk」開発秘話
PROFILE※所属および肩書きは取材当時のものです。
-

三井住友銀行 トランザクション・ビジネス本部 決済商品開発部
DX開発グループ グループ長中村 聡氏
2005年に三井住友銀行へ入行。約10年人事部にてシステム開発に従事したのち、リテールIT戦略部にてDX企画を推進。2023年より決済商品開発部に所属。Trunkに関連するプロダクト開発の責任者。
-

三井住友銀行 トランザクション・ビジネス本部 決済商品開発部
DX開発グループ 部長代理岡村 英昌氏
2013年に証券系システム会社に入社。金融・ITのコンサルタントを経験後、2024年よりSMBCに参画。現在はTrunkに関連するシステムの開発推進を担当。
-

三井住友銀行 トランザクション・ビジネス本部 決済商品開発部
国内商品開発 第二グループ 部長代理岡山 晨哉氏
2019年に三井住友銀行へ入行。法人営業経験を経て2021年より決済商品開発部に所属。法人向けインターネットバンキングの担当としてWeb21やアプリ、APIサービス等の企画業務へ従事。Trunkの立ち上げ時から開発チームに参画し、Trunkの決済機能の企画・開発を担当。
-

日本総合研究所 法人ビジネスプラットフォームタスクフォース チーム長
山田 美奈氏
2012年日本総合研究所に入社。個人向けスマートフォンアプリの開発を経て、2023年よりTrunkプロジェクトに参画し、顧客接点となるチャネルのシステム開発を担当。
-

さくら情報システム株式会社 金融事業本部 金融ソリューション第2部金融DM開発グループ
小櫻 陽大氏
2017年よりWEBアプリの開発エンジニアとしての経験を経て、さくら情報システムに2021年入社。
勘定系システムの保守開発やマンション管理システムの移行案件を実施。
その後2023年に三井住友銀行 決済商品開発部へ業務出向。Trunkの立ち上げ時から開発チームに参画し、Trunkに関連するシステムの開発推進を担当。 -

株式会社NTTデータ 第一金融事業本部 金融グローバルITサービス事業部
バンキング・イノベーション統括部 第1インテグレーション担当 主任五十嵐 正裕氏
2021年NTTデータに入社。顧客情報管理システムの保守開発を担当し、その後2023年に三井住友銀行 決済商品開発部へ業務出向。Trunkの立ち上げ時から開発チームに参画し、銀行システムと新ビジネスカードの連携要件を担当。出向期間終了後は同プロジェクトにて請求書支払い機能の開発に従事。
おすすめ記事
その他の記事を読む
-
 その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト
その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト -
 最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント
最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント
アンケートご協力のお願い
この記事を読んだ感想で、
最も当てはまるものを1つお選びください。
アンケートにご協力いただき
ありがとうございました。
引き続き、DX-linkをお楽しみください。

