なぜSMBCグループは宇宙事業に「本気」なのか。金融×宇宙で拓く、産業支援の新しいかたち

なぜ、金融グループが宇宙産業に挑むのか。
SMBCグループは今、銀行・リース・コンサルティング・ベンチャーキャピタルの総力を挙げて、いま宇宙産業の支援に本気で取り組んでいます。
一見、かけ離れているように思える「金融」と「宇宙」。その接点、そしてグループ横断で描く未来像を、各社のキーパーソンたちの言葉から紐解きます。
“金融の次なる使命”として、宇宙に挑む理由
宇宙事業への参入は、企業にとって大きなリスクとも言われます。そのなかで、なぜSMBCグループは宇宙産業に取り組むことを決断されたのでしょうか。
SMBC 横山宇宙分野への取り組みを始めたのは2020年末です。理由は大きく二つ。一つは、銀行には産業を育成・発展させるという金融機能としての役割があることです。
かつて日本は、航空機技術において高いレベルを有していましたが、戦後はその技術を活かせず、技術者たちは自動車や電機産業へと流れていきました。こうした産業は今、大きな転換期を迎えており、次の成長分野として、宇宙に技術が向かうのではないかと考えています。たとえばロケットの燃焼系技術には、自動車の内燃機関技術が応用できます。時代の変化の中で、新たな成長産業として宇宙に着目し、その立ち上げに銀行として関与すべきだと判断しました。
もう一つの理由は、政府や投資家がディープテックを中心に多くの資金を投入し始めていることです。なかでも宇宙分野は非常に有望なマーケットと捉えられており、我々としてもその流れに合わせて支援を進めるべきだと考えました。
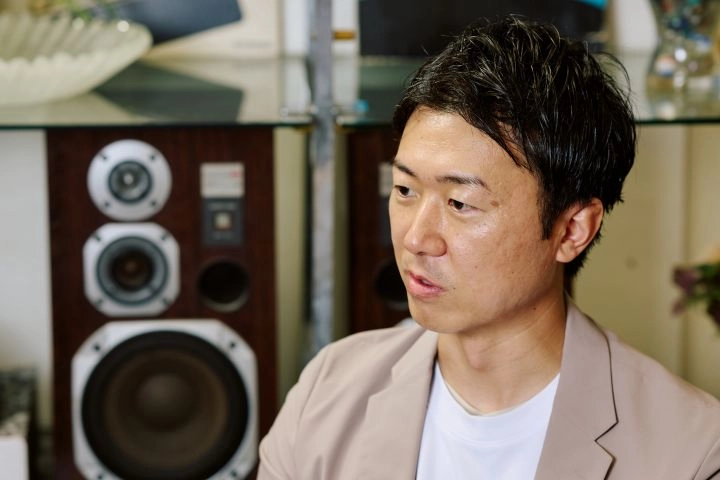
横山 嵩氏
三井住友ファイナンス&リース(以下、SMFL)は、リースという立場からどのように宇宙産業を支援されているのでしょうか。
SMFL 佐藤宇宙産業はリスクも大きいですが、それ以上に成長性の高い分野だと考えています。さらに設備投資も多い産業だからこそ、“モノ”を扱う我々の出番が増えると考えています。実際に、SMFLレンタルでは計測器をレンタルしており、衛星打ち上げ前の試験環境やロケット開発にも不可欠な存在です。融資だけでなく、リースという手段による“モノ”の支援は宇宙産業にとっても重要だと考えています。

佐藤 壮祥氏
日本総研(以下、JRI)としての宇宙領域への関わりを教えてください。
JRI 加藤当社はもともと、まちづくり分野における官民連携事業を強みとしてきました。2008年に、日本で初となる人工衛星の官民連携事業である気象衛星「ひまわり」の事業化検討支援が、宇宙分野への最初の取り組みです。その後、日本版GPSと呼ばれる準天頂衛星のPFI事業(公共施設を民間資金やノウハウを活用して整備運営すること)についても事業組成検討から現在のモニタリングフェーズまで継続して支援を行っています。
公共施設の官民連携事業(PFI)は、原則安定稼働を前提としますが、人工衛星、特に準天頂衛星のように機数拡大による契約変更を伴う事例では、リスク抑制を含めた支援が不可欠でした。
また、近年注目しているのが「スペースポート」と呼ばれる宇宙港です。たとえば大分空港では、有翼の宇宙船の着陸が可能な機能を持たせる計画が進んでいます。空港や港湾のように、宇宙港がインフラとして整備される時代に備え、官民連携事業の知見を活かした支援を検討しています。

加藤 大樹氏
SMBCベンチャーキャピタル(以下、SMBC VC)では宇宙ビジネスに取り組むスタートアップを支援していますね。
SMBC VC 真鍋我々が支援するのは、早期のスタートアップ企業が中心で、まだ技術も確立されていない段階から携わることも珍しくありません。そこにあえて投資するのは、宇宙領域の技術が現代を生きる我々、ひいては未来の人々にとって有用なものになると信じているからです。GPSや衛星通信など、宇宙開発がもたらした恩恵は多く、現状は具体的な市場開拓ができていなくても、将来的に役に立つであろうという企業・技術開発を見定めて投資することによって、価値ある技術を未来につなげていくことが必要だと考えています。

真鍋 晃太郎氏
グループ連携で生み出す、金融×宇宙の支援スキーム
具体的に、宇宙領域への支援をどのように進めてきましたか。
SMBC 横山国内の宇宙産業の拡大には、現在中心にいる企業だけではなく、「自分たちは宇宙とは関係ない」と感じているような企業の参入が必要不可欠です。そのためにはどうすべきかを逆算し、2022年度から試行錯誤しながら取り組んでまいりました。
2023年度時点では宇宙領域スタートアップへの融資実績がほとんどなかったため、デットファイナンスによる支援に注力しました。その結果、2024年度のスタートアップ向け融資全体の約900億円のうち、3~4割が宇宙関連となりました。1、2年でゼロからこれだけの数字を積み上げるインパクトがなければ、世の中で「三井住友銀行が宇宙を支援している」というイメージがつきませんし、何を言っても説得力がない。自分たちがまずコミットし、リスクを取っている意思表示としてファイナンスに力を入れました。
また、宇宙保険を手がける三井住友海上と、宇宙関連スタートアップ企業の支援に向けた協業のMOU(基本合意書)を締結。さらに、再利用型ロケットや有人輸送機を開発する将来宇宙輸送システムとの間でもMOUを締結し、自国の打上げ手段の早期確立に向け支援しています。また、銀行員が宇宙関係の大型イベントに登壇するなど、金融の立場における宇宙産業への取り組みに対する対外発信にも力を入れています。
今後は、銀行のみならず、SMBCグループ会社と“宇宙”を軸にした協業・共創を一層加速させ、金融機関としても宇宙関連ビジネスを手掛けることが可能だということを、あらゆる業界の方々に発信してきたいと考えています。
2025年1月には、社長と頭取を交えた場で、宇宙に関する銀行ビジネスの方向性について議論しました。現在では、頭取からも月面探査を手掛けるispaceの話題が出るなど、経営レベルにも宇宙に関する理解が浸透し関心が高まっています。
2025年度はより大きな形で、対外的なコミットメントを打ち出していきます。
佐藤SMFLグループとしては、主にSMFLレンタルとSMFLみらいパートナーズの二つの側面から宇宙産業の支援を目指しています。
先ほどもお伝えした、SMFLレンタルによる各種測定機器のレンタルのほか、SMFLみらいパートナーズ(三井住友ファイナンス&リースの子会社)では、2023年にJAXAとの共創プログラム「J-SPARC(JAXA宇宙イノベーションパートナーシップ)」に参画し、人工衛星のリース事業と人工衛星の二次利用事業の創出に向けた取り組みを開始しました。衛星に対してリースを活用することで、初期コストを低減し、宇宙産業への新規参入のハードルを下げることを目指しています。
衛星の二次利用に関しては、衛星の将来価値に着目し、人工衛星の取得価額から残存価値を差し引いた部分をリース料に設定するオペレーティング・リースの提供を目指しております。
JRI 加藤まちづくり分野で培った官民連携事業に関するノウハウを切り口に宇宙領域に関わり始めましたが、準天頂衛星のPFI事業支援を通じてGPS等の他国の動向も含めて測位衛星に関する知見を積み重ねてきました。最近では、Starlinkに代表されるような衛星通信分野も含めて、宇宙分野に関する調査案件や衛星を活用した実証実験の支援にも取り組んでいます。私が所属するまちづくりや官民連携事業を専門とするグループに加え、通信分野を専門とするグループとも連携し、社内横断的に体制を整えています。
また、高頻度な宇宙輸送サービスの実現に向けた「次世代型宇宙港」ワーキンググループの事務局運営にも携わっています。宇宙ビジネスが現実味を帯びる中で、さらなる案件化に注力していきます。
SMBC VC 真鍋我々はSMBCグループのVCとして積極的にリスクマネーを提供する役割があります。我々がスタートアップ企業に投資する際は、エクイティからデットへの受け渡しという観点もあるため銀行との連携は大切です。我々はVCという業態上、スタートアップとの接点が多いので、あらゆるスタートアップの会社説明資料や財務諸表を見ながら、ノウハウを社内に蓄積しています。スタートアップから銀行へファイナンスの相談があった際には、いつでもサポートできる体制を整えています。

DXで進化する宇宙ビジネス
宇宙領域の取り組みにおけるDXの進展について教えてください。
SMBC 横山かつてロケット開発は1点物で、要素技術を一つずつ検証しながら進めるウォーターフォール型のプロセスが一般的でした。しかし現在は、年間に何百回も打ち上げる時代になっており、従来型の開発では到底間に合いません。今は、実証データをプラットフォームに集約することで、打ち上げの最適化が進み、リードタイムが大幅に短縮されています。国内でこれを実現しているのは将来宇宙輸送システム社のみですが、今後の標準モデルになる可能性を感じています。
一方、我々銀行グループとしても、宇宙に関心の薄い事業会社に参入してもらうための“実例づくり”を構想しています。たとえば、三井住友カードが発行するプラチナカード会員向けに、将来宇宙輸送システムの打ち上げ見学ツアーや、宇宙食体験イベントを提供する企画を検討中です。将来的には、総合金融サービス「Olive(オリーブ)」内で、宇宙旅行の予約ができるようにする構想もあります。その際、保険やファイナンスなど、グループ各社のサービスが必要になるため、スケールメリットを活かした連携が可能です。
JRI 加藤製造・開発だけでなく、宇宙利用の領域でもDXの重要性が高まっています。とりわけ衛星撮影写真(リモートセンシングデータ)の活用が注目されている一方で、衛星の数がまだ少なく撮影頻度やリアルタイム性が課題です。
低コストでロケットや衛星を打ち上げられるようになればデータの即時性も高まり、農業など限られた分野にとどまらず、広く産業活用が進むでしょう。衛星データは見ただけではわかりにくいため、それを“翻訳”して、顧客視点で価値化できる事業者の重要性が、今後増加していくと考えています。
宇宙は“ロマン”から“リアル”へ。変わる宇宙ビジネスの熱量
最近、宇宙産業に対する期待値や動きに変化は感じられますか?
SMBC 横山一番の変化は行内の意識です。宇宙セクター立ち上げ時は宇宙を知る人材が殆どいませんでしたが、各部門に宇宙の可能性を語って回り、協力を募ってきました。そうした働きかけの結果、今では社会的価値創造推進部や企業調査部、コーポレートアドバイザリー部、ストラクチャードファイナンス営業部など、複数部署が自然と関与するようになりました。イベント出展に関わってくれる仲間も増え、JAXAや自治体などとの連携も進んでいます。
SMFL 佐藤社内外ともに変化を感じています。JAXAとの共創活動やSPACE WEEKへの出展を通じて、社内含む各方面から問い合わせをいただく機会が増え、モチベーションの向上につながっています。
JRI 加藤お客さまの捉え方も、「宇宙=ロマン」から「宇宙=リアル」へと変化しています。ロケットや衛星にまつわるスタートアップ企業の実績が現実味を帯びるとともに、非宇宙系企業の参入が進んでいます。
さらに自治体においても、地場産業を宇宙に結びつけて振興やイノベーション拠点形成を目指す動きも出てきています。今後さらに多くの企業や自治体が、宇宙に取り組む機運が高まるのではないでしょうか。
SMBC VC 真鍋我々が出資している宇宙領域のスタートアップ企業が新たに資金調達をする際、これまで事業連携していた事業会社が大型の資金を投入するケースが増えているように感じています。研究開発や事業連携の面でも、宇宙領域への期待値が高まっている、ここ1~2年が大きな転換期だと感じます。
「宇宙のことなら、SMBCグループ」と言われる存在へ
最後に、今後の展望や目指す姿についてお聞かせください。
SMFL 佐藤「宇宙を起点にした設備投資に対するリースといえばSMFL」と思い出していただけるような実績を積み重ねたいです。将来的には人工衛星のリース実現などを通じて、新しい選択肢を世の中に示していきたいですね。
JRI 加藤ようやく宇宙ビジネスが現実味を帯び、宇宙港を中心としたまちづくりが出口のひとつとして見えてきました。そのチームの一員として、まちづくりも絡む分野に注力していきたいです。また、当社には多様な専門チームがあるので、さまざまな企業にとって「宇宙が自分ごとになる」きっかけを生み出せる存在になれればと思います。
SMBC VC 真鍋日本発のスタートアップがグローバル市場で存在感を示し、宇宙技術が社会・産業全体のイノベーションを牽引するためのご支援をしたいと考えています。そのために、異業種との協業やオープンイノベーションを推進し、SMBCグループのネットワークを活かして、スタートアップの可能性を更に広げていきたいと思います。
SMBC 横山「宇宙といえばSMBCグループ」と言われる存在を目指しています。今後もイベントへの共同出展や共創を通じて、さらに認知を広げていきます。

PROFILE※所属および肩書きは取材当時のものです。
-

株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門都市戦略グループ シニアマネジャー
加藤 大樹氏
2016年3月に東京工業大学大学院卒業後、同年に株式会社日本総合研究所に入社。官民連携事業である準天頂衛星運用事業等のアドバイザリー業務を皮切りに、衛星を活用した実証事業・研究開発事業支援、衛星や宇宙輸送に関する調査案件等、数多くの宇宙関連案件に従事。
-

三井住友ファイナンス&リース株式会社 ネクストビジネス開発部 主任
佐藤 壮祥氏
2019年に大学卒業後、三井住友ファイナンス&リースへ入社。大阪営業部にて在阪の中堅・中小企業向けのリース営業を経験。2021年よりネクストビジネス開発部へ異動し、宇宙チームでの活動を中心に新事業開発に従事。
-

SMBCベンチャーキャピタル 投資推進部
真鍋 晃太郎氏
2019年に三井住友銀行に入行。地元である四国法人営業部にて地場中小企業・スタートアップ向けの融資業務に従事した後、2023年にSMBCベンチャーキャピタルに異動。
「人生を賭けた起業家と伴に明るい未来を創造したい」という思いから、主にハードテック・ディープテック領域の案件ソーシング・DDを担当。社内では宇宙領域の知見を蓄積するために宇宙チームを発足し、業界の知見集約を行う。 -
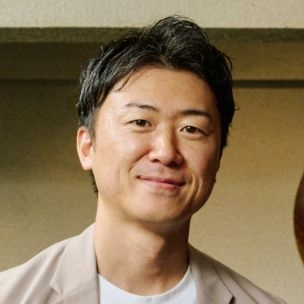
三井住友銀行 成長事業開発部 業務推進第一グループ長
横山 嵩氏
2009年に大学を卒業後、三井住友銀行に入行し、グローバル・アドバイザリー部で日系企業の海外進出支援に従事。2011年には赤坂法人営業部に異動、港区を中心とする中堅中小企業向けの法人営業を担当する傍ら、法人営業部では初のスタートアップ支援専門グループを立ち上げ。2014年にはトレードファイナンス営業部(東京)に異動し、大手日系企業および海外金融機関との貿易金融案件を担当。2015年には同部ドバイ拠点に赴任し、中東各国の地場金融機関を通じた地場企業向け輸出入支援に従事。2018年には同部ロンドン拠点に異動、アフリカ諸国の金融機関との提携促進や新たなファイナンス手法の企画設計を推進。2020年には成長事業開発部に異動し、スタートアップのバリューアップ支援や宇宙セクターの担当として、宇宙スタートアップ向けのファイナンス支援、各種イベント登壇、グループ会社との協業・共創支援を担当。
おすすめ記事
その他の記事を読む
-
 その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト
その他の記事もチェックDX-link(ディークロスリンク)Webサイト -
 最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント
最新情報はこちらDX-link(ディークロスリンク)X公式アカウント
アンケートご協力のお願い
この記事を読んだ感想で、
最も当てはまるものを1つお選びください。
アンケートにご協力いただき
ありがとうございました。
引き続き、DX-linkをお楽しみください。
